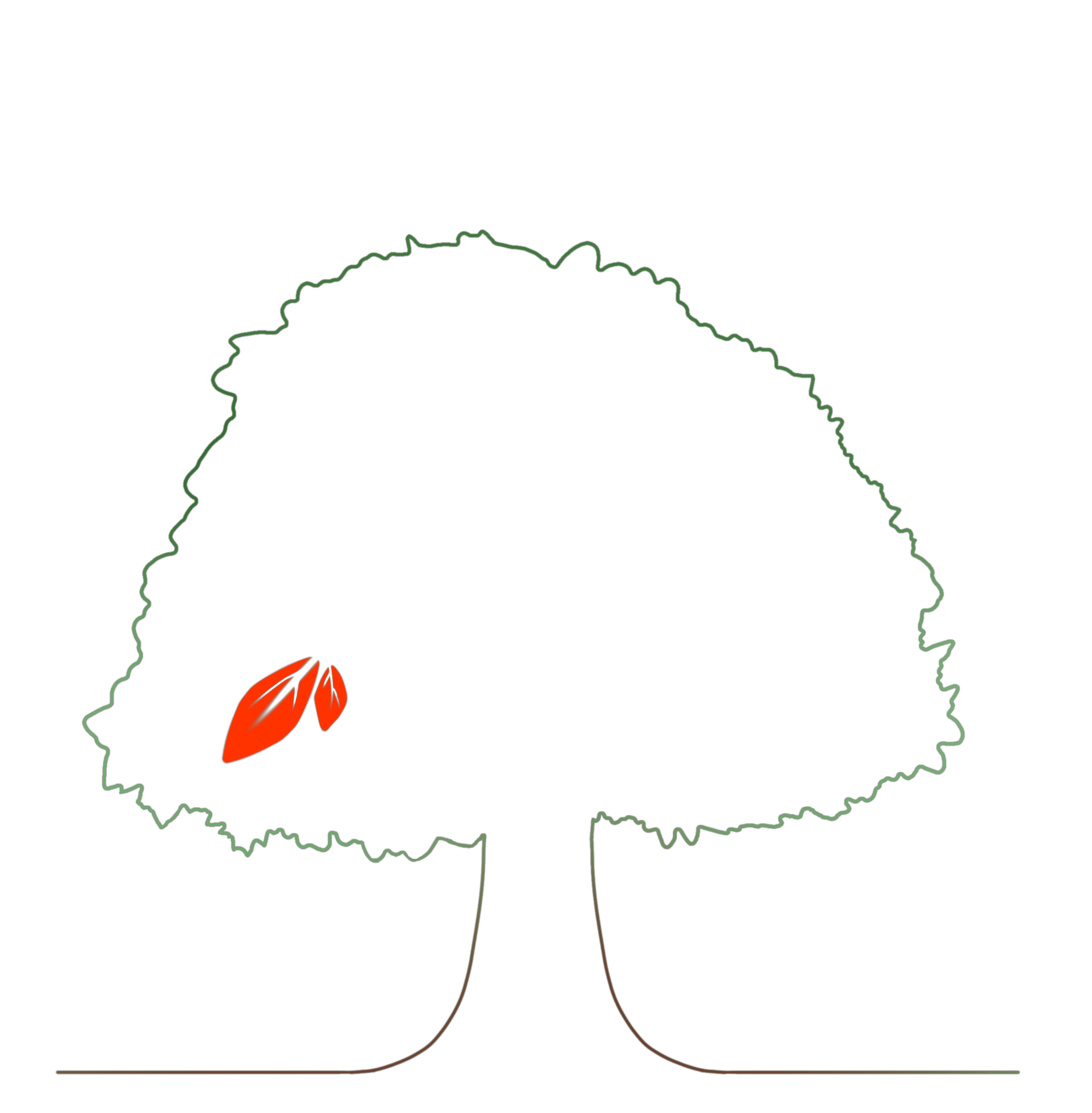最近、私のブログの中でアクセスが多いのが、
行政書士開業にまつわる過去のブログです。
今の時期は、試験に合格して、「さてその後どうしようか?」と、
人生の岐路に立たれている方も多いと思います。
私のブログが役に立つとは思いませんが、
当時と登録後1年8か月経った現在とでは、
私自身、少し変わった心境もありますので、
今日はその辺りも整理して2024年版でお話したいと思います。
なので、来年はまた変わっているかもしれません![]()
が、少しでも参考になればと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
まず、「行政書士として今から仕事をするか?」
それとも「更に別の資格を目指すか?」
「別の資格を目指す」については、
また別の機会にお話しすると思いますので、
ここからは「行政書士をやってみようか⁉」という方を前提で
お話を続けます。
「行政書士をやってみよう!」と決めると、
まず悩むのは、
「いきなり個人で独立するか?」
それとも「既存の行政書士事務所に雇ってもらうか?」
または「他士業の弁護士事務所や司法書士事務所などに雇ってもらうか?」
という選択だと思います。
これを大きく二つ「開業行政書士」と「勤務行政書士」に分けて、
最初に「勤務行政書士」のお話をします。
就職サイトなどを検索すると、
少ないながらも行政書士の募集は確かにあります。
ただ、何度か検索していると、
募集が長期間で、募集元もあまり変わらないことにも気づきます。
つまり、その行政書士事務所は、
「ちょっと問題があるのかもしれない。」という疑念が出て来ます(全部が全部とは申しませんが)
私の同期でも「勤務行政書士」の先生は何人かいらっしゃいますが、
聞いてみると一般募集ではなく、
コネや人伝手の方が多いようです。
この場合は、仮に自分が行政書士事務所を経営していて、
人手が足りなくて、「勤務行政書士」を雇いたいと考えれば、
自ずと想像はついてきます。
これは、後に書く事務所にも関わってきますが、
事務所を構えれば、かかる経費は少しでも安く抑えたい。
人件費も経費ですから、自ずとその対象です。
言葉は悪いですが「搾取する側」になるのか、
「搾取される側」になるのかの選択です。
勿論、メリットもあります。
「寄らば大樹の陰」で、
事務所がある限り余程のことがなければ安泰というメリットはあります。
安定していれば、将来への見通しもしやすいですし、
何よりも知識を得るにも環境が既に整っているという、
実務面での最大のメリットもあります。
そこに自分を当てはめて、
合致するのかを考えたら良いと思います。
しかし「せっかく国家資格を手に入れるチャンスを得たのに、
サラリーマンと同じようでは。。。」と思われた方は次に進みます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
次に「開業行政書士」ですが、
おそらく、このブログをここまで読まれた方は、
ここからが気になるのではないでしょうか?
ネット情報などでは、「まず専門を決める!」と言われますが、
正直、試験に合格したばかりで、
自分が行政書士として何を専門にやっていくのかなんて、
難しすぎると思います。
それは、もう少し後で良いです。
その前にまず開業資金です。
登録費用は所属書士会によって多少は異なりますが、
最初に30万円ほどは必要です。
次は、自分が行政書士としての軌道に乗せるための助走期間の目標設定です。
私は3年で設定しました。
早い人は1年目で軌道に乗せられるそうですが、
一般的な経験者のお話を聞くとだいたい3~5年だそうです。
この3~5年間というのは、逆に言うと、
新人の行政書士が振るい落とされる期間でもあります。
(かくいう私自身も、今この真っただ中です![]() )
)
そして「3年」と決めたら、そこから必要な経費を計算します。
この期間の生活費も勿論です。
自宅で開業するか事務所を借りるか。
私のお薦めは、事務所を借りておいて言うのもなんですが、
自宅です。
自宅でしたら行政書士の総売上がほぼそのまま純利益のなるからです。
しかし、事務所だと毎月経費が掛かります。
事務所賃料、月極駐車場代、光熱費、事務所での食事代他。
正直、事務所を借りる経費は、新人行政書士にはキツイです。
これは、元々のお金が有る無しに関わらず、
それ以上の売上を生み出さなければならないという、
試練が一つ増えるからです。
新人であるだけで試練なのですから、
試練は一つでも少ないほうがいい。
今の私なら、可能なら自宅開業をおすすめします。
私の支部で先輩行政書士に聞いても、
自宅開業の先生が圧倒的に多いです。
「家の玄関に一番近い部屋を事務所にした」という言葉はよく聞きます。
ただ、自宅が賃貸の場合は、
書士会の事務所開設の要件を満たすのが、
かなり難しいので、
どうしても事務所を借りることになってしまうと思います。
しかし、この場合にも「共同事務所」や「合同事務所」という方法で経費を抑える方法もあります。
同じ行政書士なら「共同事務所」、
他士業と組むなら「合同事務所」です。
登録申請の際に経費の区分を「折半」とか「〇分の1」とか
書いて提出すれば、毎月のかかる経費は押さえられます。
問題は、一緒にやってくれる同志がいるかということと、
その同僚と揉めたときです。
言ってみれば「パートナー」選びになるので、
事務所選び以上に慎重にならなければいけません。
しかし、上手く行けば、
経費を抑える以上のメリットもあります。
何よりも常に相談相手がいること、
扱える専門を増やしやすいということ、
パートナーが他士業でしたら、
業際問題を簡単にクリアして利益に結びつけやすいということ、
などです。
そして、ここまでが行政書士開業の1番目のハードルでもあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
次に先ほど少し触れた「専門を何にするか?」ですが、
よく「3つくらい専門を決めろ」と言われます。
しかし、そう簡単には決められないのが当たり前です。
そういう場合は、
まずは都道府県書士会が開催する基礎研修を、
時間が許す限り、片っ端から受講することです。
コロナのおかげで、
その殆どをオンラインでも受講できますが、
出来れば会場受講をおすすめします。
なぜなら、会場受講にくる行政書士は、
自分と同じ新人行政書士ばかりだからです。
そして、講師はその分野の専門家です。
言ってみれば、これはチャンスです![]()
会場に行って運悪く録画映像受講だったとしても、
会場の設営進行を担当する人たちも
一応行政書士だったりするからです。
また、隣の席になった人や、
休憩時間に挨拶や雑談をした人とは、
タイミングをみて、名刺交換をします。
(しばらくは、名刺ホルダーが行政書士の名刺だらけになる筈です![]() )
)
名刺交換をしたら、その日か翌日の午前中までには、
メールか電話で再度、挨拶と名刺交換のお礼を伝えます。
その際は相手の顔や話の内容を思い出しながら。
メールであれば、その時には気付かなかった疑問などを
話してみても、その後の話題に繋がります。
別に一方通行でもいいのです。
そういうやり取りから、
私の場合は5~6人くらいの会を3つ作りました。
今でも定期的にそれぞれに飲み会を開いています。
最初の頃は、集まりでの中心は、
「勤務行政書士」の方々の話です。
未だ仕事の無い、私のような他の「開業行政書士」は、
指をくわえて、
その先生の実務の話題に聞き入るのです![]()
実務の話を聞くと、焦りも感じますが、
実務の色々なポイントを知ることができます。
その場で変な質問をしても、お互いに一年生ですから![]()
出てきた単語でも、知らないことは覚えておいて、
あとで自分で調べてみるのです。
キーワードを繋いでいくと、
「ああ、あの先生は、今こんな仕事をされているんだ!」と、
仕事の概要が掴めたり、
「面白そうだから、この本を読んでみよう!」とか、
「次回は基礎研修じゃなくて、実務研修を受けてみよう!」
とか、色々な思いが浮かんできます。
そうやって裾野を広げていくと、
自ずと「自分に合うもの合わないもの」も見えてきます。
それでも何も専門が思いつかない人は、
浅くても良いので、守備範囲を広くとっておくことです。
そうしておけば、もし依頼がきても「やれるやれない」くらいの判断は出来ます。
まぁ、この時期に「やれる」という確信はないでしょうから、
「できそう」くらいで良いとは思いますが![]()
そして、その「やれる」「できそう」があなたの専門に一番近い物だと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
でも、営業はどうするのか?
ここが一番知りたい部分かもしれません。
返って不安を煽るようですが、
正直、これと言える答えはありません。
ホームページを作るとか、ブログを書くとか、
チラシを配布するとか、広告をうつとか、
色々な話がありますが、
まずはお金がかからない方法を選択すべきだと思います。
ホームページは着地点としてあったほうが良いでしょうし、
ブログは私の場合は、営業と言うより、ライフワークになっています。
私の場合、ホームページでは問い合わせが外国から来たくらいで、
ブログからは、相談を受けましたが、
結局ボランティアのような感じで終わりました。
最終的に、仕事と言えるものが来たのは人伝手で、
今はそこからの紹介紹介の繋がりです。
ただ、紹介とはいっても赤の他人なので、
ホームページやブログの存在が相手に安心感を与えたのではないかと思うことはあります。
なので、どこがどう繋がって仕事になったと明確には言えないので、
「答えはありません」という答えになってしまいます。
この答えは、組合で同席した、
ベテラン行政書士の先生も同じことを仰っていたので、
おそらくは、それで良いのではないかと思っています。
そして、今現段階の私が言えることは、
「不安を忘れる程にポジティヴに動くこと。」
これに尽きると思います。
その為に「自分が動ける環境を作っておくこと。」が大切だと思います。
他人のために業として働くのが行政書士であるならば、
まさにそういうことだと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「実務が来たらどうするの?」
仕事が欲しい欲しいと思いつつも、
実際に依頼があると、
「果たして自分に出来るのか?」
と逃げ出したくなる不安に駆られるのは、
私だけではないと思います![]()
「ネットで調べろ!」という人もいますが、
これは半分正解で半分不正解です。
これを書くと、同業から文句が出そうですが、
ネットに出ている情報のほぼその殆どは、
誘導広告と思っても良いと思います。
そもそも論で、行政書士がホームページ作って、
そこに答えが書いてあったら、誰も依頼しないですよね![]()
つまり殆どは、入口だけです。
では、ネットでは何を信用すれば良いのかというと、
行政庁のホームページです。
ここには基本的に誤った情報はありません。
答えがあるとは限りませんが、
少なくとも信ぴょう性ではぴか一です。
行政書士であれば、まず行政庁のホームページをチェックすべきです。
そして、ホームページでも判らない場合は、
直接、行政庁へ問い合わせをします。
しかし、この場合も知識ゼロで聞くのではなく、
ある程度基本知識を備えた上で、
先方の答えが最小限で済むように配慮すべきです。
ここら辺りからが、行政書士の腕の見せ所だと思っています。
そして、そこから得た深い知識を蓄積することが、
行政書士の価値だとも思います。
ただし、最初はそうは言っても、なかなかしどろもどろで、
論点を得ないのが、普通でしょう。
私もそうです。
最初から上手にできる人なんて一握りです。
そういう時は、行政書士の県会や支部会が主催する
無料相談会を利用すれば良いのです。
相談会は基本的に誰でも相談に行けます。
だから、行政書士が相談に行っても良いのです。
県会に直接問い合わせることも可能ですが、
都合さえつけば、無料相談会を利用すべきです。
なぜなら、先方も相談に乗りたくて、
ウズウズして待ってますから![]()
そして、相談会で担当される先生は、
皆さん知識豊富で、親身になって下さる先生ばかりなので、
まず答えが出ないという事はありません。
ピンチはチャンスです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さて、以上ここまでザーッと私なりの経験と考えを書いてきましたが、
あくまでも私個人の意見ということで、収めて頂ければ幸いです。
本当は文字に起こしながら「もっと言いたい」ということは
沢山ありましたが、
そこはそこ、行政書士としての隠し味的な部分もあるので、
敢えて控えました。
試験に合格して迷っておられる方々の一助になればと思い、
書かせていただきましたが、私もまだヒヨコ🐤ですから、
「行政書士になろう!」と思われたら、
是非一緒に頑張りましょう!
長文にお付き合いいただき、ありがとうございます。