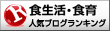“秋を愛する人は心深き人~♪”
“冬を愛する人は心強き人~♪”
すいません、今回は『四季の歌』から入ってみました。
それはさておき、あなたは春夏秋冬、
どの季節に一番、愛着を感じますか?
好きな季節が到来する、それだけで心が落ち着いたり、ワクワクしたり。
“なんか良いことが起こりそう!”
そんなトキメキの予感があったりもするものです。
今回は、「季節と発酵」、「旬と発酵」をテーマに、医者を遠ざけ、クスリを拒む。
そんな生き方のポイントについて述べてみたいと思います。
■不自然な納豆は!?
「納豆」
納豆と言えば、朝ご飯の定番メニューです。
ネバネバ納豆を食べて、
ガマン強く、ネバリ強く・・・。
そんな気持ちを込めて、食べている人もいるのではないでしょうか?
でも、本来納豆は、
「秋冬の食べもの」
夏や春に口にできるようなものではなかったのです。
なぜ、
春と夏は納豆を食べられないのか?
それは納豆熟成の主役、
“納豆菌”
にその理由があるのです。
納豆菌はあのネバネバを生み出す源になるのですが、彼らが好む季節は、
「秋から冬」
夏場は気温が高くなるので、納豆菌の活動は意気消沈。
弱まってしまうのです。
到底、糸を引くような発酵作業はできなくなる。
だから、春夏に納豆を食べること自体に
ムリがある。
納豆菌は涼しくなった秋口から活動のギアを上げていき、雪がチラつく季節の到来とともに、
“エンジン全開!出力MAX!”
こんな感じで本領発揮となるのです。
“私たちは秋と冬を愛しているの。だから性格はココロ深くて、ココロ強い感じになるの”
納豆菌はギラギラした夏の温度を好まない、そうした特徴を持った菌なのです。
「枯草菌」とも呼ばれています。
原料となるワラも大豆も、秋に収穫するものだから当然、
秋冬の食べものになる。
こうした次第になるわけです。
野菜に「旬」があるように、納豆にも適した季節というものがある。
納豆の旬は、
「秋から冬」
になる。
野菜も生きもの・菌たちも生きもの。
それぞれが好み、愛する季節というものがある。
『四季の歌』に続いて、『僕らはみんな生きている』を歌いたくなってきました!
■夏納豆の実態は!?
強力糸引き納豆、臭わない納豆。
反対に、
糸を引かない納豆、さらに納豆をドリンクにした無臭納豆。
これらはいずれも不自然で反自然なシロモノですが、
「夏に売られる納豆」
これもひどく不自然なものといえるのです。
それを可能にするのが、
化学操作・化学培養技術。
中には強力な紫外線や、放射線、ガンマ線などを納豆菌に浴びせかけて菌の
「突然変異」
を誘発しているケースもあるのです。
人間の都合に合わせた菌になるように生命を化学の力で作り変える。
こうした事情が納豆にもあるのです。
※参考:化学操作・化学培養の詳しい実態は以下を参照してみてください。
『自然食関係者が業界ぐるみでヒタ隠しにする・食の安全アノ事情を業界OBが真相暴露!』
■反自然・不健康の極み
納豆づくりには発酵に必要な、
「室(ムロ)」
が必要になります。
ムロとは、納豆菌専用の発酵部屋に当たります。
これは納豆菌が快適に発酵・熟成作業が行われるように工夫された部屋のこと。
夏でもムロの外の温度を低くできるのなら、“ウマい納豆”を熟成させることができるのです。
大型の冷蔵庫のようなものの中に、ムロを設置して、その中で熟成させる。
それが可能であれば夏場の納豆も食べられるといった次第です。
後ほど紹介する「天然ワラ納豆ふくふく」は、こうした設備を持っているので、
夏場でも天然の納豆菌によるワラ納豆を作ることができるのです。
トマトやキュウリに旬があるように、
納豆菌にも旬がある。
発酵食品とは、
「素材選び・温度管理・加工技術」
といった様々な条件を揃えて初めて作り出すことができる。
こうした設備と技術がなければ、天然菌による夏の納豆づくりは不可能なわけです。
そのため昔の人たちは、夏には「干し納豆」を食べていたのです。
■教訓を政策に!
もちろん「天然菌ワラ納豆ふくふく」が支持を集める理由は単に、
天然菌だけの力によるものではありません。
大豆をじっくり煮詰めて、菌が入りやすい絶妙な柔らかさに仕上げること。
この煮豆の技術が“匠のワザ”になるのです。
煮豆の美味しさと天然菌の働き、そして快適な設備。
さらに菌の力が弱まらないようにと、井戸水を殺菌していないこともポイント。
実験で塩素殺菌した井戸水で作ってみたところ、目指す味から
“ホド遠い”
ものになってしまったとのことです。
こうした実験と試行錯誤を経て、「ふくふく納豆」は
「大人気商品!」
となった次第です。
有機野菜の宅配や自然食品店等で売られているのは、
化学操作・化学培養された納豆菌ばかりです。
中には、容器としてワラに包んでいるものもありますが、それはタダの包材に過ぎません。
ぜひ自然本来の旨味引き立つ、本物のワラ納豆をぜひ一度お試ししてみてください。
難点はちょっと、ワラから納豆を離すのに手間取ることと、お値段の高さですかね。
繊細な菌の世界への誘い。
そしてその菌たちの活動を最大限サポートし、引き出す
「匠なる技」
味の良さの背景に潜む、こうしたストーリーを踏まえて、味わいたいものですね。
■天然菌ワラ納豆ふくふく・アマゾンで購入
・伝統製法を復活・天然わら納豆 「ふくふく」300g 1本(6~8人分)★国産無農薬大豆★クール冷蔵便配送★少量生産のため数量に限りがあります。
■天然菌ワラ納豆ふくふく・楽天市場で購入
■“食の安全”・百冊読むよりこの9章!
■参考文献
・『自然食の裏側』 三好基晴 著 かんき出版刊
・「ハイテク化された発酵醸造菌」:http://kinsyoukai.fc2web.com/hakkou1.htm