『割れ窓理論』
建物の窓が壊れているのを放置すると、「誰も注意を払っていない」という象徴になり、やがて他の窓も破壊されていくという、アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングが考案した理論です。
その当時の理論にいたった過程と考察に関しては賛否があるのですが、割れた窓の放置に限らず、ゴミのポス捨てや落書き、放置自転車など、軽微な犯罪や風紀の乱れを放置しておくと、「誰もこの地域の治安に関心を払っていない」というサインになり、犯罪を引き起こすリスクを高めてしまうという内容が、現代の『環境犯罪学』では述べられています。従って、そういった風紀の乱れや軽微な犯罪を小まめに、徹底的に取り締まることが、凶悪犯罪を含めた、犯罪の抑止に繋がり、住民の安全・安心にも繋がるのです。

『環境犯罪学』は、犯罪を取り巻く様々な環境に着目し、効果的な犯罪の予防を目的とする学問です。この学問の前提には、犯罪者と非犯罪者の間には大きな人格的差異は無く、『犯罪を行える』という機会に遭遇してしまえば、なかには理性を押さえきれず犯罪を実行してしまう人もいる、という性悪説があります。従ってそういった潜在的犯罪意識を覚醒させないために、日常生活における様々な環境を整備し、犯行には都合の悪い状況を作り出す事が大切だ、という事です。
その具体的な方法としては
・犯罪者の手間を増やす(近づき難くする。出入りのセキュリティ強化)。
・犯罪者のリスクを上げる(自己防衛の意識。人の目を増やす。見通しを良くする。法律の整備、罪の厳罰化)。
・犯罪者への挑発を減らす(対象となる事を回避する)。
・犯罪者の意欲を低下させる(管理が及んでいる事、治安が行き届いている事を示す)
などが挙げられます。
それでもなお、何事も恐れずに犯行に及ぶ人間もいる、という事を常に念頭に置き、自己防衛を心掛けなければいけません。

こういった環境が及ぼす人への影響の学問は、学校教育やビジネスの現場でも活用されています。
例えばスティーブ・ジョブズがアップルに戻った時、最初に行った仕事は『働く環境の徹底的な整備』でした。常態化していた遅刻を厳罰化し、喫煙も禁止、福利厚生制度を見直して、サバティカル制度(長すぎる休暇)も廃止しました。 クリエイティブな企業だと、私語OK、時間は自由、区切られたデスクは書類が山積みといったイメージがあるかも知れません。しかしそれでは業務効率は上がらず、仕事もいい加減になるというのがジョブズの理論でした。汚い作業環境では「これでいいや」という無意識の妥協を生み、仕事の完成度に甘さがあっても許容してしまい、そのいい加減さが不正などを招くまでに至る、という考えです。片付けない→非効率かつ、いい加減で良いという妥協→更に片付けない…という負の連鎖で、環境は悪化し生産性は落ちていきます。作業環境が整然としており綺麗な状態であれば人間心理の常として「やはりいい加減な仕事できない」と思うのです。
つまりスティーブ・ジョブズは、或いはアップルという会社は、個人の能力や組織力が優れている、というだけでなく、個人の能力やアイディアを極限まで引き出し、組織力を最大にするためには、『働く環境を徹底的に整える必要があることを理解し、実践した』のです。「身の回りの整理整頓」「あさイチのメール処理」「職場の近くに住む」など、当たり前のことを当たり前にする。その微々たる環境や決まり事の習慣化が、1年後2年後には人として、組織として、大きな差を生み出すのはご理解いただけるでしょう。そしてそれらが無理難題ではない事もお分かりいただけると思います。

さて、ここからが本題です。とは言っても、みなさんもはやお解りでしょう。身の回りの環境が及ぼす、人体への影響は、犯罪率や仕事の効率だけでなく、健康の維持・増進にも通じるのです。視覚(無意識の内に目から入ってくる様々な情報)、聴覚(音楽や言葉や声のトーン)、臭覚(アロマテラピーなどの香りからフェロモンまで)、味覚(日々口にするするモノの内容)、触覚(身につけるモノや触れるモノの質感)など、24時間絶え間なく、無意識の内に触れているモノ全てが、心身の調律に影響を与えているのです。
悪いモノは遠ざけて、良いモノは近づける。その微々たる積み重ねで心身は調律されていくのです。
遠ざけるモノの1例で言えば、ネガティブな情報や誇大広告などが挙げられます。あらゆる広告媒体やメディアが、人の健康不安を煽り、依存させたり慢性化させたりしようと仕掛けてきます。とりあえず、という習慣でつけているテレビや、何となく見ている雑誌から、無意識の内に次から次へと送り込まれてくるネガティブな情報の影響は、決して無視できません。プラシーボ効果やノセボ効果、プライミング効果などと呼ばれるモノがあるように、無意識の内に情報が擦り込まれることで、痛くないのに痛いと感じたり、必要ないのに必要だと思いこんだり、病気でもないのにネガティブな情報や言葉で不安になり体調を崩したりすることが、人間の身体では起こりうるのです。
みなさん一人ひとりが、そういった情報や言葉に触れた時、「真実なのかどうか?」「自分に有益なのかどうか?」を冷静に、化学的・統計的に正しいかを判断するリテラシーが養われているなら問題ないのですが、日本人の多くは、情報を疑い、自分で検討、検証することが苦手なようです。だからこそ、まずはネガティブな情報に触れる機会を減らす、或いはむやみに信じないと自分に何度も言い聞かせる、というふうにして環境を整えるのです。
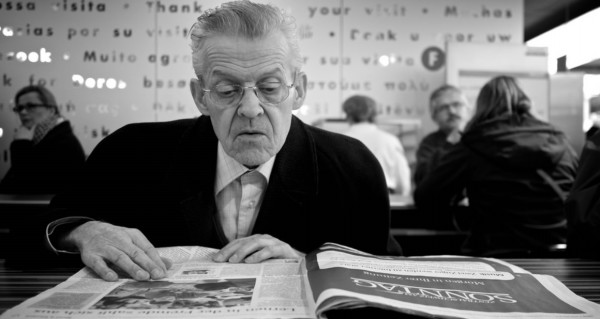
次に良いモノを近づける1例です。
私が個人的によく質問されることは「どうしていつも赤い服を着てるんですか?」と「どうして金髪なんですか?」という内容です。一言でいうと「そうする方が、調子が良いから」です。
私は元来、内向的で、人見知りで、放置しておくと鬱に傾く、ダウン傾向な性格です。それぞれの色に対するイメージは人によって異なりますが、私は赤とかオレンジから、太陽や血や情熱や前向きなエネルギーなどをイメージします。一般的にもその傾向はあるようで、赤系統の服を着たり、部屋に入ったりすると、血圧が上がったり、体温が上昇するという研究結果もあります。また黄色に関しても、輝き、希望、黄金、ヒラメキといったイメージがあり、私が前向きになって突き進むのに必要な力を与えてくれます。私はこういった色からイメージを受けて、活力に変換し、ダウン傾向の性質をアップ傾向に引き上げているのです。そうやって心身のバランスを調整してやることで、放置していれば起きたかも知れない鬱的な気分の落ち込みを、未然に防いでいるのです。勿論色だけではなく、音楽や香り、食事などにも配慮しています。

心身調律は、良い状態を維持する力、自分で整えようとする力、自然治癒力や免疫力を無意識下で最大限引き出すことが目的の1つです。その時、絶対的に必要となるのは自分で自分を良くしていくんだという意志の力です。誰かに治してもらおう、薬でどうにでもなる、マッサージとか整体で良くなる、といった他人やモノに依存する心は、状態を悪化、慢性化させ、回復を遅らせてしまいます。
と言うと「意志弱いんだもん」と、即座にネガティブな事を口にする人もいます。意志が弱い、という意志を貫くことだけは強いんですね、と言いたくなりますが、つまり面倒くさいのでしょう。そうやってすぐに言い訳をして、自分には責任がないというスタンスをとる癖がついている人にこそ実践して欲しいのです。
まずは環境から整えましょう。環境犯罪学やビジネスの現場なども含め、ここまで紹介した内容は、それほど難しいことではなかったでしょう。日常生活においても、冷蔵庫の中を整理にする。トイレを綺麗にする。身だしなみを整える。約束や時間は守る。一気にやらなくて良いのです。ひとつひとつ整えていけば、自ずと気持ちも整ってきて、それが行動に反映され、身体の状態も変わってきます。また逆に神経質すぎる人は、リラックス出来る香りや音楽、笑える映像や音源などを生活の中に取り入れ、高すぎる緊張感を緩める方に調律します。
正解はありません。医者や著名人やメディアで言われていたから、それが全て正解で、全ての人に有効という訳ではありません。身体と日々向き合っていれば、今日の正解と、1週間後、1年後の正解が違ってくることに気付くでしょう。
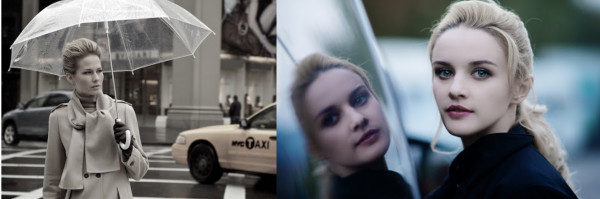
自分の身体が何を求めているのか?
自分はどういう状態に持っていきたいのか?
いつも何気なく見ているテレビや雑誌の情報は、自分をどう形作っているのか?
本当に有益で必要なのか?
周りの人達からの影響は?
周りの色、音、香り、食事からの影響は?
全ての選択の自由は自分にあるのです。たまには時間を作って、自分自身と、五感が触れている人やモノについて、ゆっくりと考えてください。ストレスになっているモノがあれば遠ざけて、感謝すべきモノがあるなら大切にする。それだけで心が穏やかになり、時として涙が溢れてきます。
1つ大きく深呼吸して、周りをサッと眺めてみる。
何か乱れているモノ、汚れている場所があれば、ササッと直す。
もう一度元の場所に戻り、直した箇所を見つめ直す。
ほら気持ち良い。
環境を整える作業は、心を整える作業。
ようこそ心身調律へ。
2016年4月9日 サクラ舞い散る目黒川のほとりで。
一般社団法人日本トレーナー協会代表理事 生西聖治