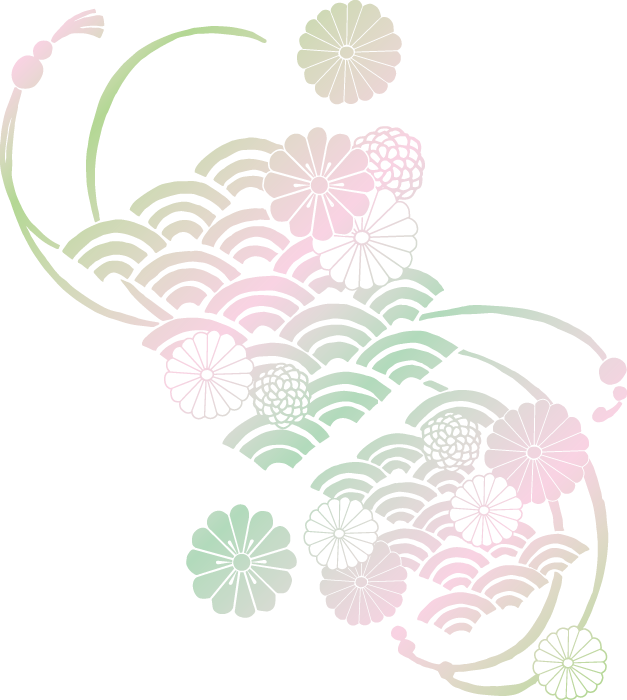東洋医学において
身体の仕組みや病気の成り立ちを
理解するために考え出されたのが
気・血・津液という三要素です。
大雑把にいうと
気は生命エネルギー、
血は血液およびその働き、
津液は血液以外の水分を指します。
それぞれ体内で作られ
それを担うのが腎・脾・肺です。
西洋医学では腎臓・脾臓・肺が
その臓器を指すのに対して
東洋医学ではそれが持つ
働きまで含めて捉えます。
三つの違いをみると
腎;生まれながらに持っている
脾;飲み物や食べ物を材料にする
肺;外界との往来に関わるバリアやフィルター
と言えます。
*******************
気・血・津液は互いに深い関わりがあり
生成プロセスや運搬プロセス、
調整プロセスにおいて支え合っています。
お互いが無くてはならない関係なのです。
東洋医学の根本である整体観では
人間は自然の一部であり
体内にも自然界と同じ構造がある
と考えています。
なので身体の中をイメージするのには
自然界で起こる様々な事象を眺めるのが
良いかもしれません。
太陽エネルギーが海を温め
雲を作り雨を降らせる。
気温差で風が吹き、種が飛ばされる。
大地の養分が芽吹きを助け
育った植物が動物を養う。
時がくれば命は尽きて
やがて土に還り、土を肥やす。
互いに関わり合って
巡っていることが分かりますね。
***********
自然界も人間の身体も
個々の要素の量と動きがちょうど良く
しかもお互いが時々に合わせて
調和していることが大事。
変化に応じてそれぞれが
ちょうど良く変化することで
全てが良好に向かっていきます。
これが自然治癒力ですね。
反対にどこか一部分に不具合が生じれば
その影響は全体に及びます。
地球温暖化も人体の病気も
何かのどこかの変化が
全体に影響した結果なのでしょう。
気を巡らす気功体操はもちろん
血や津液の巡りも促します。
無理なく動きながら
その時々のちょうど良いを実感しつつ
全体として調和した状態を目指します。
**************
参考文献;『東洋医学 基本としくみ』(仙頭正四郎 監修/西東社)