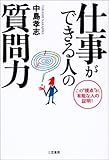本日の紹介はこちらです。
↓↓↓
【出会い】
「ケアマネジャーに必要な質問力」という電子書籍を書いていた時に、ブックオフの105円コーナーで発見しました。
【本書のテーマ】
質問力を磨くには?
【岡本大輔の視点】
介護現場で使いたい質問力。
【気になった抜粋】
質問というのは、お互いの「伝えたつもり」「わかったつもり」というミス・コミュニケーションを防ぐためにあるのだ。
人が行動を起こす時、その大もとにあるのは動機づけである。
「それはできません」「いままでやったことがありません」「無理です」この一つ覚えが思い浮かんだら、次のように自分に質問してみてはどうだろう?①時間をかければどうか?②やり方と仕組みを換えればどうか?③みんなでやったなら、どうだろうか?
「納得できない」ということは、いい換えれば、「想像もできない」という意味だ。
松下幸之助さんの口癖・・・「君、どう思う?」。
一日はどんな人間にも24時間しかない。
行動しない人間に限って、きっかけが欲しいと叫ぶ、きっかけなどなくても、始める人間は始める。
【響いた抜粋と学び】
質問とは問題点を明らかにし、正解をつくっていく技術そのものだ。
ケアマネジメントや介護現場では今目の前にいるお客様にはどのような課題があるのか、明らかにして対応策や必要な介護サービスを結びつけるわけです。
そこに至るまでには質問するわけです。
僕は先日、とあるお客様に質問をしたことがあります。お金を遣い過ぎる方です。
お金がなくて、年金支給日から2週間たつとご飯がまともに食べられない。この状態は大変だと感じ、お金の使い方について質問をしたところ、課題点が明確になりました。
本人にとって、年金が支給された当日にお金がなくなることが問題だと思っていないこと、お金がない間はツケなどで食いつなぐ状態を普通だと考えていることに問題があると知ったのです。
知らない人は「質問したくても、何を質問していいのかさえわからない」のである、事情を呑み込んでいる人だけが質問できるのだ。
ケアマネジメントの現場や研修でこのような状況になりえると感じます。ということは、事前に事情を把握しておく前準備が必要であるし、研修前で言えば、自分は何のためにこの研修に参加し、何を学ぶのか、この研修のポイントは何かを考える必要があります。
松下幸之助・・・「石炭のことは石炭に聞いてみる。これがいちばん、いいのではないですか?」。
実は、「松下幸之助さんから学ぶ介護」(仮)という電子書籍も書いています。
松下幸之助さんのエピソードは僕達介護職にもよく当てはまります。
認知症が重くて、自分の気持ちを訴えられないお客様に対して、僕はこの言葉が頭をよぎります。
「お客様のことはお客様に聴いてみる。」、これは当たり前だと思われるかもしれませんが、現実のケアマネジメントや介護現場ではお客様をそっちのけて、家族の意向や介護職の考えだけが先走ることがあります。
本人の考えは?本人はどうしたいと思う?
ここを忘れてはいけません。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
コメントは自由制です。一見さんも読者も大歓迎です。
返信は24時間以内にいたします。
※心無い非難・誹謗・中傷等は削除させていただきます。