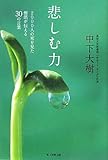みなさん、おはようございます。
あかりデイサービスでは
毎年恒例の秋の行事
観楓会・・・
(本州では
紅葉狩りと
表現した方が
ピンとくるでしょうか?)
を開催しています。
北海道
十勝・帯広では
紅葉の見ごろと
なっています。
さて、
ここ一ヶ月に
なりましょうか。
僕は、
「生・死」
に関する書籍を
借りて続けています。
以前に読んだ書籍の
自分の葬式をどうするか?
そこから人生を逆算する。
というのが
頭に残っていたのでしょう。
単純に同業者・・・
介護職の死を看取った話を
読むだけでなく、
異業種の言葉を参考に
学んでいます。
今回は中下大樹さん・・・
僧侶から学びます。
故小林正観さんの書籍でも
多くありました。
お釈迦様の考え。
僕は今まで無宗教で
特別信じるものがありません。
しかし、正観さんの書籍を
読んでいくうちに
お釈迦様の考え、教えに
非常に興味を持っています。
中下さんの書籍も同様です。
仏教では「悲しみ」の心を
大切にしている。
例えば「慈悲」
著者の見解では
「悲しみ」から「慈しみ」が
生まれると話しています。
「悲しみ」から目をそらさずに
受け止めることができた方ほど
穏やかな気持ちになれる。
ここに自分の見解も
加えたいと思います。
福祉の現場でも
悲しみ・・・特に人の「死」は
避けられがちです。
しかし、自分の人生を
振り返ったときに
考えるのは
「喜び」を共有する仲間は
素晴らしいが
自分の「悲しみ」を共感し
受け止めてくれる仲間が
いたのなら・・・
もっと素晴らしい。
「悲しみ」はネガティブなこと。
みんなが避けたいことを
受け止めてくれる仲間が
いたら、人はもっと
幸せになるだろう。
そう感じました。
一切皆苦・・・
人生は苦しくて当たり前。
仏教では上記のとおり、
人生とは苦しいのが
当たり前なんだそうです。
この部分を読んで、
高齢者との関わりや
今までの会話を
思い出すと、
(もちろん加齢に伴って
ネガティブになることが
ありますが)
そうなのか、
だから日本人はネガティブなんだ
と感じました。
1000年以上前から
人生とは苦しいもの
と教えられてきた。
で、あれば
ネガティブにもなるし
謙遜の文化が根付く
そう納得しました。
僕は自己啓発本や
セミナーなどそれなりに
経験し、並みの介護職よりも
ポジティブイメージを有しています。
しかし、それは日本の文化という
レベルで考えると
珍しいことなのだと
気付きました。
日本は無宗教の人も
多いのですが、
古来日本は
稲作伝来と一緒に
確か仏教も伝来し、
わが国で一番多い宗教は
仏教なはずで
学校を生徒が掃除をするなどは
仏教の影響でしょう。
納得しました。
最後に
本書に載っていた
マザーテレサの言葉を
紹介します。
「自分の家族の外で人々に
ほほえむのはたやすいこと。
あまり知らない人を世話するのは
とてもかんたんなこと。
家の中で毎日会っている家族を
思いやりをもって、やさしく、
ほほえみを忘れずに
愛し続けることはとても難しいこと。」
この言葉に
今後の家族ケア、居宅ケアが
記されていると
直感しました。
今までの僕は
介護職として・・・
どうして
自分の親のことなのに
とか
親子がどうして
話し合えないのか
そんなことばかり嘆いていました。
しかし、
違うのです。
家族だからです。
今まで身近にいたからこそです。
当たり前のように近くにいて
当たり前のように顔を合わせる
そんな仲だからこそ、
難しいのです。
デイサービスの相談員として、
介護支援専門員として、
家族関係の悪いケースを
何度も僕は見ています。
今まで
「家族なのに・・・」
と思っていたことが
「家族だからこそなんだ。
家族だからケアが難しい。
だからこそ、僕たちプロが
存在する意味がある。
僕たち介護のプロが
誕生したんだ。」
そう胸をはれます。
さらに考えれば
そう多くはないでしょうが、
昔の人は子育てから
介護から
すべて自宅でやっていた人たちは
「素晴らしい」
その一言に尽きます。
人との関わり。
身近な人との関わりほど
難しいことはない。
そう思い知らされた
一冊でした。
デイの生活相談員や
それに準ずる方。
介護支援専門員は
絶対読め!!
と推奨します。