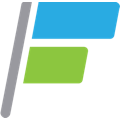「20年前」と比べて、その言葉の「意味合い」が大きく変化した言葉っていうのはいろいろあるんです。
たとえば「アマゾン」。
それこそ「20年前」であれば、ただ単に「密林」という意味でしか存在しなかった言葉でしたが、今では「第一義的」に、「ネット通販」を思い浮かべる人が大半でしょう。
同じように、「楽天」もそうです。
こちらも当然ながら、元々は「くよくよしないで人生を楽観すること。」という辞書的な意味合いが存在するわけですが、やはり「ネット通販」を思い浮かべる人が大半でしょう。
そして「炎上」。
こちらも当然ながら、「火が燃えあがること。」という辞書的な意味合いが存在するわけですが、やはり今では、「ネット炎上」として使われることが大半になったのではないかと思っています。
そして、ここで書きたい今日のテーマは「利する」という言葉。
もう今の時代は、「ビジネスの場」でも使う人は減った気がします。
無論、日常で「利する」を使う人は…皆無でしょう(^_^;)
これ。辞書的な意味合いは、「(その者の)ためになるようにする。利益・便宜があるようにする。」なのですが…
「りする」という発音が、「ディスる=disる」(俗に、相手を否定する、または侮辱することなどを意味する表現)と酷似しているがゆえ、取って代わってしまった気がしたんです。
日常で全く使われなくなったこの「利する」ですが、ニュースでは時たま使われているんですね。
たとえば、「この政策は、結果的に中国を利することになり…」などの使われ方なんです。
文章として書けばなんの違和感もありません。
ただ、いざこれがニュースで読まれると…
「この政策は、結果的に中国をディスることになり…」と受け取られるようになり…
ネット上→「今ニュースで中国をディスることになりって聞こえて、ついにニュースでもそんなスラング使うのかと思ったら、利するか。聞き間違えるわ。」
「中国をディスるって…そんな言い方ニュースで言っていいのかよって思ってたら違った。」
ニュースでも頻繁に使われるわけではない「利する」という言葉ですからね。
流れた途端、Twitter検索して「ネット上の反応」を確かめるようにしているんです(^o^;)
「利する」と「ディスる」。
大昔から存在する「利する」と、時代を経て誕生した「ディスる」という、「正反対の意味」でも「似た発音の言葉」が交錯する瞬間、というのがある意味「興味深い瞬間」でもあるんです(;・∀・)
以前、NHK「おはよう日本」の関東甲信越ローカルの枠にて。
茨城県東茨城郡城里町古内地区にて生産されている「古内茶」というお茶が取り上げられていたことがありました。
読み方は、ふるうちちゃ。
で、聞いていてあれ?と思ったのが…
「フルーツ茶」と聞こえるよなと(;・∀・)
で、案の定、Twitter検索をかければ出てくる出てくる…
「茨城県でフルーツ茶なるものがあるって。なかなか斬新だなと思って画面見たら古内茶とは…」
「NHKで茨城県にフルーツ茶なるお茶がある、水戸黄門も絶賛したというから、ホウ、そんなお茶があるのか。甘いのかね?と画面をみたら古内茶(ふるうちちゃ)だった。」
「フルーツ茶って言ってて、フルーツ茶って何よ?フレーバー?って思っていたら古内茶 とのこと。 ふるうち?ふるうつ?…これってやっぱり茨城なまりなのかなぁ~?」
「テレビから「フルーツ茶」と聞こえてきて、果物フレーバーのお茶なんかな? と思ってたら「古内茶」だった」
そして、予想外の反響に対して、町も公式に反応しています。
※古内地区地域協議会公式Twitter(当時)より。
「古内茶がフルーツ茶に聴こえる謎現象、思ってたんと違う反響だけど、なんでだろう凄く嬉しい。」
「古内茶でツイート(当時)して頂いただけで感謝です。 この際、フルーツ茶でも良いのではと悪魔のささやきがあったのはここだけの秘密です。」
日本語として古くからある言葉が、広く知られている「カタカナ語」に取って代わってしまう。
それがまったく違う言葉になってしまうというのは、日本くらいなんでしょうかね(;^ω^)
でも、「利する」というワードがニュースで出てきたときは、必ずX(旧Twitter)の検索かけて確認しています。
どんな勘違いPOSTがあるかなって(;^_^A
今日は、「利する」という言葉について取り上げてみました('ω')ノ
当ブログに対するご意見は、こちらからどうぞ(^^)/