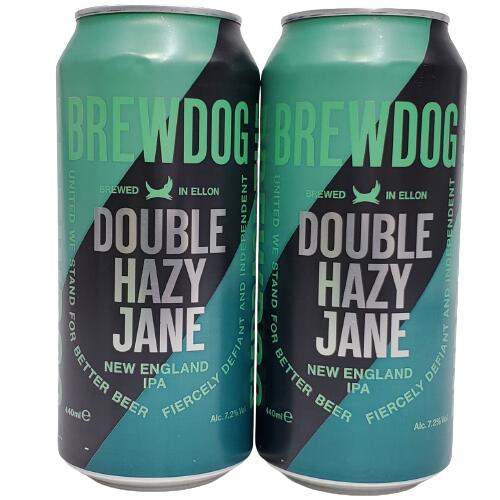Bavaria レモンラガーを飲んでみました。
昔の週刊の漫画ってジャンプ、サンデー、マガジン
チャンピオンとあって、私の回りはほとんどジャンプを
読んでいて、サンデー、マガジン、チャンピオンって
喫茶店か床屋でしか読まなかった記憶があります。
その中でチャンピオンは一番手にとるチャンスが
すくなかったのになんでマカロニほうれん荘だけは
おぼえているのかな?
Bavariaのレモンラガーがあったので
買って見ました。
早速飲んで見ると
ただの甘いレモンジュース!
アルコールも2%です。
私も若くてお酒を飲み始めたばかりだったら
こういうジュースみたいで
飲みやすいお酒にはまったかもしれません。
でもオヤジにはちょっと甘すぎですね。
Bavariaってオランダでは有名なビールだけど
まだBavariaの普通のビールは紹介して
いませんでした。
Bavariaは1719年創業のブルワリーだそうです。