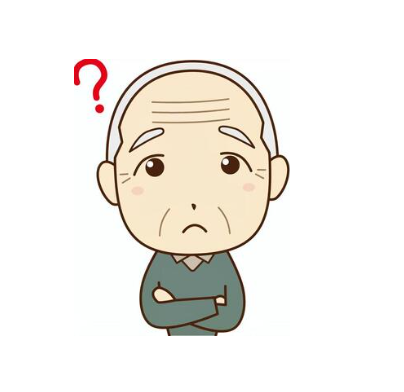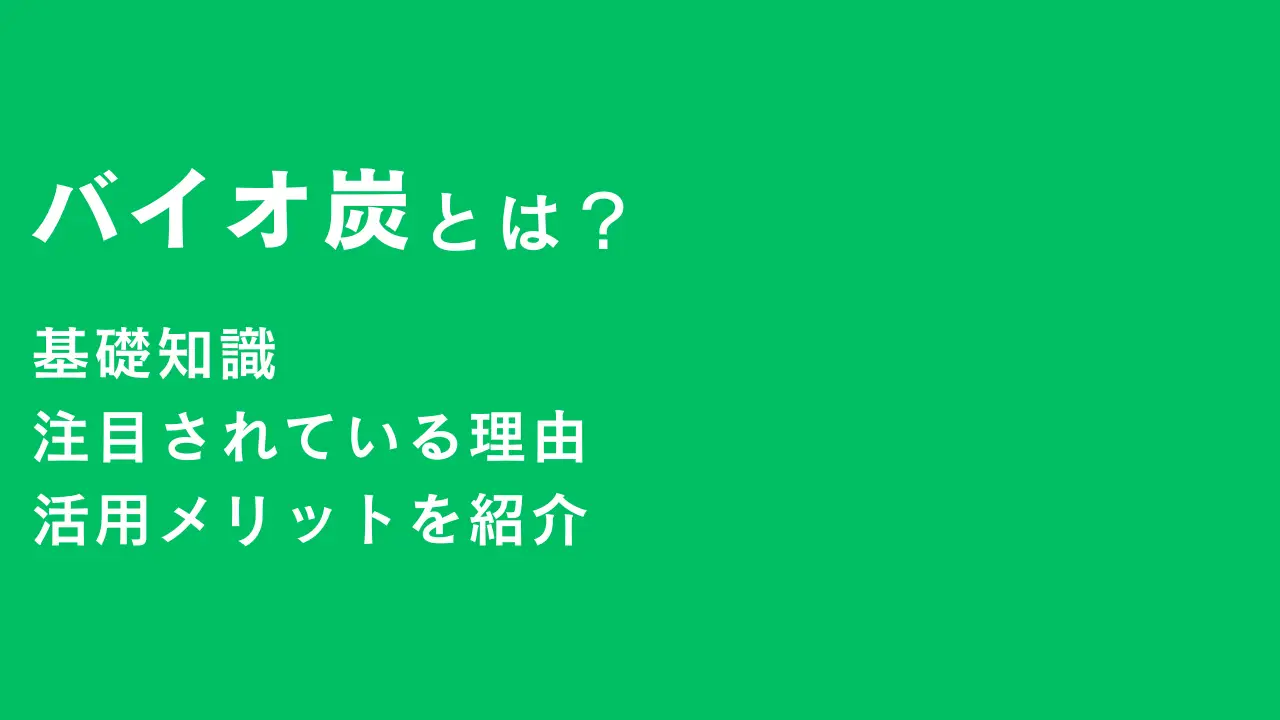前回書いたバイオチャーとカーボンクレジットの話の続き。
カーボンクレジットの言葉は以前から聞くが、今の処世界共通の一つのルールがあるという訳ではなくて、今後環境整備が進んでいく様だ。因みにカーボンクレジットを皮肉っぽく言えば、自分でCO2削減が出来ない企業が、排出権を買って責任を逃れるというメカニズムと言える。映画や小説では「何でもお金で解決できると考える様な大金持ちは、鼻持ちならない嫌な奴」というのが通り相場のイメージだが、事ビジネスの世界となると当たり前の話になってしまうのは、資本主義では致し方ないのだろう。
また排出権を売る立場の人達も、お金の為の活動と聞くと何か功利的で本来の価値を下げる様な印象を持ってしまう事がある様だ。因みに、私が参加しているボランティアのいすみ竹炭研究会の会長に、「竹炭の炭素固定をカーボンクレジットで資金化する予定はありますか」と話題にした時には、「お金の為にやっているんではないので、興味はありません」と一蹴され、そんな事を聞いた自分が何だか気恥ずかしい思いになった。そう言えば、以前マイケルサンデル教授が「原発から出る放射性廃棄物を何処に埋めるか」という悩ましいテーマに関して似た様なエピソードを紹介していたが、確かこんな内容だった。候補に挙がった米国内の大半の自治体は受け入れ反対だったが、ある自治体の住民は「誰かがやるしかないなら自分達が受け入れよう」という使命感の様な意見で過半数が纏まった。然し政府が補償金を幾らにするかという議題で会合を呼び掛けた途端に、住民たちは反対派に回ったと言う。理屈は、自分達は飽くまで国全体の為に敢えて犠牲になろうと申し出たのであって、金の為ではなかったのに今更お金の話を持ち出されて侮辱された、という意識だという。人は利己的な生き物と言われる一方で純粋に高潔な人達も居るというエピソードは、我が身を振り返ると忸怩たる思いだが、何れにせよ心が温まるものだ。
とは言え理想論は別にして、大半の私の様な人達はお金に絡める事で経済原理に乗って炭素固定を意識する様になり、活動がより盛んになる事は間違いないと言えるので、現実問題は実社会で脱炭素が進む為には必要且つ有効なシステムに違いない。