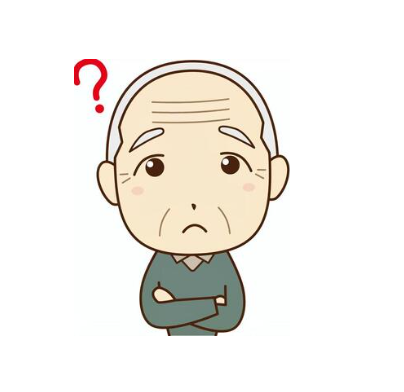以前のブログで、「高関税での管理貿易や自国優先主義は遠からず自分の国にも悪影響を与える事になるだろうが、今はそんな理屈は相手にされない」と書いたが、そのメカニズムを明確には説明出来なかった。
鍵となる式は以下だ。(紫文字は本文から抜粋)
(1)国内総支出+輸出=国内総生産+輸入
(国内総支出とは消費支出や住宅投資など国民の豊かさに繋がる物。右側は付加価値の総額であり、国内総生産とは国内での生産で、輸入は他国での生産である)
⇒ 式左側の「輸出」を右側に移すと以下の式になる
(2)国内総支出=国内総生産+経常赤字 (経常赤字=輸入-輸出)
トランプは高関税で輸入を減らして経常赤字を減らそうとしているが、これは式で判る様に国内総支出という国民の豊かさを減らす事になる。つまりトランプは国民を不幸せにしようとしている事になる。
そうは言っても経常赤字で国民が豊かになるという図式は持続可能なのか、という素朴な疑問は出て来る。
その点は以下の式で考えるとイメージが見えて来る。
(3)経常収支の赤字=金融収支の黒字
経常収支=貿易収支+サービス収支
金融収支= 海外資産からの収益+対外借り入れの増加+海外資産の取り崩し
経常収支の赤字が続き、しかも、海外資産からの収益だけでそれを賄うことができないとすれば、海外資産を取り崩すか、海外からの借り入れを増やすしかない。しかし、そのような国に投資するのは極めて危険なことだ。対外資産が減少して、それを返済することができないような事態に陥る可能性が高いからだ。だから、借り入れを増加し続けることができなくなるだろう。
対外収支の赤字とは、極端にいえば「働かないで食べていける」ということだ。そんなうまい状態をいつまでも続けられないのは、当然といえば当然のことだ。
要するに、トランプが心配する様に、貿易赤字が続く事は不健全ではあるのだが、では此れ迄アメリカは何故長期に渡り貿易赤字を続けながら、国民は豊かになり続けられたのかとなる。その理由はアメリカという国への信頼感が大前提にあり、それを元にドルが国際的な基軸通貨として通用して来たので、長期に渡る経常赤字は問題にならなかったという理屈だ。
そして「アメリカへの信頼」の基盤として以下の点が上げられている。
一人の独裁者に権力が集中してしまうことがないように、三権分立が機能している。
そして中央銀行の独立性が保障されている。
このような制度的な仕組みによって、バランスのある安定した政策が実行される。
そして、自由な研究活動が認められるので、能力のある人々が世界中から集まってくる。
基礎的な研究開発に資源が投入され、新しい技術が開発される。
こうしたことによって新技術が開発され、新しい経済活動が興る。
そして経済成長を持続できる。
それに加えて、軍事的・地政学的な優位性を保持している。
このため、ドル資産を保有してもデフォルトの危険は少なく、将来、十分なリターンを伴って回収できると確信できる。
トランプは三権分立を骨抜きにし大統領三選も画策している節があり、中銀への圧力を強めたり、ハーバード大学の留学生受け入れを禁止したりと、アメリカの信頼性を失わせる施策のオンパレードである。
トランプの愚策と言われる所以だが、果たして本人や取り巻き達はこの様な指摘を冷静に議論する節度を備えているのだろうか。裸の大様に本音をぶつける家臣は居ないというのが通り相場であり、だからこそ裸の王様なのだが、矢張り困りものだ。