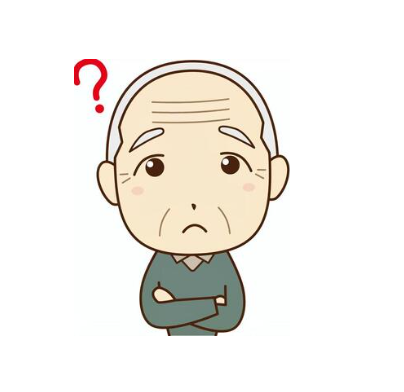前回に続き協生農法の話。
菌ちゃん農法を実践中の私としても協生農法は期待度大の農法だと感じるのだが、
TBS番組ビデオのユーチューブには否定的コメントもあるので抜粋してみる(紫文字)。
土地生産性は確実に落ちるし、結局多くの土地での生産管理が必要になる。こういうのを信じたり頼る人は、大概周りの農地に病害虫をまき散らして迷惑をかけていることに気づかない人が多い。
一定規模の土地で、連作障害を考慮しながら最大効率で肥料農薬を効かせて、最大限の土地生産性を上げることが減肥減農薬の近道。
自然農法や菌ちゃん農法では良く言われるが、微生物が豊かな土になると、虫にとっては食べ難い元気な野菜が育つようになるので、厄介な虫が寄り付かなくなる様だ。
この種の農業は手間ひまが非常に多くかかり、収量が少ないので農家にとっては採算がとれない。
だから素人が採算抜きの趣味でやるに良いと思う。現代農業の抱える問題の抜本解決にはならない。
奇跡のリンゴの木村秋則氏や菌ちゃんファームの吉田俊道氏は、既に採算が取れる経営を実践していると聞く。土地の履歴や気候風土他色々な要素が絡むので、誰がやっても100%上手く行くとは断言できないものの、少なくとも可能性がある事は間違いない様だ。
面積当たりの収量は確実に落ちるし、秀品率も落ちます。少なくとも慣行農法から転換して何年間は。
反収いくらで利益がこれだけという思考を変えない限り、一般の農家がこの手の農法には移行できないと思います。
50年前から、有機農法や無農薬無肥料栽培が提唱されて熱烈な支持者がいるのに、有機農法の耕作面積は日本の農地の0.6%と言われています。
耳障りの良いことだけ強調して、負の面にほとんどまったく触れないのは昔から変わらない。変わらないから拡大しないのではないでしょうか。
前回のブログでも書いた通り、人類の存在自体が多かれ少なかれ自然環境を壊すという不都合な真実からは逃れられないが、生き残りの為には、肥料・農薬の悪影響を極小化する意識と施策が最優先課題だろうと思う。生産性・事業性等で色々ハンデがあるという意見は、食わず嫌いの偏見も混じっているとは感じるものの、大筋では理解できるし、慣行農法の当事者としては単純に無肥料・無農薬栽培に移行は出来ないと思うが、其処で思考停止にならずに圃場の一部だけでも実験的に始めてみるというアプローチはあって良いのではと思う。
これは菌ちゃん農法でも言える事だが、裾野が広がり、実績が積み上がり、世代交代が進めば、現在日本の農業の99%以上を占める慣行農法に携わる農家・学者・政治家等関係者の見方が変わり、消費者の意識や要求も変わる、という流れは起こり得ると期待したいものだ。
続きは次回