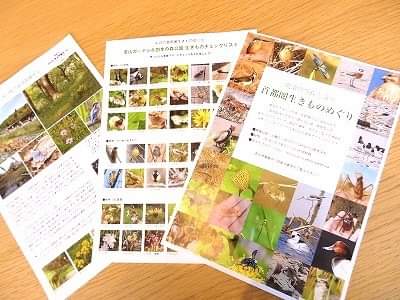お約束通り、前回の続きです。
1ヶ月弱の間を置いて再び代々木公園へ。
パークガーデンアワードの会場を巡り、
昆虫を探してみます。
東京で育つ宿根草の多くは
夏以降に開花の最盛期を迎えるもの。
つまり、予定通りに植物が成長すれば
ちょうどこれくらいの時期が一番見頃になるはずです。
実際、前回と比べても花の量が多く見応えがありましたが
一方で一部の花壇では、暑さのためか「枯れ」も見られ
宿根草花壇づくりが一筋縄ではいかないことがよくわかります。
(実際、東京では育てられない宿根草も多数あります)
左はニホンミツバチ。右はアカスジカメムシ。
いずれもここではポピュラーな昆虫ですが
前回と比べるとカメムシの方は多かった気がします。
前にも書きましたが、ここは殺虫剤が使えず
捕殺するにしても花壇を作った皆さんが
毎日通うわけにはいきません(地方の方もいますし)。
東京近郊ですと、花壇にセリ科の植物を植えて
そのまま何もしなければ高確率で奴は来ます。
今後、何らかの対策がとられる可能性はありそうです。
(私はただ撮影するだけです(爆))
左のクマバチがとまっているこの花は
上のニホンミツバチが来ているのと同じ種で
アガスターシェというシソ科の常緑多年草です。
この植物が、この日はとにかく多くの虫を呼んでおり
大活躍している印象でした。
アオスジアゲハ(右)のいるバーベナもそうですが
小さな花がたくさん集まって咲く植物は
本当に昆虫にとってはありがたい存在のようです。
特に、ラベンダーやアガスターシェの属するシソ科は
花の蜜が美味しいのか、よくハチがやってきます。
ちなみに日本だと一年草扱いされていますが
コリウスもシソ科で、昆虫の蜜源として活躍します。
一応、これは新顔のハチになります。
オオフタオビドロバチといい
竹筒や木材などの中に巣を作って
イ●ムシを運び込み、幼虫のエサにするタイプのハチです。
遭遇率・・・3(珍しいハチではない)
インパクト・・・2 (ミツバチよりやや大きい程度)
美しさ・・・2 (黒と黄色のハチらしい配色)
俊敏性・・・4 (多くのハチに準じる)
知名度・・・2 (本種を呼ぶためにバグハウスを設置する人も)
実はここのコンテストガーデンの一つに
竹筒を敷き詰めて彼らが巣を作れるようにした
「バグハウス」を設置しているところがあります。
もしかしたらそこから……と一瞬思いましたが
コンテストガーデンの造成工事は昨年12月にスタートしたばかりで
その頃にドロバチの成虫が飛び回ることは考えにくいので
まあ、順当に明治神宮から飛んできたのでしょう。
もちろん、今後バグハウスで営巣する可能性はありますし
そうなればコンテストにおいても高く評価されることでしょう。
スズバチが地面を掘っていました。
ガーデンの中ではなく、外側です。
ニホンミツバチを仕留めたシオヤアブ。
小昆虫の数がグンと増えているので
こういう肉食昆虫が来るのも当然の流れです。
トップの方でも書きました通り
ガーデン内の宿根草は最盛期でした。
この後、秋に向かうに連れて
咲く花の種類は大分変わっていくようです。
そういう季節の「変化」を楽しむのも
宿根草ガーデンの醍醐味と言えるでしょう。
このガーデンでは、レイズドベッドで立ち上げたり
コンポストを設置したりといった工夫も。
南国風の大きな葉の植物もユニークですね。
バーベナ(紫)とフェンネル(黄)で高さを、
アガスターシェ(薄紫)などで横幅を担保し、
足下はキク科の植物で埋める……というデザイン。
もちろん植え込み時点では「こうなるだろう」と
予測・イメージしてデザインすることしかできません。
今のこの姿も、まさに植物のプロだからこそできる芸術。
今更ですが、ガーデナーの皆さんには本当に感心します。
ぶっちゃけタダで見ているだけの私としては
感謝の言葉しかありません。
翅を閉じたテングチョウ。
本ブログではよく春先に登場していますが
本来は1年に2回発生する傾向にあり、
夏場でも6~7月に発生するようです。
モデルガーデン『クラウド』へ。
こちらでもアガスターシェが目立っています。
俯瞰で見てみましょう。
奥に見える鬱蒼とした明治神宮の森と
控え目な花色中心のガーデンが良く調和しています。
白い花はアガパンサスで、よく見る紫のものよりやや小型。
オリンピック宿舎をバックに。
マメコガネ(左)がかなり増えてきました。
前回は見かけなかったので、一気に羽化した模様。
イチモンジセセリ(右)も出ていましたが
こちらはまだ1頭しか見られませんでした。
マメコガネは、セリ科一辺倒のアカスジカメムシと違い
様々な種類の植物の葉を食べることで
農業・園芸界隈ではかなりの嫌われ者となっています。
今後の真夏に向かっていく中での動向が気になるところです。
最後に、吸蜜中のモモブトスカシバです。
都会の公園で見る機会は滅多にないですが
恐らくこれも明治神宮から飛んできたのでしょう。
この日は2個体ほど見かけております。
何気に、こういうホバリングしている姿は
今回初めて撮影したものになります。
「モモブト」という名前の通り
後脚が太い……というより剛毛に覆われ
飛んでいるとそれが特によく目立ちますね。
別角度からもう一枚。
後脚の毛は赤・黄・黒の3色で構成され
なかなかお洒落と言えるかもしれません。
何しろ今までこういうシーンを
一度も撮影したことがなかったもので
こんなに顕著に「モモブト」だとは思いませんでした。
代々木公園といえば、目と鼻の先が若者の町 原宿。
そういえば若い女性の間でこういうブーツが
流行したような気がするのですが……
冷静に思い出すと私の学生時代の話でした。
(要は20年くらい昔の話)
流行についていけない私ですが
そもそも学生時代から流行に疎かったので
何を今更という感が拭えなかったりします(爆)
【7/7 代々木公園で撮影した生きもの】
鳥類・・・ヒヨドリ
昆虫類・・・アオスジアゲハ、アカスジカメムシ、イチモンジセセリ、オオフタオビドロバチ、オオモンツチバチ、キイロスズメバチ、クマバチ、シオヤアブ、スズバチ、セイヨウミツバチ、ツマグロヒョウモン、テングチョウ、ナナホシテントウ、ナミテントウ、ニホンミツバチ、ハラアカヤドリハキリバチ、マメコガネ、モモブトスカシバ、モンシロチョウ、ルリシジミ
★次回、生きもの探索ツアー「首都圏生きものめぐり」は
2023年8月20日(日)に開催いたします。
行先は「小山田緑地(東京都町田市)」でございます。
現在お申込を受付中です。ご興味のある方はこちらよりお申込ください。
(講座の概要につきましてはこちらをご参照ください)
【小学校6年生までのお子さんのご参加につきまして】
小学校6年生までの方は、初回500円でご参加いただけます。
ただし、御父兄の同行をお願いいたします。