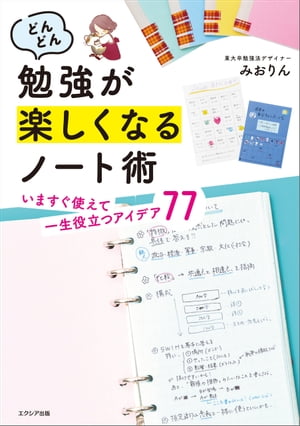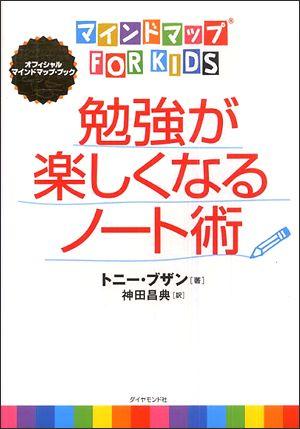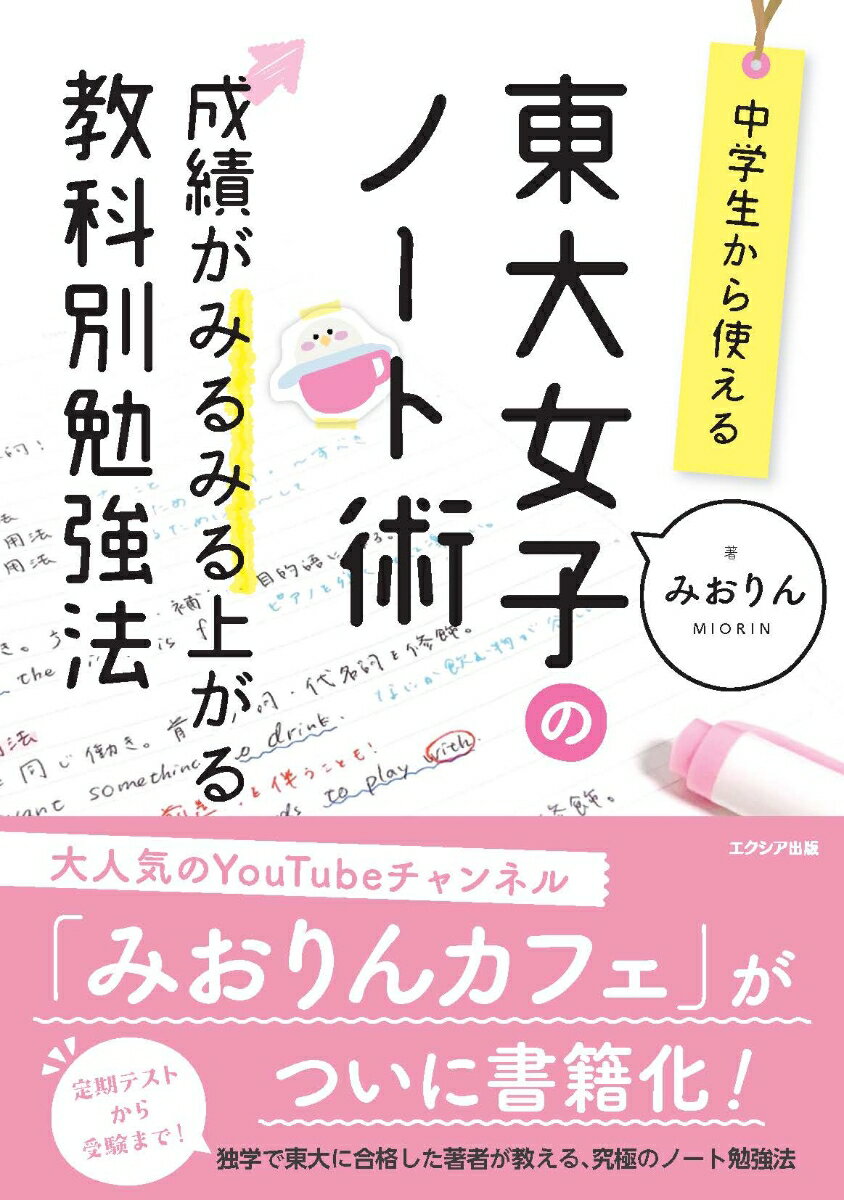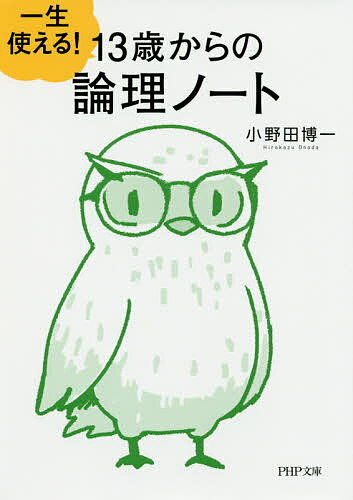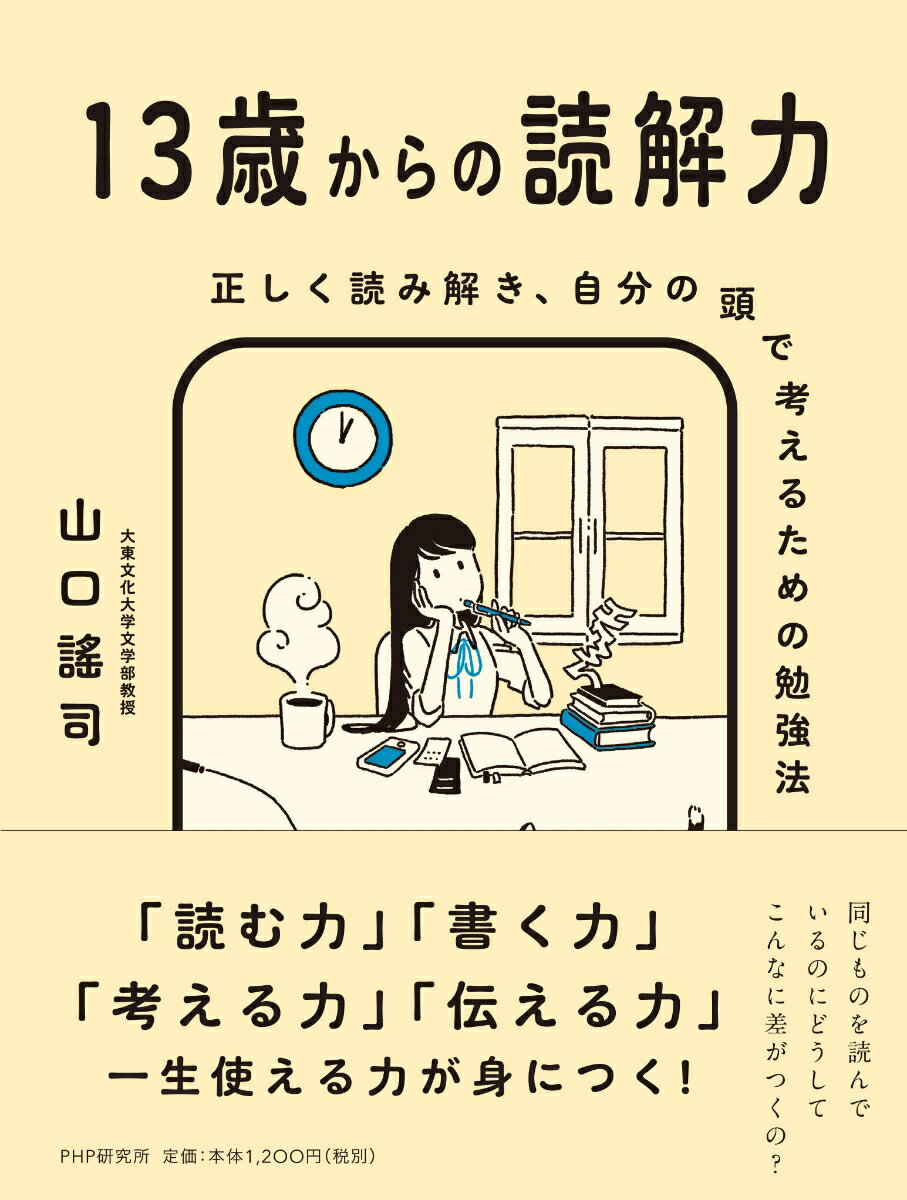教科書、参考書、ラーニングなど、少し文字数が多いと、「読まない、読めない、理解できない」というルーチンになってしまうようです。
でもこれは、自学学習(自習)をする上では、大きなデメリットになります。
何せ文字が読めないのですから、「書いてある内容が判らない=解けない」ということになり、勉強する気になっても一発アウトになってしまう感じです。
この症状が起こると、授業が聞けないので、先生の話す内容が理解できない!
↓↓
判らないので寝てしまう
↓↓
平常点が下がる
↓↓
定期テストで点数が取れても、5段階成績は結構下がる
↓↓
内申点が下がる
↓↓
入試でランクを下げねばならない
というルーチンになってしまうかもです。
教科書でもなんでも良いのですが、読んでみて「判らない」ということになってとき、子供達はどうしているのでしょう??
いま、塾では、ノートの作成方法をやっています。
ま、言ってしまえば、自分が判りやすいノートを書けば良いのですが、みんなノートを活用したことが無い!汗

タブレットの影響もあるかもしれませんが、
「短時間で図解や先生が話した内容などのメモを取る」
ということが出来ていない。
また暗記(記憶)する時のノートも、上手く作っておけば、試験の時などに役立ちます。
これも実際にノートを一緒に作ってみて、やらせてみます。
教科書、問題集などの文章を少しずつ読み進めて、どの単語から理解が出来なくなったのかを確かめます。
これは実際に本人に解説をさせます。
途中で行き詰まるところがあります。
または、意味が判っていないで説明をしているところが見受けられたら、こちらから質問をします。
「〇〇って書いてあるけど、この意味はどんなこと?」
それらをノートに落とし込んでいきます。
塾には、参考書、教科書などがありますので、場合によっては自分で携帯で調べたりもありとします。
これをやると、自分で文章を作らねばいけないので、良い練習になります。
意味を調べ、その解き方もノートに書いていきます。
授業でもそのノートを使い、どんどん加えていきます。
世界に1冊の大事なノートの出来上がりです。
また文章を読むコツを、順次書いていこうと思います!
-------------------------