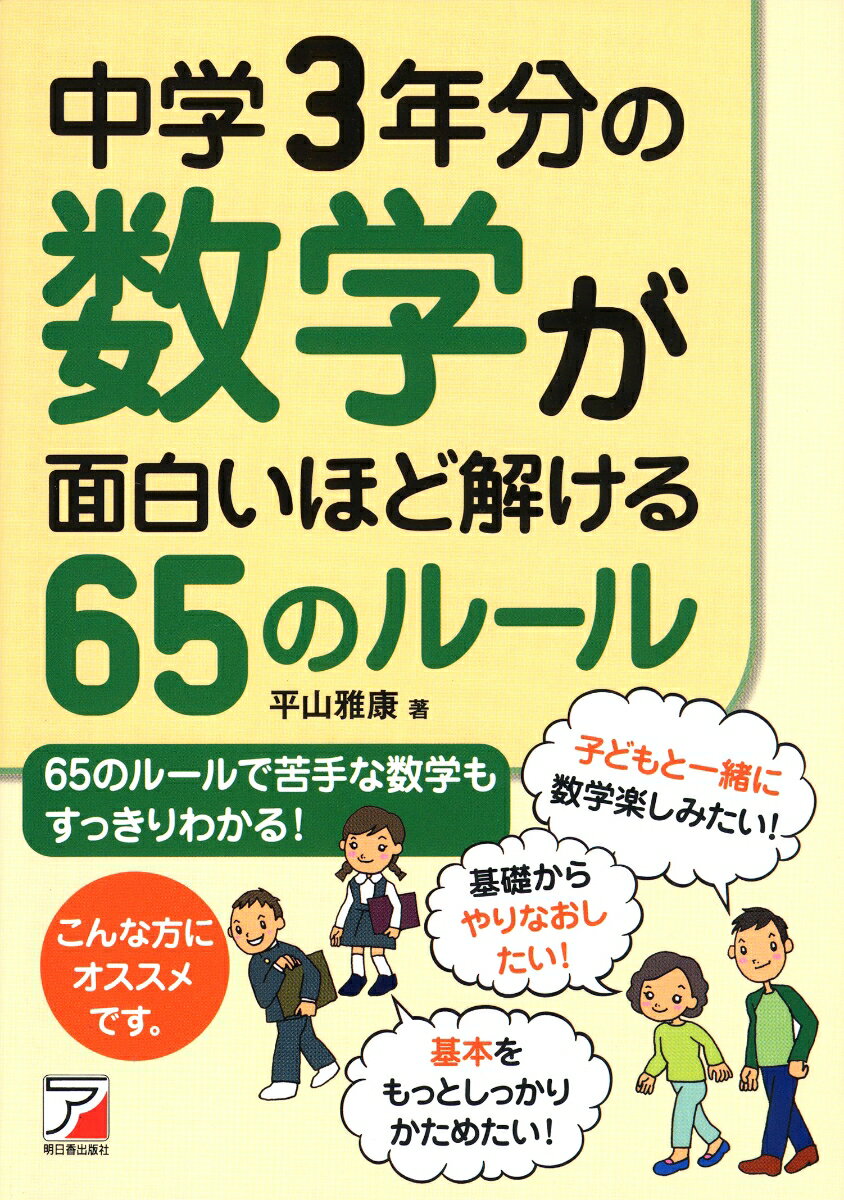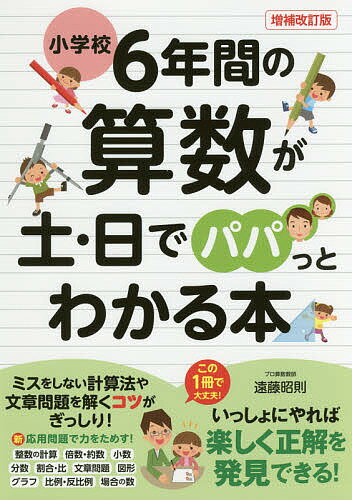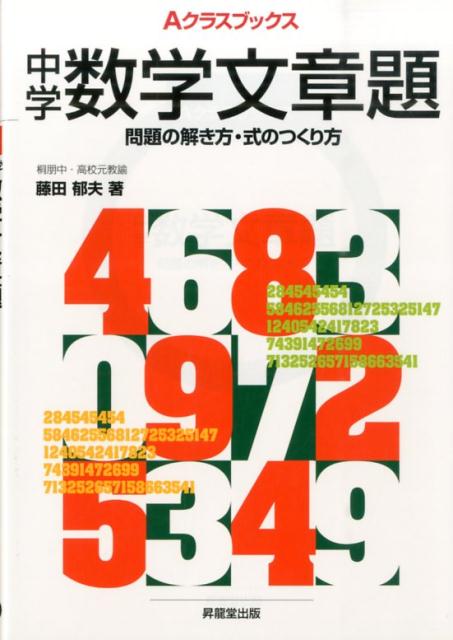問題の中で、子供達の苦手ナンバー1は、「文章問題」かな~と思います。苦笑
小学校の時は、そんなに長い文章問題は少なく、また問題を理解するのにも、そんなに複雑では無いかなと思ったりしています。
まず、何が出来ないのかというと、
1:そもそも、読まない
2:読めない=読んでも理解できない
1の読まないのは、「読む気が無い」=解けないという諦めから読もうとしない。
解こうとしないので、いつまで経っても解くことが出来ない。
これは「2」の所にも通じるのですが、まずは1つずつ問題を読むことが大切なのですが、子供の理解度は千差万別で、理解スピードが違うので、出来ない子は判らないまま読み進めてしまうので、余計に判らなくなってしまうのです。

そこで対応法ということで、「読書をすると良い」ということが先生たちからも言われることがあるみたいなのですが、個人的には、推奨していません。
読書は大事ですし、色々な本を読んで欲しいとは思いますが、文学作品を読んだところで、「方程式を組み立て解く」ということにはならないと思っています。
それよりは、まず問題に何が書かれているのかを理解し(これが出来ないので解説をしたいと思います))、式を立てることができるようにすることが、一番の対応策かと思います。
そして類似問題を沢山解くことで、苦手意識も無くなっていきます!!
【例題】
例えば、以下の問題があります。中2の連立方程式です。
----------------
2桁の整数があり、この整数の10の位の数と1の位の数の和は8になる。また、この数の10の位と1の位を入れかえてできる整数は、もとの整数よりも36大きくなる。もとの2けたの整数を求めなさい。
これを解けるようにするのに、推奨文学作品を読んでも解けるようにはならないかと思います。
そこで、細切れにして、まず何が判らないかを探していきます。
まず、「2桁の整数」とあります。
整数って何?
ということから考えます。
定義をしっかりいえるかどうかを確認します。
次に2桁の数字は、「37」と書かれていれば、小学校低学年でも「さんじゅうご」と読むでしょう。
数字は、3と7ですが、並んでいると「さんじゅうなな」と読み、10が3個と1が7個だと判っているけれど、37をどうやって表すかがわからない。
そして次に「10の位、1の位」ってなんだ?
「和」とは何??
と、一つずつ解析をしていきます。
判らなくなって所で、それを調べます。
または先生、友達、塾の講師などに質問をします。
自分は、「ここまでは判ったけれど、ここが判らない」と、判断・説明ができるようになれば凄い進歩です。
良く私は、「問題の意味は判りますか?」と聞きます。
「はい」と答えても、実際は判っていないことが多いので、確実に判っているかをチェックして行きます。
そして、これらを正確に、詳細にノートに書く練習をします。
地道な作業ですが、これが一番早く、正確に問題を解くことができるようになると思います。
----------------------------