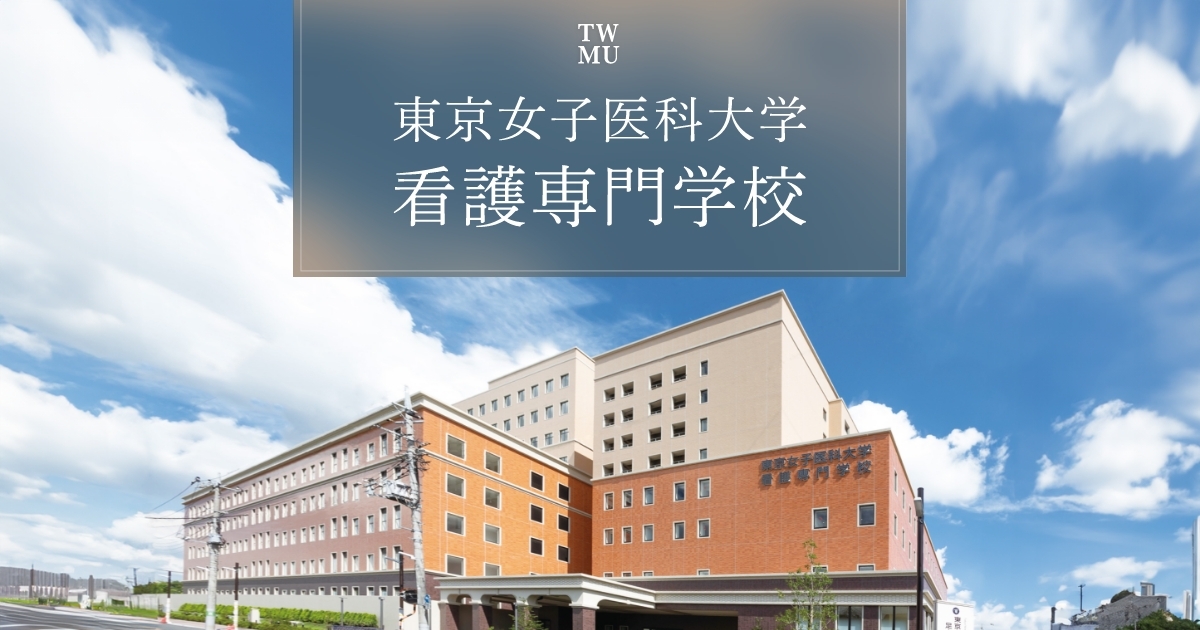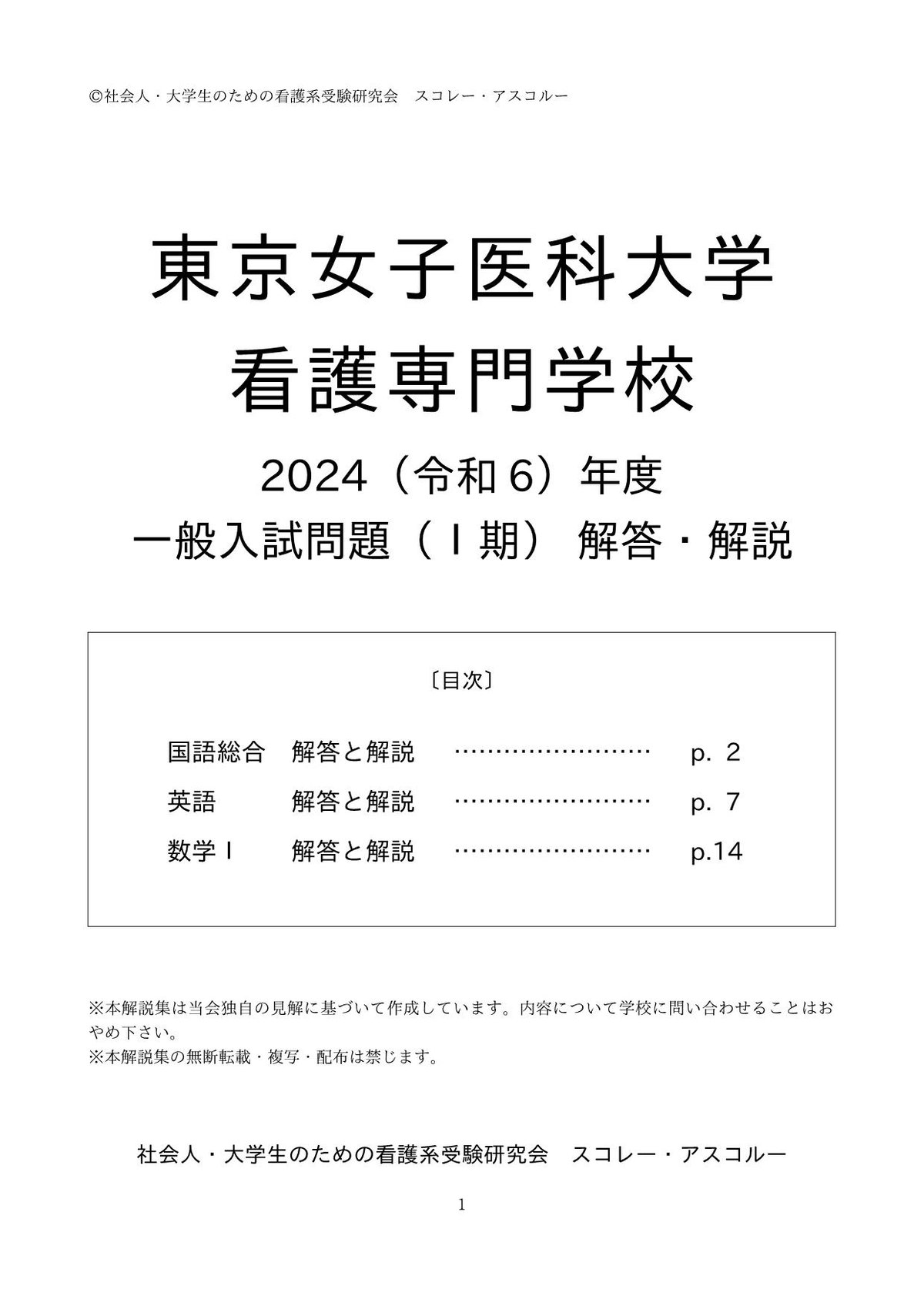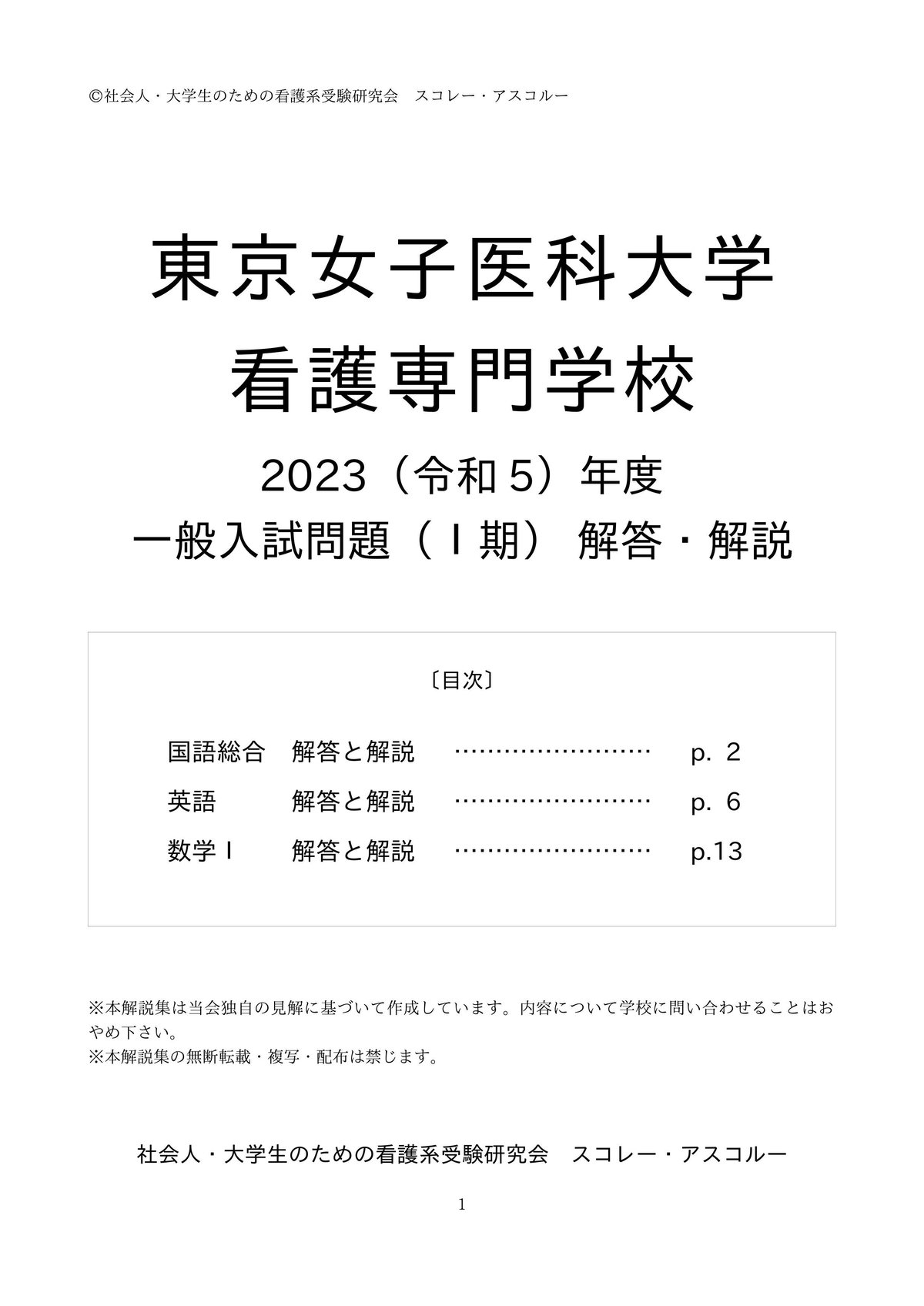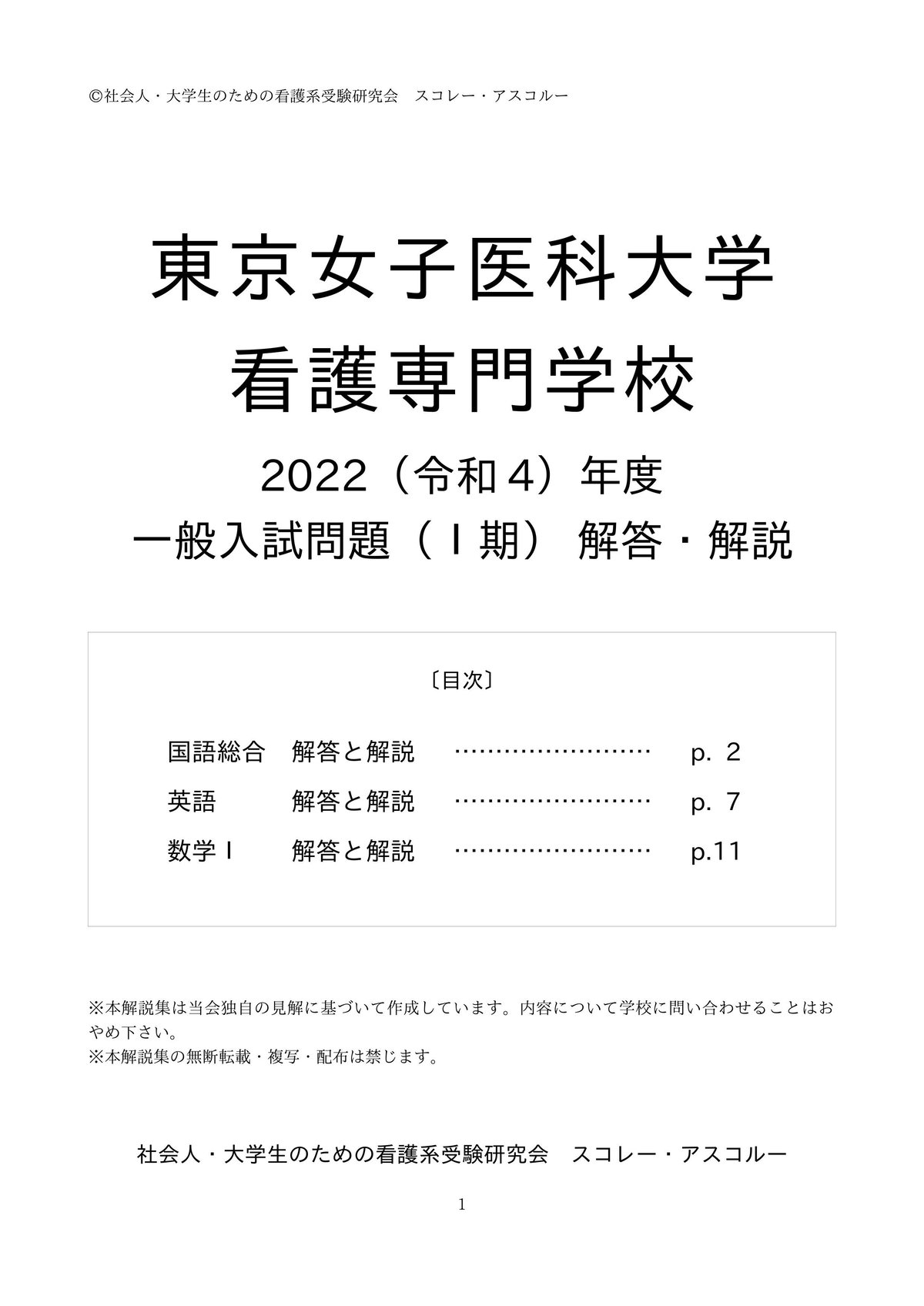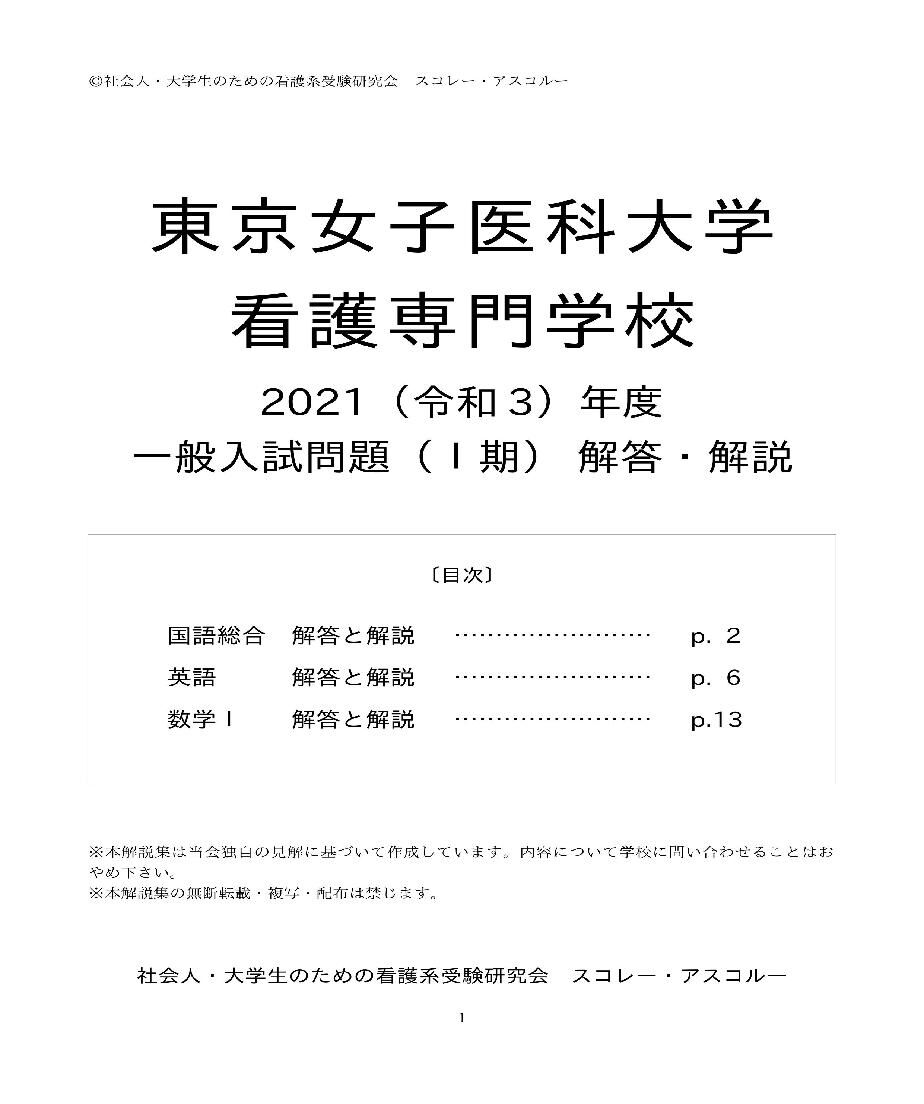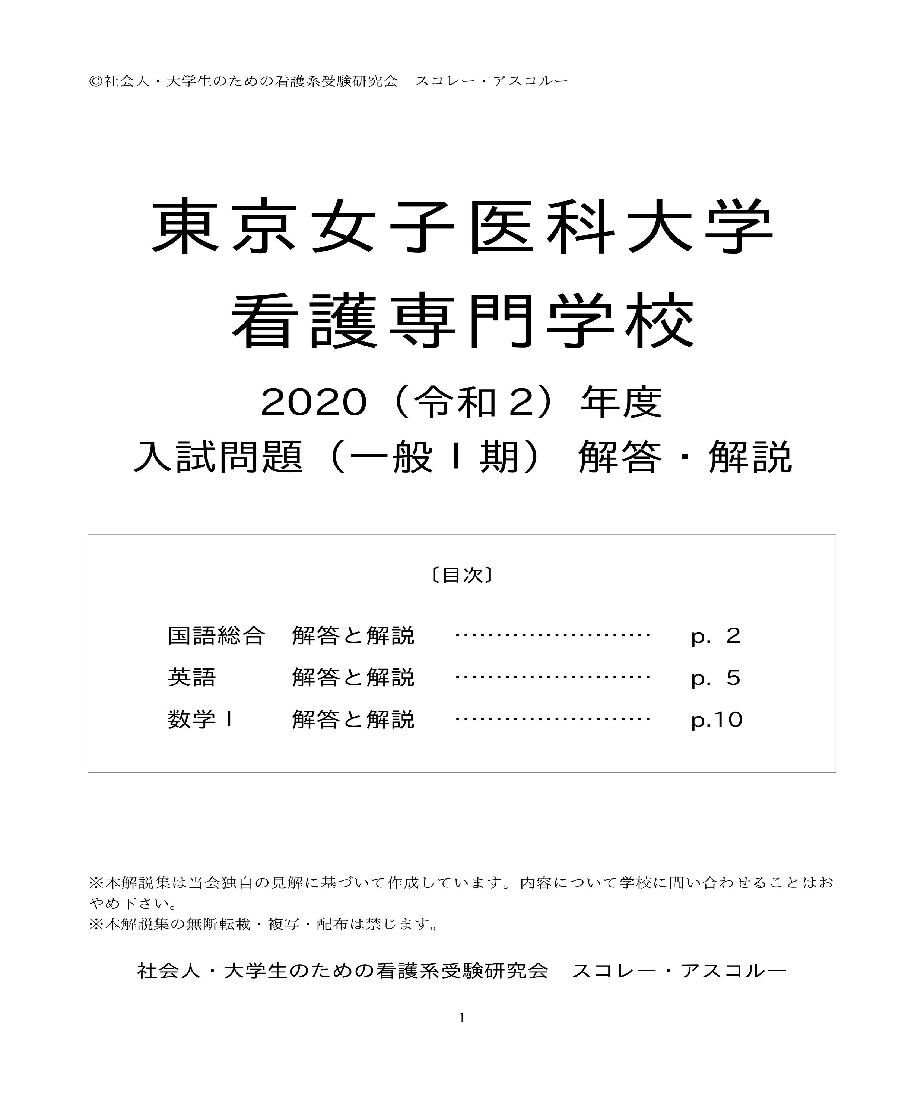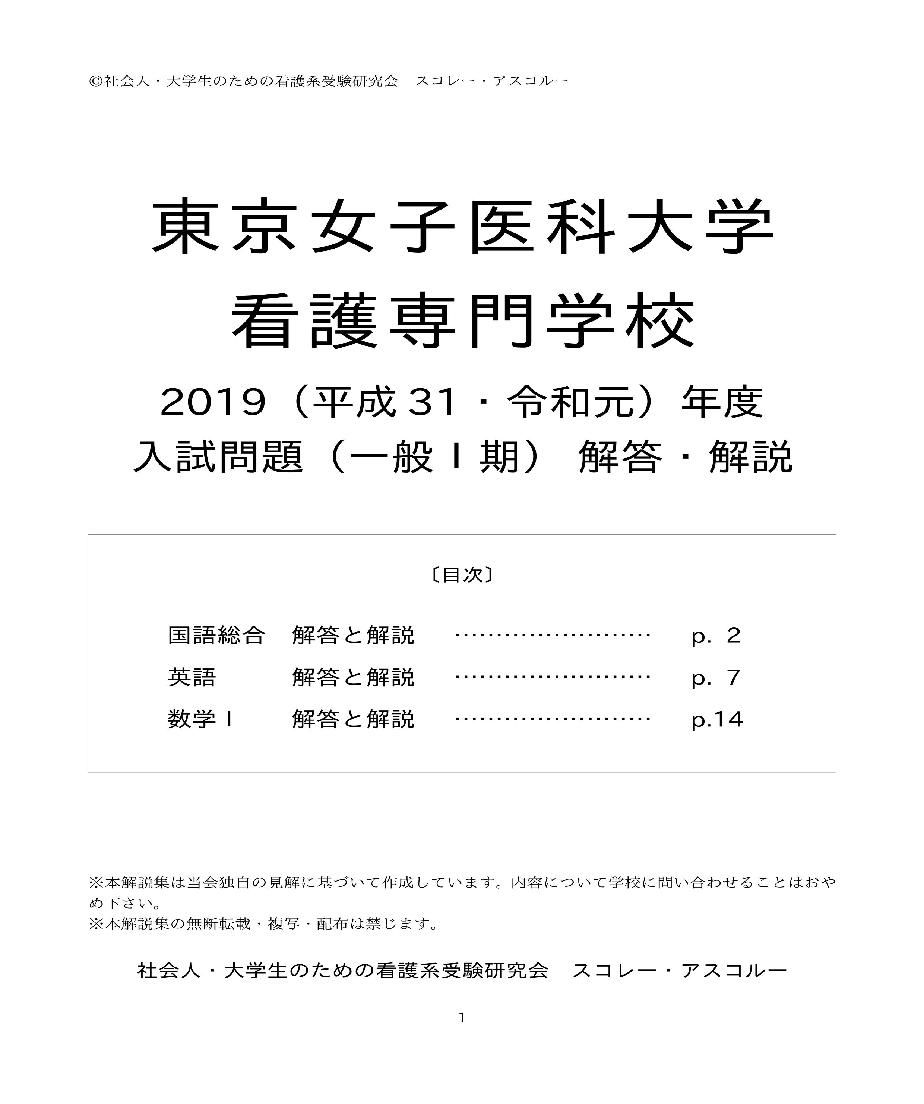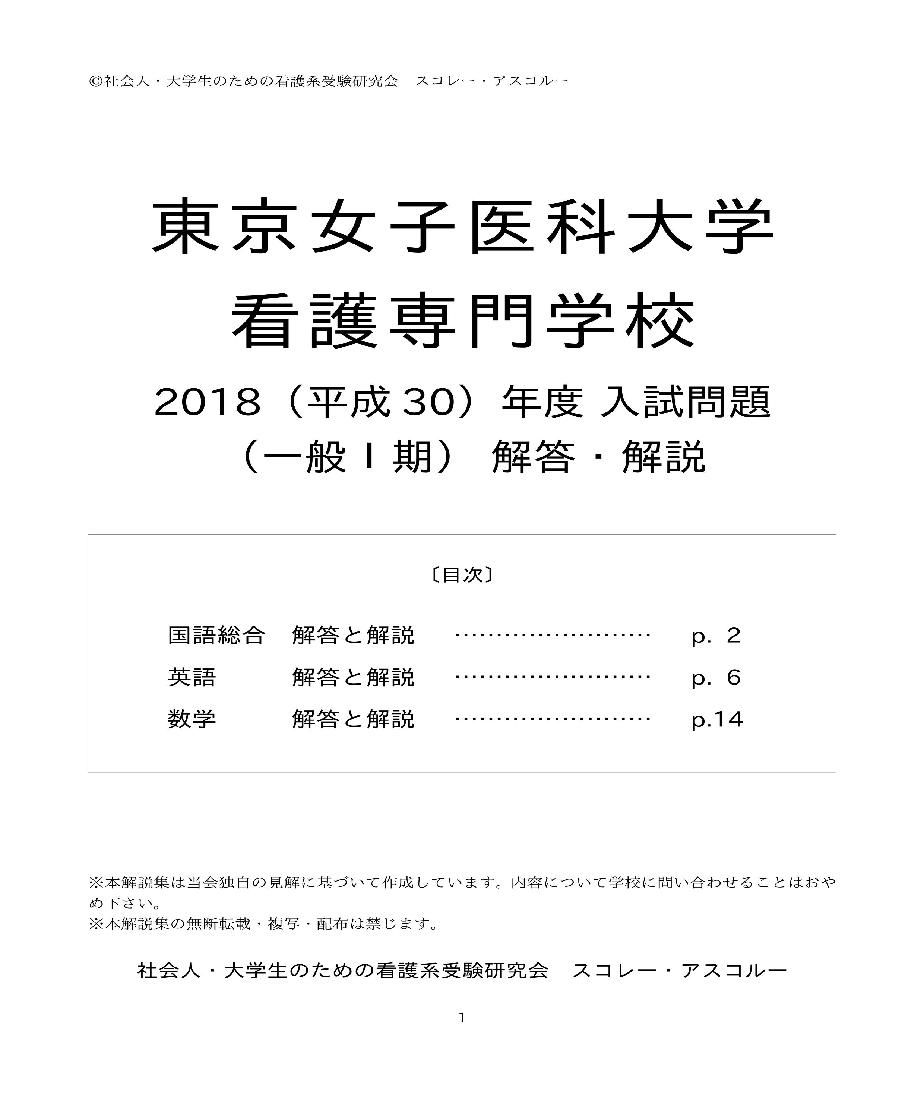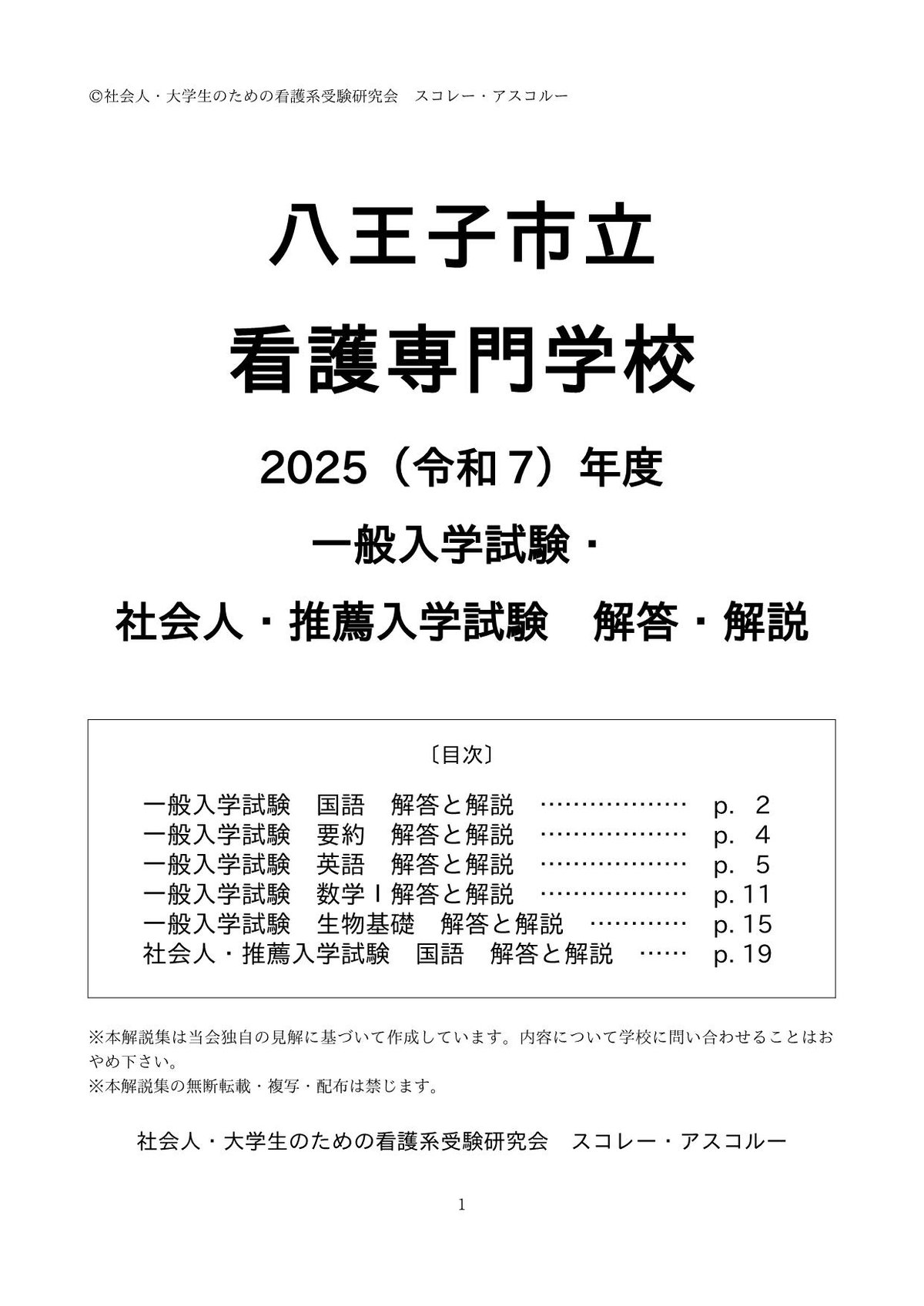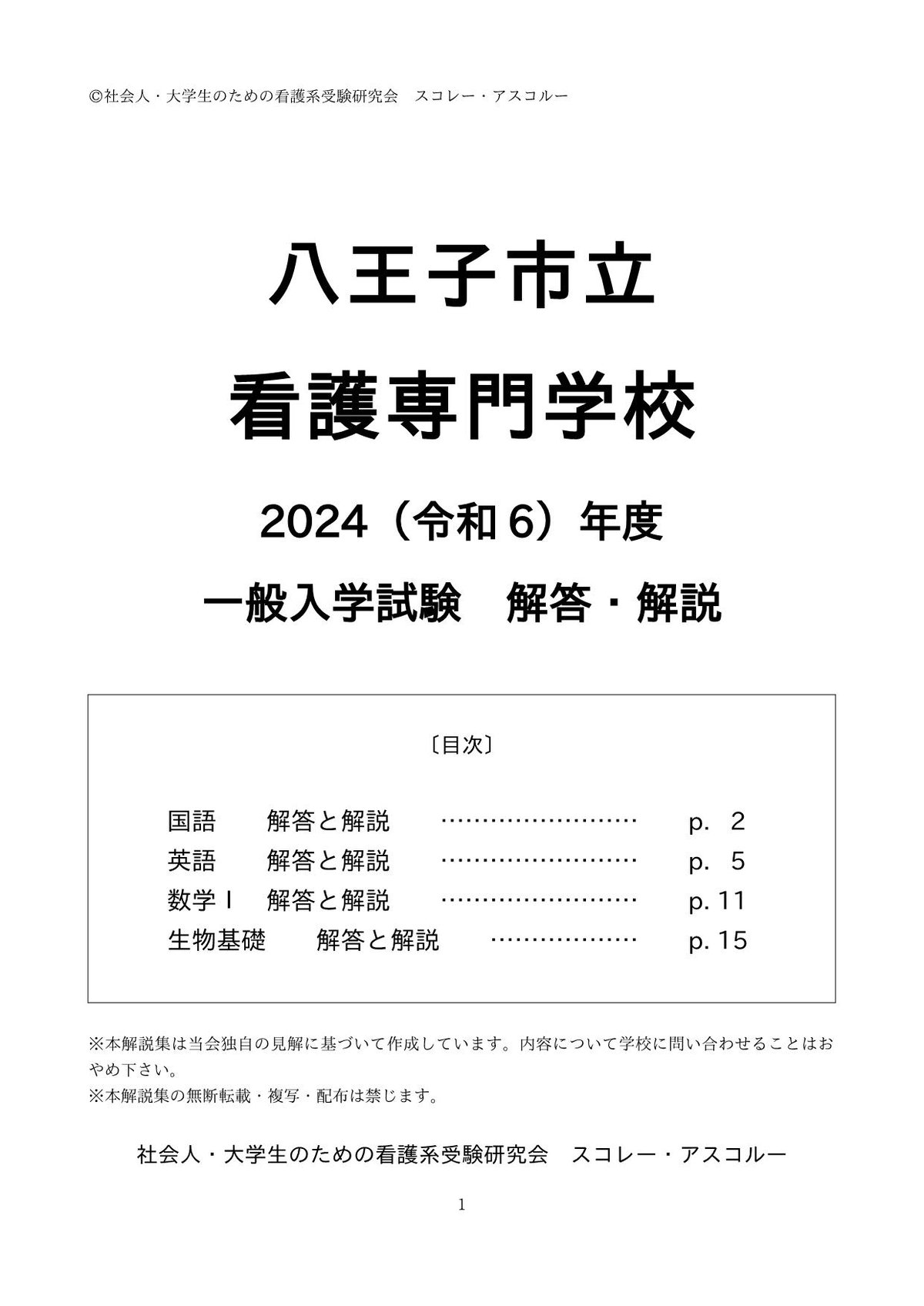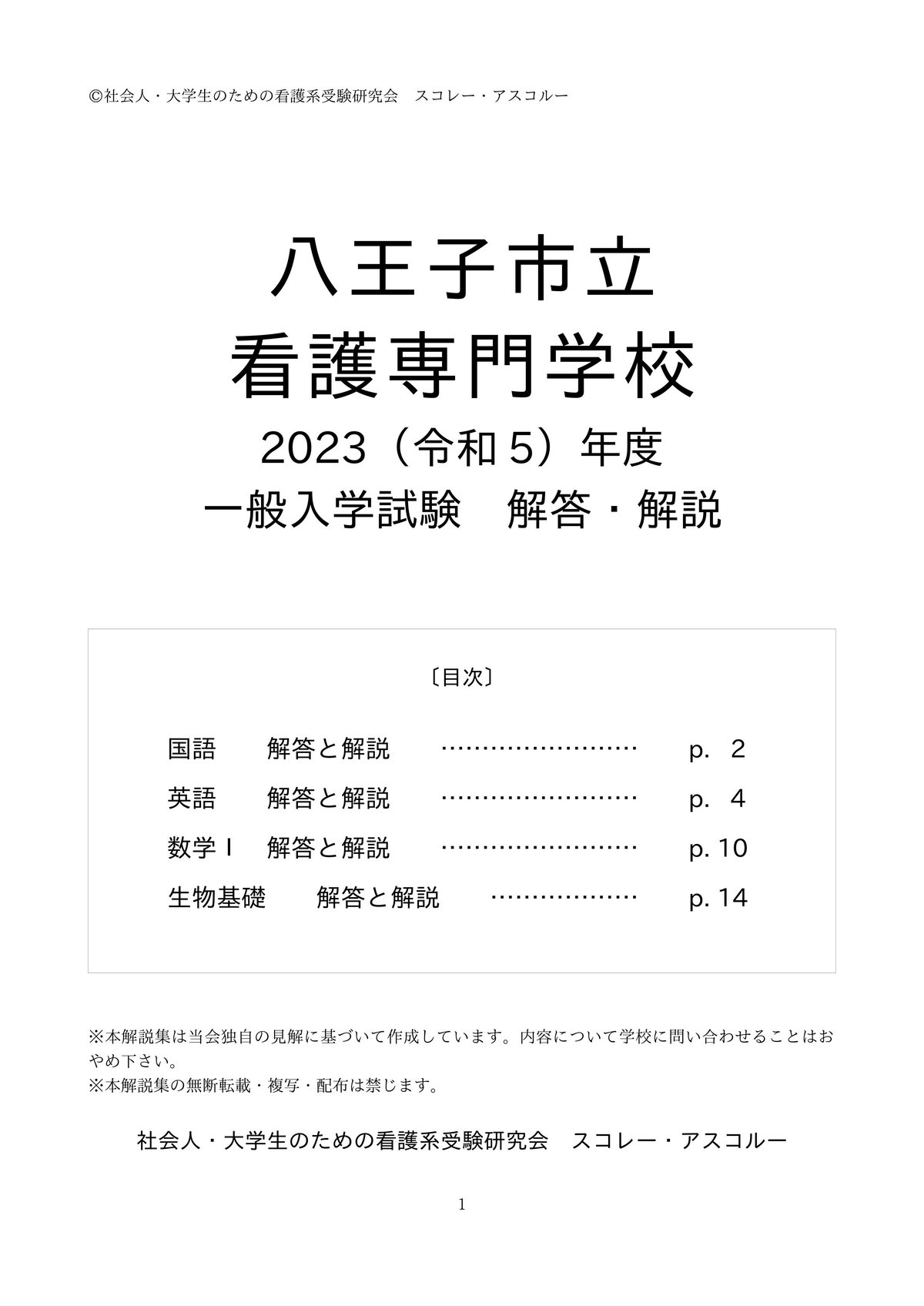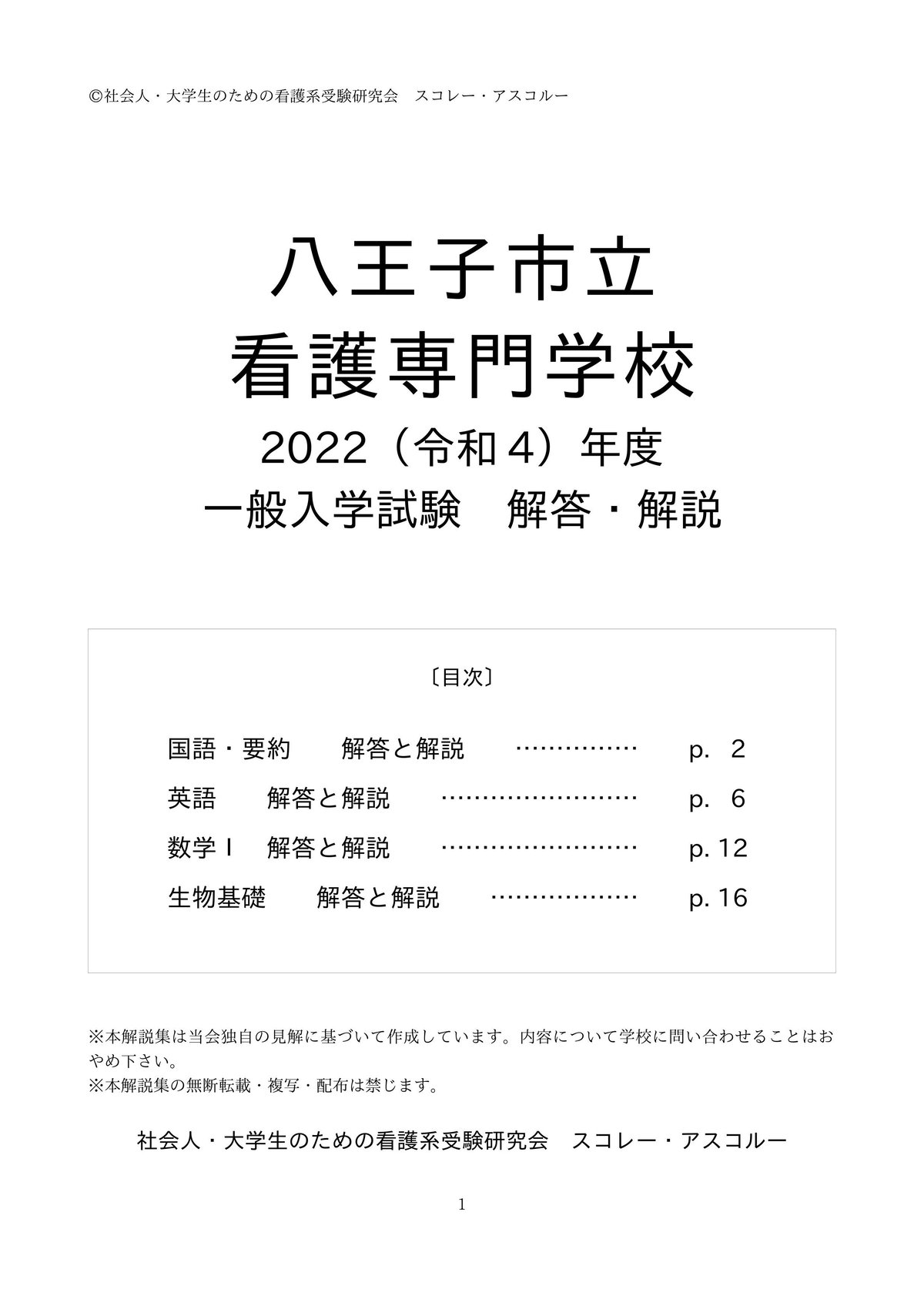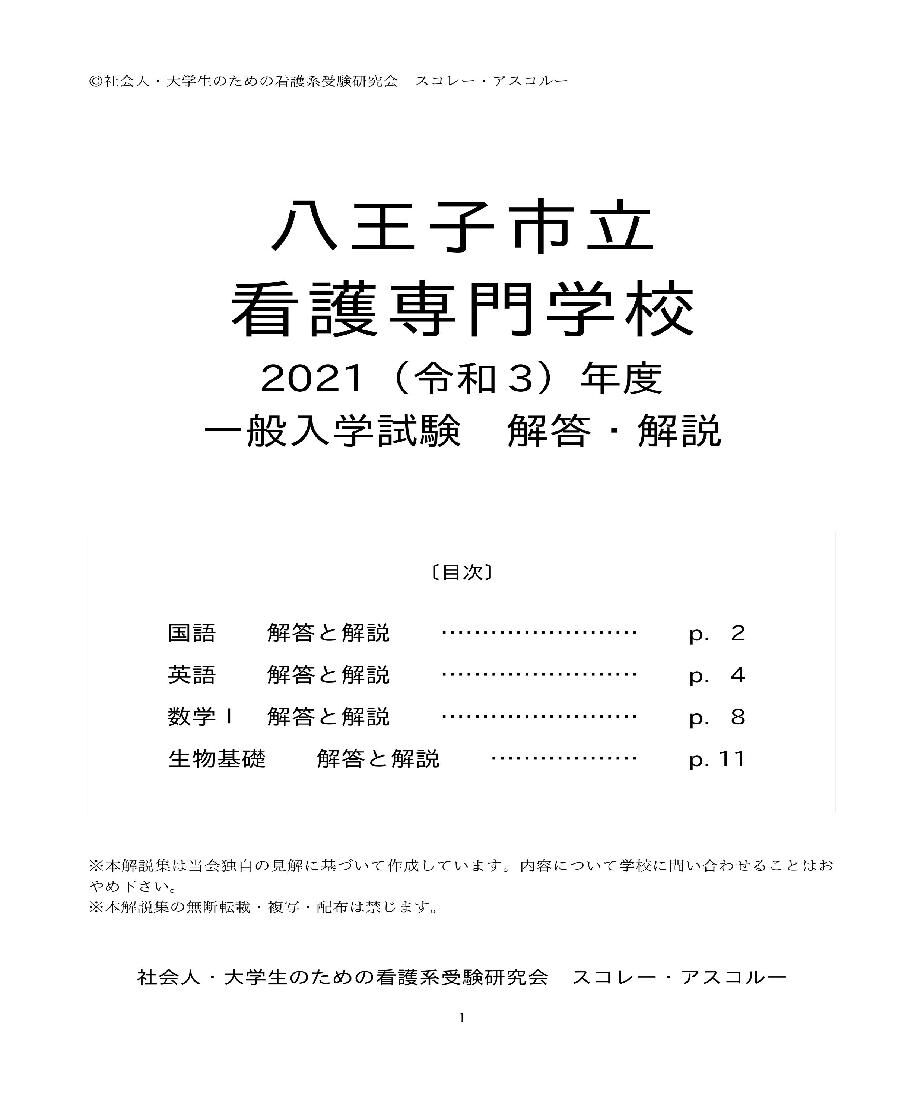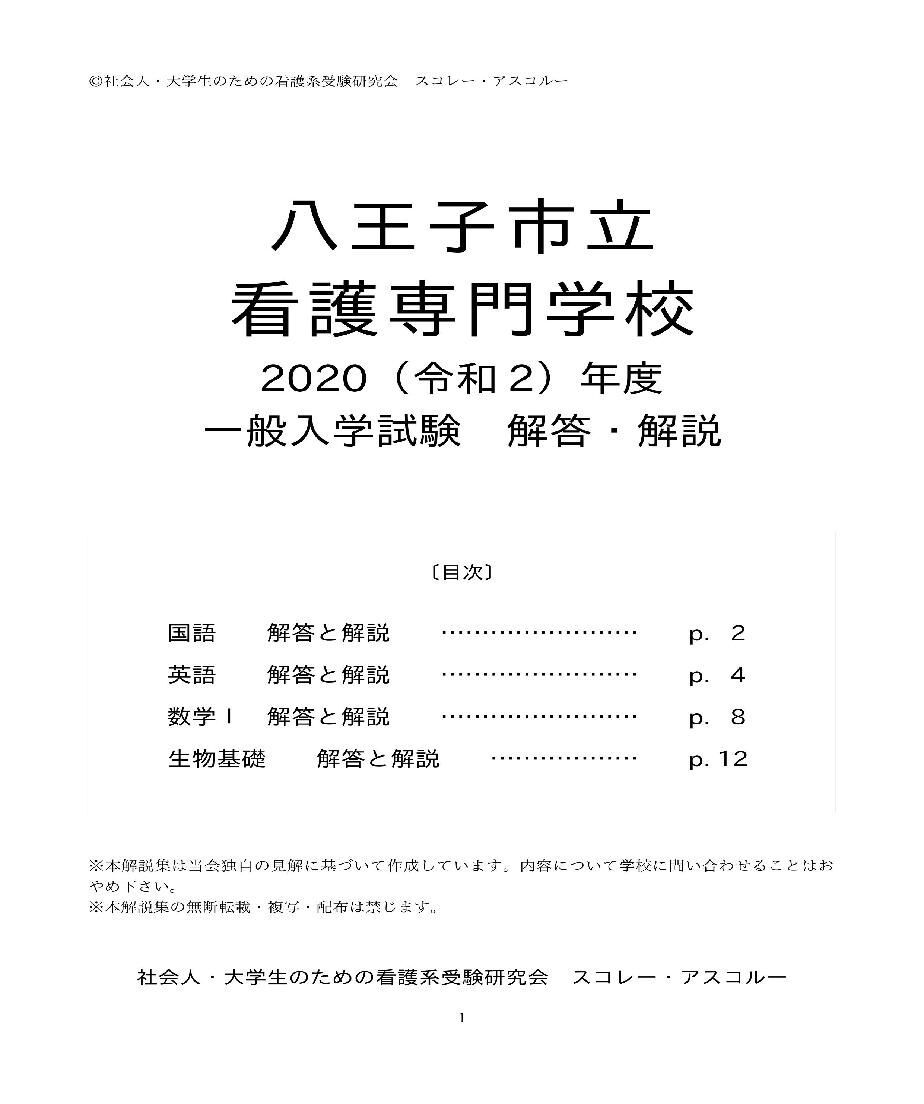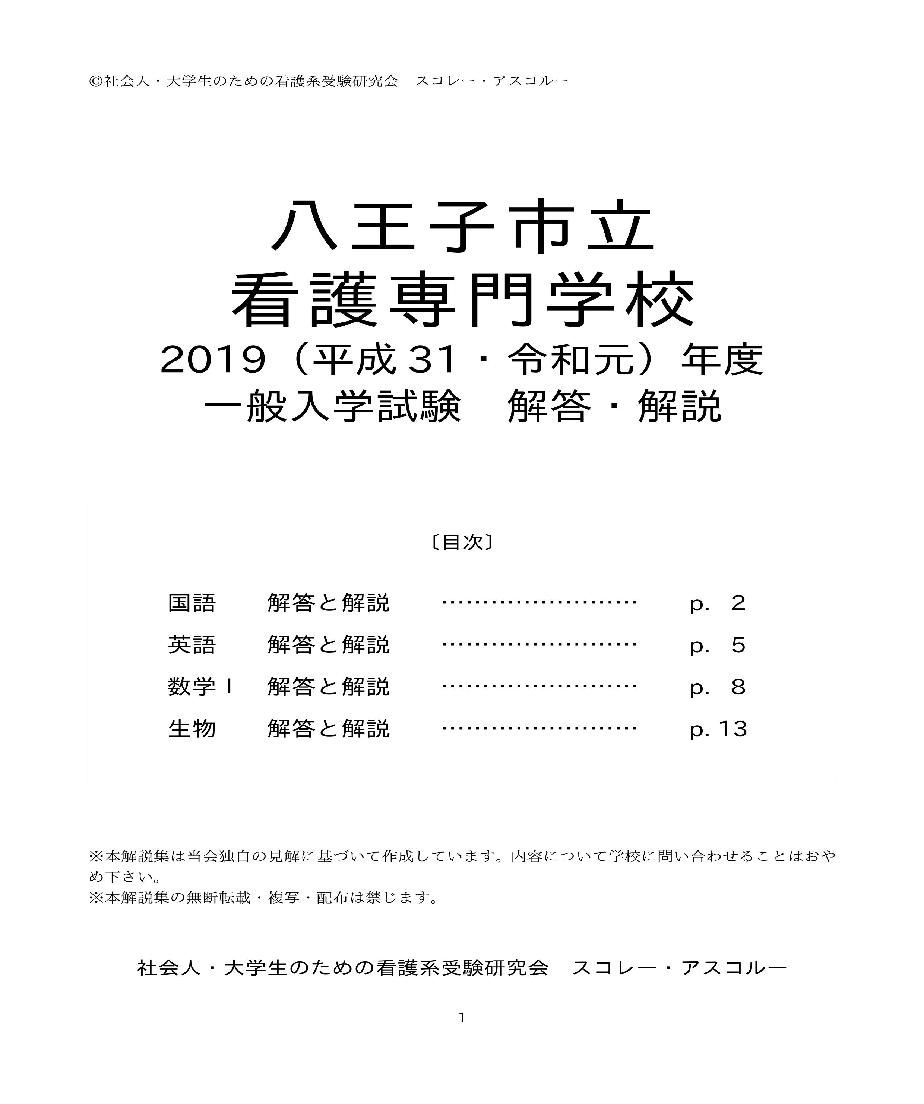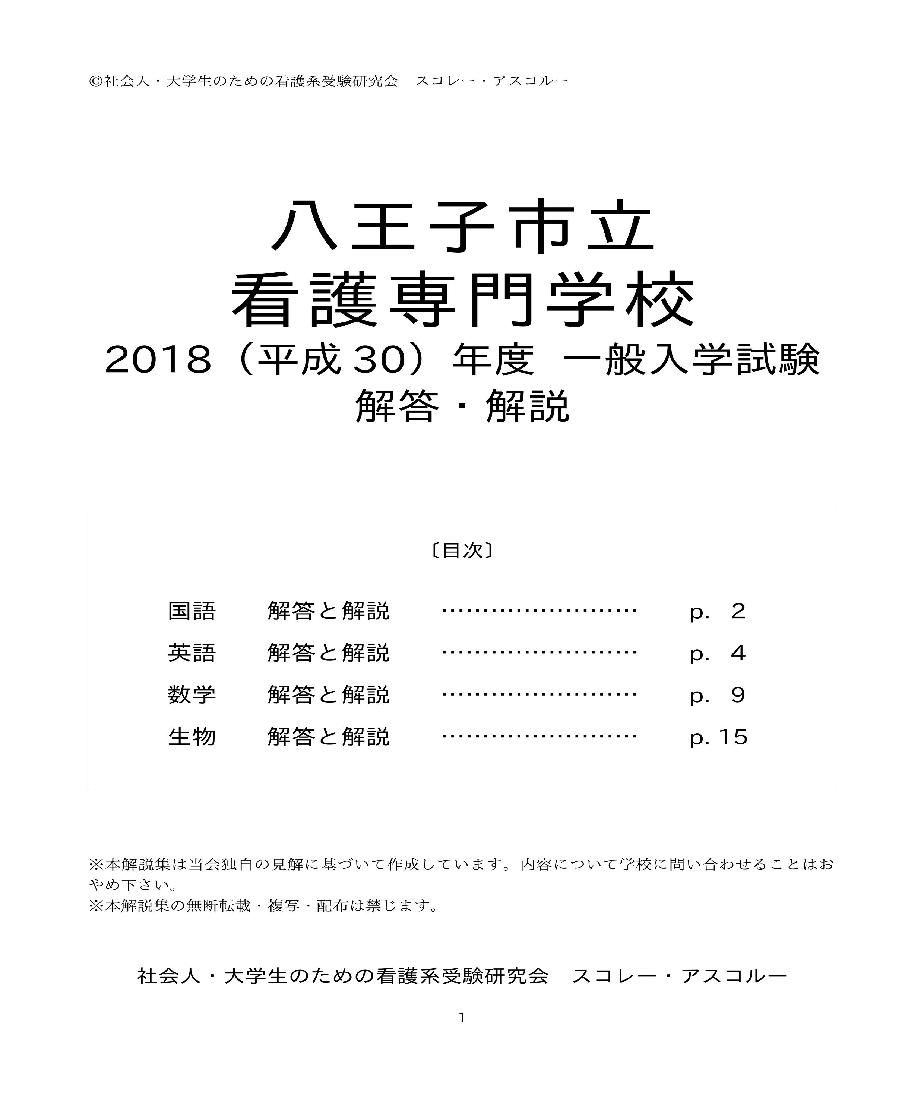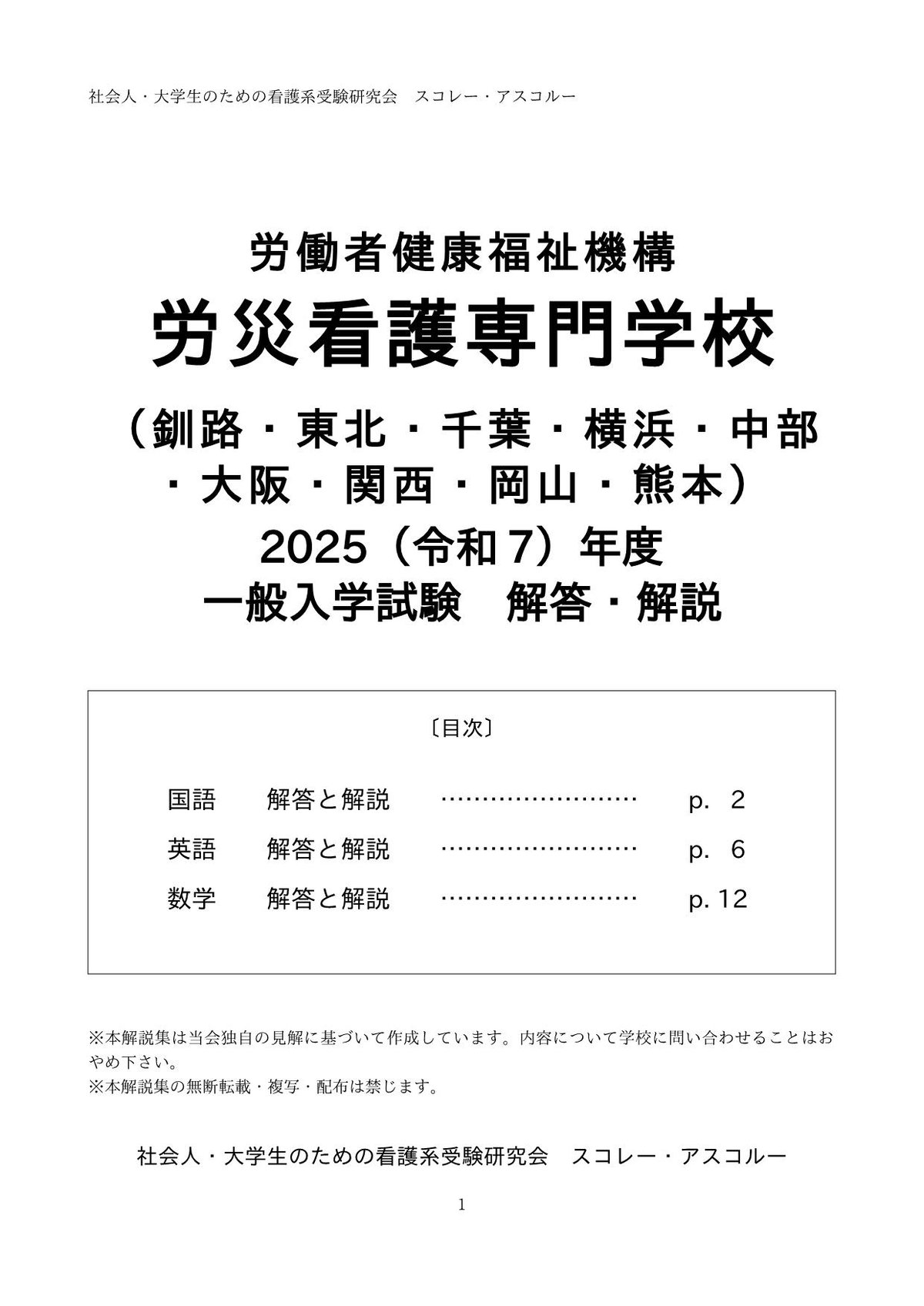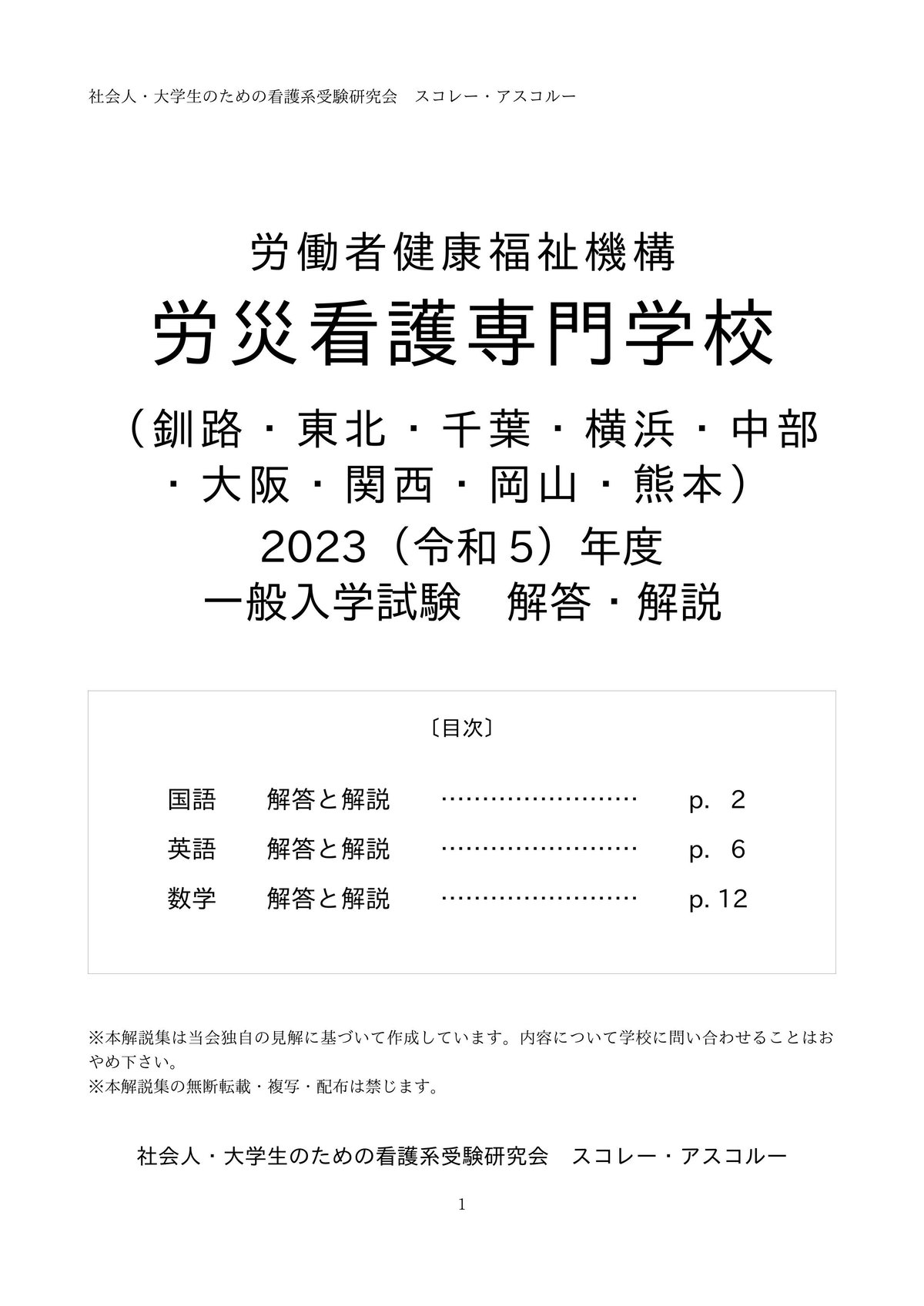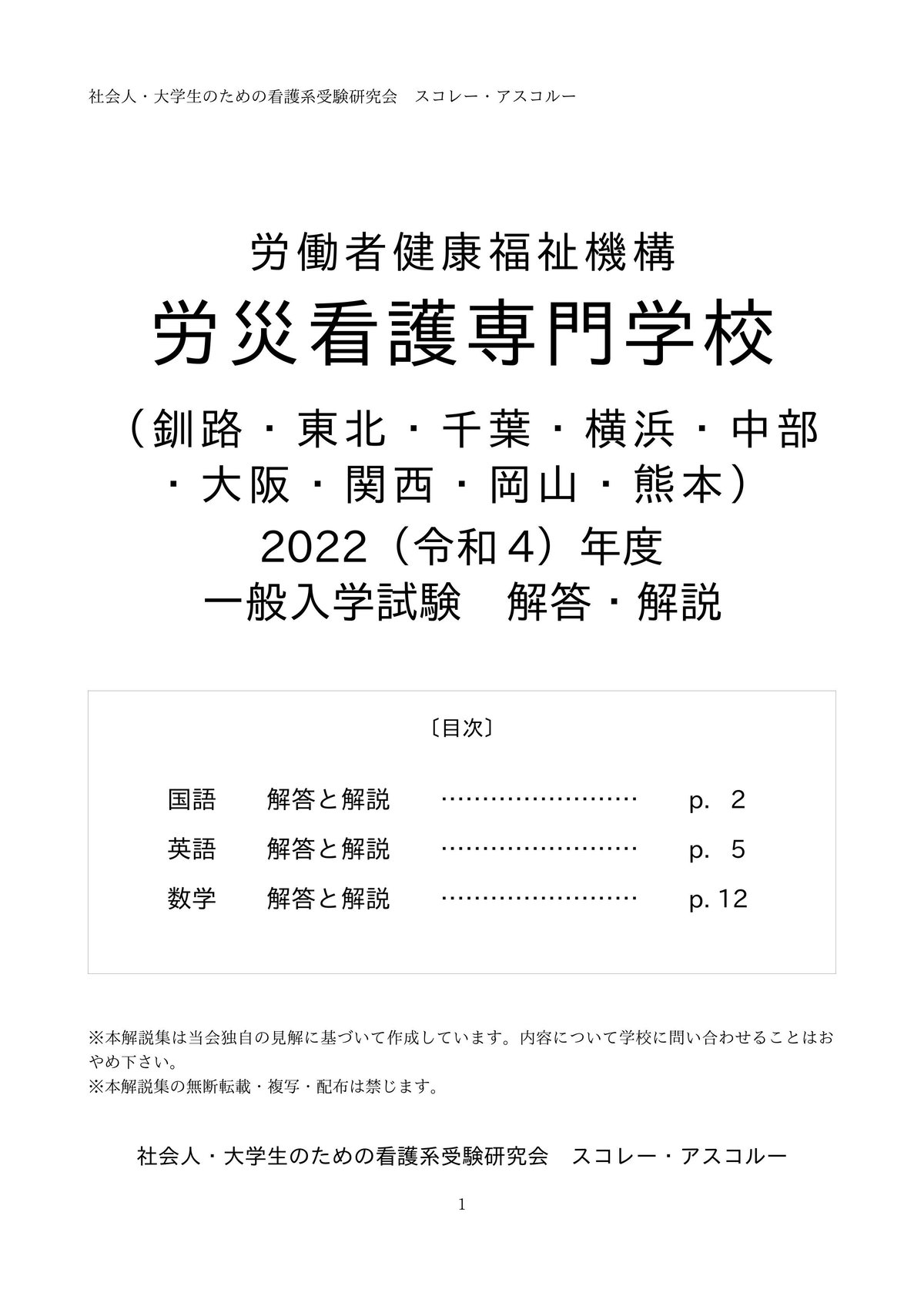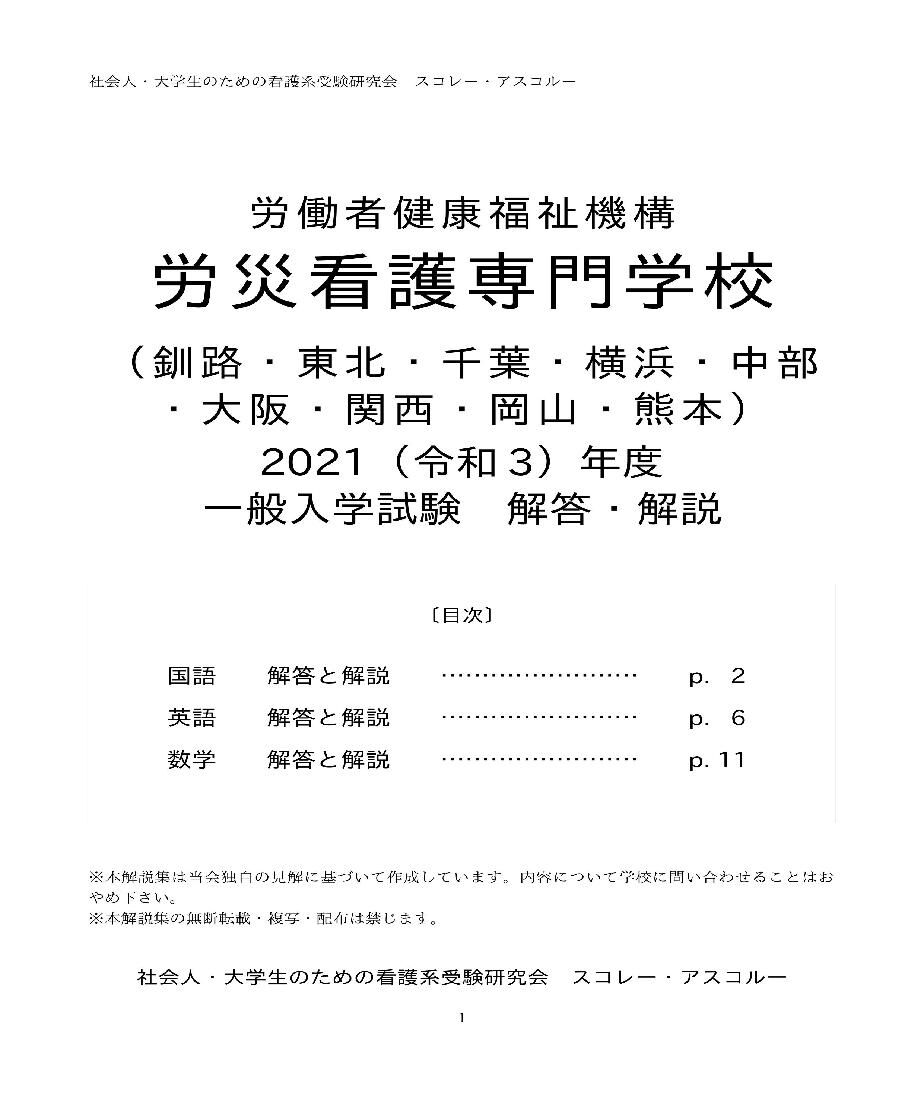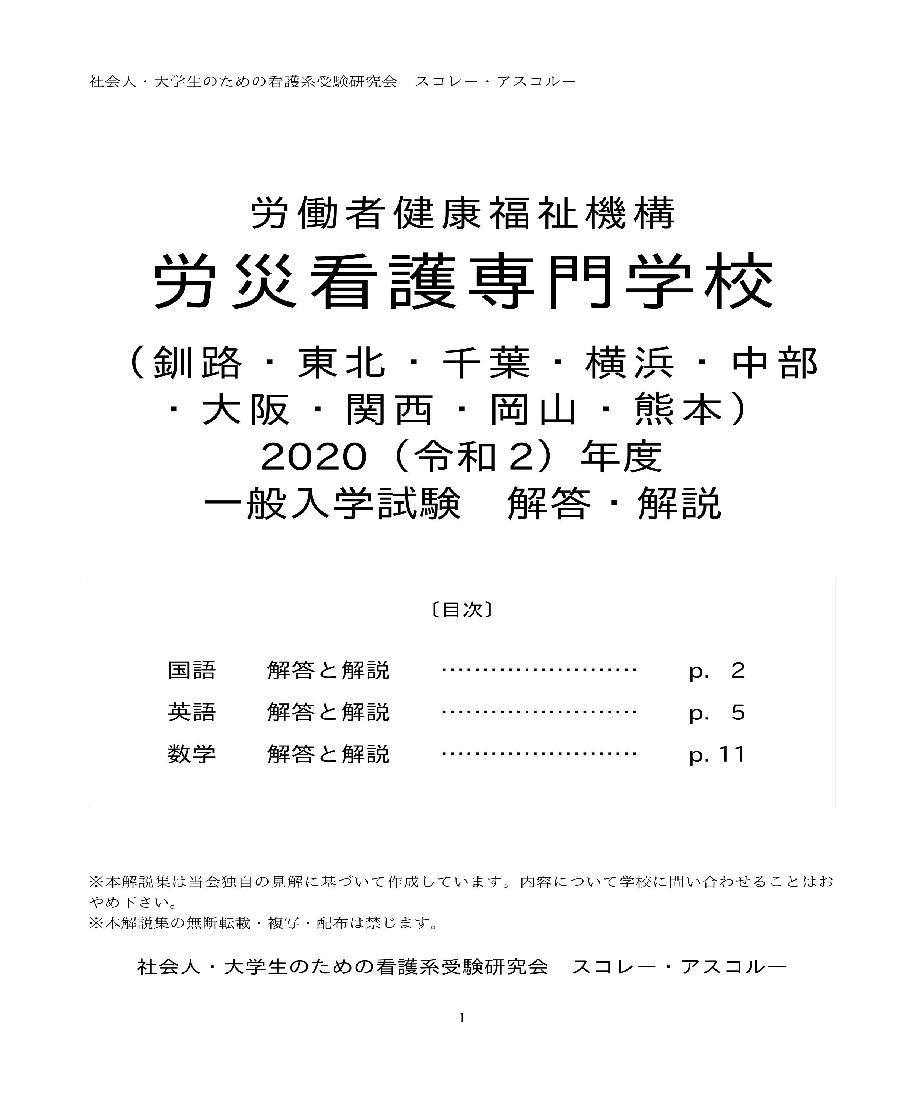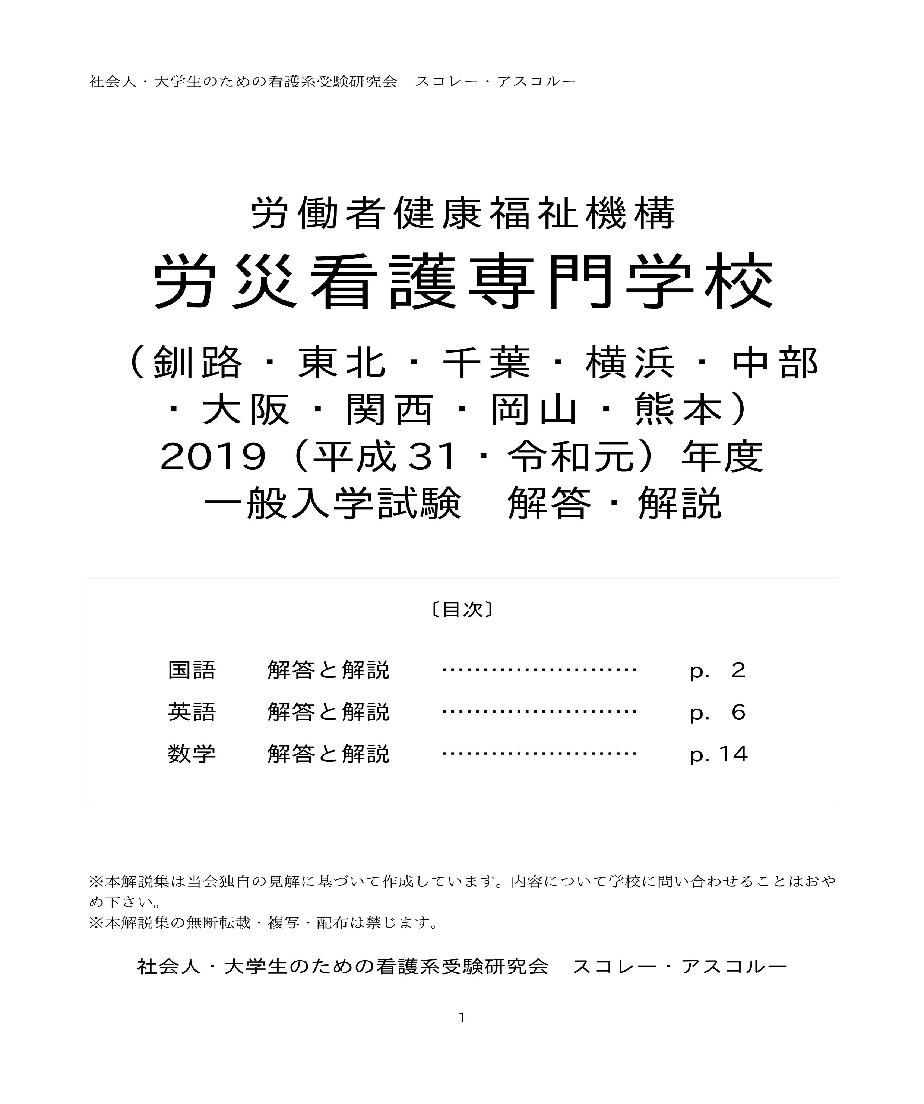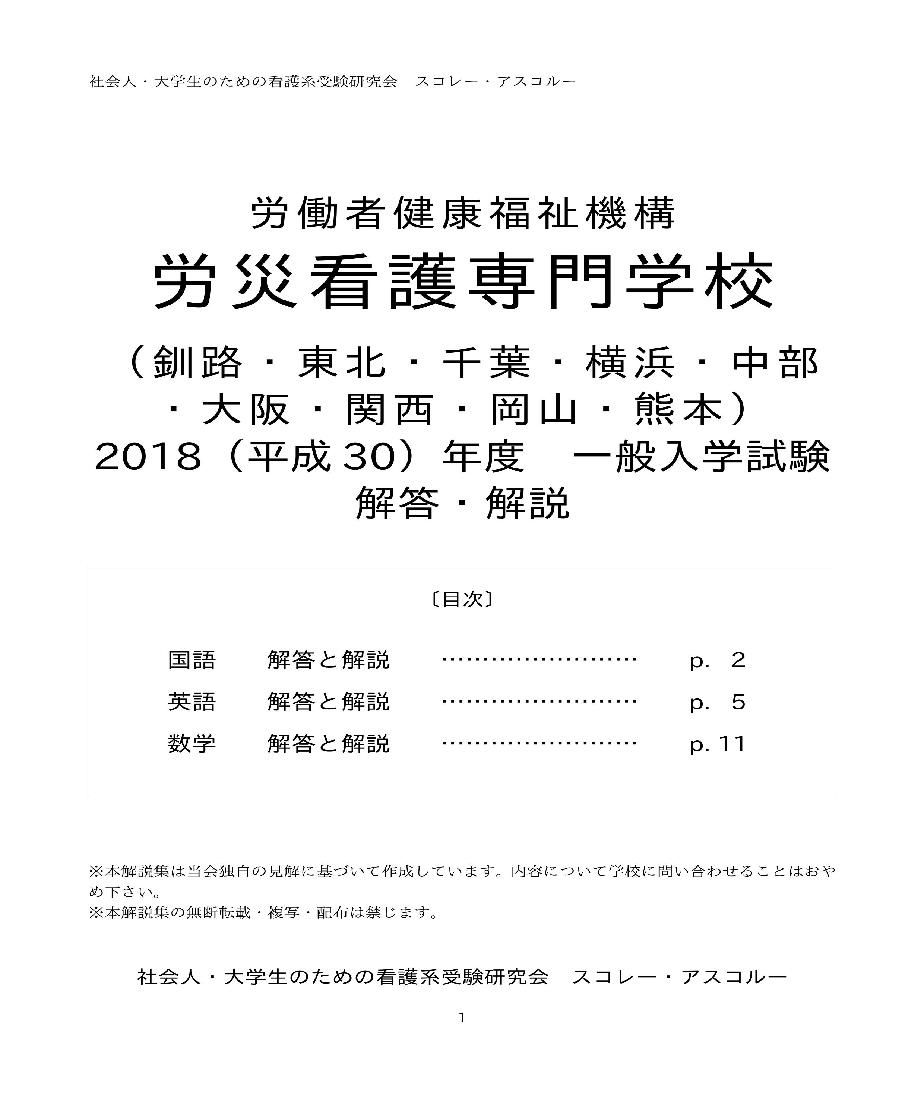スコレー・アスコルーでは、通信添削(赤ペン添削)による【小論文添削指導サービス】を実施しています。
【小論文添削指導サービス】は以下のような方にお勧めです。
・初めて小論文を書く方
・文章を書くことに苦手意識のある方
・受験校に合わせて、課題の内容や書く回数を変えたい方
・東京都立看護専門学校社会人入試対策、聖路加国際大学・慶応義塾大学編入学試験対策、国公立大学入試対策、など、受験校に合わせた専門的な小論文対策を行いたい方
(昨年度は、聖路加国際大学、慶応技術大学、東京都立看護専門学校各校などに合格しています。)
・模範答案のコピーでない、自分の考えや意見を掘り下げる方向で添削を受けたい方
・メール、LINE等でやり取りする通信添削サービスです。(郵送での対応も可)
・コースは「1題コース」「3題コース」「5題コース」から選べます
・課題は「過去問演習」「基本課題練習」「自由課題練習」から選べます
(※3題コースで1題を「過去問演習」、残り2題を「基本課題練習」のように、自由に組み合わせることができます)
・提出〆切は年度内 (※翌年3月末まで)
・添削済み答案の返却は、最短当日、通常2日以内
(※メール、LINEでの提出の場合)
・オプションで、答案の返却後、zoomやLINEなどのビデオ通話アプリを用いた直接個別指導が可能です。対話をしながら、どのように手直しをしていくとよいかを学ぶことができます。(別途料金が必要です。)
・相談や質問はいつでも可能です
◎【小論文添削指導サービス】のコースについて
課題① 過去問演習(字数は課題に従う)
受験校の過去問を、希望の回数、練習します。(答案と一緒に問題もご提出ください。)
課題② 基本課題練習
以下の基本練習課題から課題を選んで、練習します。
a 目指す看護師像(400字~800字)
b 医療を自分の仕事とすること(800字)
c 現代の医療において看護師に必要な資質(800字)
d コミュニケーションについて(800字)
e 人口問題① 少子化・人口減少(800字)
f 人口問題② 超高齢社会(800字)
g 介護(800字)
h 貧困・格差問題(800字)
i 女性の自立・女性の活躍(800字)
j チーム医療(800字)
k インフォームド・コンセント(800字)
l 将来の医療・AIなどのテクノロジーの医療への応用(800字)
m 災害と医療(800字)
n 環境問題・温暖化対策・環境汚染問題(800字)
o 健康(800字)
p 豊かさ・幸福(抽象的課題)(800字)
q その他・医療時事問題(800字)
課題③ 自由課題練習(字数は課題に従う)
サービス利用者の皆さんがテーマを自由に決める課題です。
テーマについては相談して決めることや、類似問題の作成・提案も可能です。
◎添削コースと料金
■1題コース……3,000円
課題①~③から1題選び、答案を1回提出するコースです。
■3題コース……8,500円
課題①~③から3題選び、答案を3回提出するコースです。
■5題コース……14,000円
課題①~③から5題選び、答案を5回提出するコースです。
※各コースで、選ぶ課題やその組み合わせは基本的に自由です。選び方でお悩みの場合は、お気軽にご相談・お問い合わせください。
オプション
■オプション個別指導(40分)……1,000円
※添削後、直接zoomやLINEビデオ通話など、ビデオ通話アプリを用いて、答案について直接、個別指導を行うオプションです。(希望者のみ。希望者は、お申し込み時に、実施希望日時を「ご注文(続き)」の欄にご記入ください。)
◎答案の提出と返却について
答案の準備ができましたら、当会まで答案をご提出ください。
添削ができましたら、お申込みいただいたお客様のメールアドレスやご住所等に、答案を返却いたします。
添削を提出してから返却までにかかる日数は、1~2日程度です。 ※メールでの提出の場合
◎お申し込み方法について
お申し込みは、下の「お申込フォーム」に必要な項目を入力の上、「送信」ボタンを押してお申し込みください。
「ご注文・お申し込み」の項目は
「小論文添削サービス 1題コース」
「同3題コース」
「同5題コース」
をチェックし、「ご注文(続き)」の項目に、課題番号や課題名をご記入ください。
オプションの個別指導をご希望の方は、個別指導の実施希望日時をご記入ください。
お申し込みいただいた方には、折り返し、
・お申込み番号(ID)
・添削料の合計や答案の送付先
・振込先口座
・(オプション個別指導をご希望の方のみ)個別指導実施日時
などを記した「返信メール」をお送りいたします。
「返信メール」に従って、添削料を振り込み、答案を提出して下さい。
提出時には、お申し込み番号(ID)もお書きください。
※お申し込み後のキャンセル・返金はできません。
社会人・大学生のための看護系受験研究会
スコレー・アスコルー