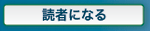「デカルトからベイトソンへー世界の再魔術化」(モリス・バーマン)の抜き書き書評記事を投稿します。


先の投稿の写真家の北桂樹さんの積読本リストにあったのがきっかけで手に取ったのですが、コロナウィルス騒ぎで本を読む時間が出来たので、ひさびさに骨のある本を読んでみようということになりました。
近代の物質主義や科学主義ということを近代主義(デカルト)の世界観として否定することに前半延々と紙面が割かれています。
それらを生み出したニュートンを実は錬金術に傾倒していた最後の魔術師だというように表現して、錬金術やニュートンを批判したウィリアムブレイクなど、近代主義の批判を繰り返すのが前半部分。
後半では、作者が世界のこれからのあるべき意識論として、支持するベイトソンの哲学について、生物学者だったベイトソンの父親の研究のことから語り始めていくという構成です。
この主な論旨である後段にたどり着けるまでが長いことが、この本の読破を困難にさせているような気がするのですが、良い映画は前置きが結構長かったりもします。
私は作者の術中にはまり、ようやく本編来ましたかというところに入っては、待ってましたという感じで、読みふけることが出来ました。
どうしても結論だけ知りたいということであれば、後半最終章の「明日の形而上学」をいきなり読んでしまうということも可能です。
本書評でも、以下、最終章の「明日の形而上学」の記述について詳述します。
はじめは、グレゴリーベイトソンの父親の遺伝生物学者だったウィリアムベイトソンの研究についての説明から始まります。
ここでは、例外から全体を探るという方法論だとか、生命に限らずモノも含めて循環性の法則があるのではというような漠とした神秘主義を吸収したというような表現で書かれています。
そして、ナヴェンというニューギニアのある民族で行われているという、事あるごとに性を逆転させた役割を演じる儀式が行われる祭りに対しての研究について話は進みます。
そのお祭りをグレゴリーベイトソンは、男性性女性性が極端に色分けされた日常生活を補うための相補的な儀式だと分析します。
同じ相補的な現象として考えるという思考様式で、ダブルバインドという精神病を起こさせる条件の分析と、それを乗り越える際に、学習の認知の次元を一つあげるための取り組みがあると解説を続けます。
それが更に教えてもらった芸をしてもエサがもらえなくなったイルカが思考と行動の次元を一つあげて、オリジナルの技を出来るようになったことをメタ認知獲得の学習の次元をを一つあげた事例として説明されています。
ここまでで言うと、最近ではよく言われる、認知バイアスを取ろうとか、メンタルモデルを認識してその枠の外にある視点を獲得しようというような話になり、そう言ったような様式を学習Ⅲと呼んでいます。
そして近代論と比較してベイトソンの全体論を並べて比較した上で、一気に未来の社会のあり方論が展開されていきます。
この最終章の未来予測論の記述が非常に面白かったので、以下抜き書きです。
◾️サイバネティクス的説明の核心
関係こそ現実の本質である
◾️伝統的文化は
トーテミズムや自然崇拝などの慣習を通して、循環性とサイバネティクスの概念を直観的に把握していた
それによって環境を維持することができた
◾️どんな連鎖反応が生じるか
関係の網に心を集中することができる
全面的に一体化(ミメーシス)に回帰せずとも、全体論に基づく正気の行動が可能になるだろう
◾️〈精神〉をめぐる知が
美的認識という形でよみがえり、技巧的(アートフル)な芸術的(アーティスティック)科学(世界についての知)を我々は手にすることができる
◾️補強しあう
一体化(ミメーシス)と分析の両方を手に入れ、それらが「ふたつの文化」の分裂を生むのではなく
たがいに補強しあうようにならないだろうか
◾️真の洞察
人間は関係(環境だけでなく、人間がかかわりあうすでてのものと)一体的(ミメティック)な関係をもってはじめて、現実に対する真の洞察が得られる
そうやって得た洞察が分析的理解の中心となる
こうして事実と価値が合体する
◾️学習Ⅲとは
「壮大な生態系」への心が一気に飛躍すること
◾️回心
キリスト教神秘主義、禅の悟り、錬金術の変容の最終段階などと類似している
◾️学習Ⅲもそれらの回心も
人格が根本的に変容するということが、最も重要なポイント
◾️視座
どちらの場合も、人は新しいレベルへと飛躍し、自分の性格と世界観を外から眺める視座を得る
◾️ベイトソンのいう学習Ⅲとは
単に個人レベルの忘我的ヴィジョンを得ることだけではない
人と人がつながった共同体的生き方を追求する上での必要不可欠の部分
◾️〈精神〉はつねに
「部分同士が内部で結び合わさった、社会システム全体、この惑星のエコロジー全体に内在している」
◾️未来の「地球大の文化」を思い描くとすれば
夢、ボディランゲージ、美術、ダンス、空想、神話などから成る内的〈精神〉風土が、世界を理解し世界のなかで生きようとする試みにおいて、大きな役割を果たすことになる
ESP(超感覚的知覚)、神秘力(サイコメトリー)、念力(サイコキネシス)、霊気(オーラ)の読解とそれによる治癒といった、さまざまな心霊能力を高める試みもなされるだろう
生態学と心理学がほぼ一体になるだろう。病というものはその大半が肉体的・情感的環境が乱されたことへの反応であることが、広く認識されるようになるはずだからだ
身体は抑圧されるべき危険なリビドーとしてではなく、文化の一部分として捉えられるようになり、そうした認識の結果の一部として、性の抑圧は大幅に減少し、人間もまた動物であるという自覚が深まるだろう
拡大家族が見直され、今日において精神病の発生源となっている、たがいに競争しあう孤立した核家族は減少するだろう
「非生産的」な人間を収容するための老人ホームに年寄りを捨てることもなくなり、子供たちとともに暮らす老人の叡智が文化的生活の欠かせない一部分となることだろう
◾️人格の理念も大きく変わる
自我(エゴ)から〈自己(セルフ)〉へ重点が移行
ひとりの人間の自己と他人の自己とがたがいに反応しあうことが奨励されるだろう
競争ではなく協働、個人主義ではなく個体化
「にせの自己のシステム」や役割演技などは消滅するだろう
◾️力という概念
他人の意志に反して他人に自分の望むことをやらせる能力というふうには捉えられなくなって
力とはすなわち中心の安定(centeredness)であり内的な権威である
他人に圧力や強制を加えることなしに他人に影響を与える能力、それこそが「力」
さらに、未来の文化は、人格の内においても外においても、異形のもの、非人間的なものをはじめ、あらゆる種類の多様性をより広く受け入れるようになるだろう
そのように包容力が高まる結果、「正気」の捉え方も、フロイト=プラトン的発想から錬金術的発想になるだろう
すなわち、理想的な人間とは、万華鏡のごとく、「多面的」な人間であるということになる
人生の関心事、仕事や生活のスタイル、性的・社会的役割などにおいて、柔軟なしなやかさを持つ人間こそが理想とされる
いかなる行動にも、「影」と呼ぶべき相補的な対応物がかならずひとつはあり、それがしかるべき表現を与えられるのを待ち受けているのである、と考えられるようになるどろう
非分裂生成的な思考・関係のさまざまな方法をめぐって、実験的試みがなされることなもなろう--累積的にひだいするのではないパターン、満足を将来に引き延ばすのではなくそのままで満足をもたらしてくれるようなパターンを創り出そうとするのだ
◾️人間の文化
自然のなかに人間が調和することこそが大事だと誰もが考えるだろう
そうした社会がめざすのは
「ある領域を支配するのではなく、解放すること」
テクノロジーが我々の意識の隅々にまで浸透することはもはやなくなるだろう
テクノロジーが人間をコントロールするいう転倒した関係は消滅するのだ
医学、農業、その他いかなる分野であれ、人間はもはやテクノロジーの「薬」に頼ったりせず、長期的な見通しに立った解決策--症状ではなく病因にじかに取り組むような解決策--を選択することだろう
◾️政治について
大規模な脱中央集権化があらゆるレベルでの公共機関にわたって行われ、それこそが地球大の文化の絶対条件だという認識が生まれるだろう
地域に根ざした自律的な政治構造になるということ
こうして生まれる社会では、市民病院、食品生協などがかならずあり、地域の有効意識と自律が育まれ、テレビ、自動車、高速道路など、共同体を破壊するものは抹殺されるだろう
マスプロ教育に変わって、弟子が師に教わる徒弟制が生涯教育の形で行われ、それぞれの人間の関心の変化に適応できるようになるだろう
そのような社会では、人は職業(キャリア)ではなく、人生(ライフ)を持つのだ
都市はふたたび生と喜びの中心となるだろう
人は自分の仕事に密接して生き、仕事、人生、娯楽という区別がほとんど意味をなさなくなるだろう
◾️経済は
定常状態の経済がめざされ、小規模の社会主義、小規模の資本主義、直接の物々交換とが混じりあった経済になるだろう
資源の浪費は極力避けられ、可能な限り地域の自己充足がめざされるだろう
利益をそれ自体目的として考えることはほとんどなくなるだろう
他人や天然資源に対しても、搾取や儲けではなく、調和を念頭に置いて接するようになるだろう
経済学は生態学の一分野としての「生態経済学」となるだろう
◾️このヴィジョンに向かう変化を引き起こしつつあるもっとも強力な要素は
先進工業社会の衰退そのものである
工業経済は縮小し続けている
好むと好まざるとにかかわらず、定常経済への回帰は避けられない
◾️このような変化を引き起こす上で大きな要因になっているのが
社会に背を向けている何百万もの人々である
◾️労働者たちは
ブルーカラーもホワイトカラーも自分の仕事に何ら本来的な価値を見出せなくなっており、いまや仕事以外の場所に人生の意味を求め、仕事に対する忠誠心を失いつつある
現代の我々の生き方の精神的支柱であるプロテスタント的労働倫理は、経済がその倫理をもっとも痛切に必要とするときにはおそらく姿を消してしまっているだろう
◾️全体論的社会
右翼/左翼といった従来の政治的二分法を超えたさまざまな立場から、全体論的社会が我々に近づいてきている
フェミニズム、エコロジー、民族主義、超越主義(宗教的復興)
それらはみな、同じひとつの目標に向かって収束しつつあるのかもしれない
こうした運動は、工業文明によって抑圧されたけど「影」たちを代表していると考えるべきだろう
◾️周縁的な存在
「対抗文化(カウンターカルチャー)」のさまざまな要素を結び合わせる共通の絆はあるのだろうか?
おそらくそれは「回復」という概念である
◾️「回復」(recovery)という概念
本来我々のものであるはずの、身体、健康、性、自然環境、原初的伝統、無意識の〈精神〉、土地への帰属、共同体、人間同士の結びつきの感覚、そうしたものを回復することである
◾️『易経』の言葉
めざすべきは、人類全体が満足できる政治的あるいは社会的組織である。我々は、人生のもっとも根本的なところへ降りて行かねばならない。生のもっとも深い必要が満たされないような、表面的な生の秩序化などまったく無益であり、何ら秩序をめざさないのと同じことである
これこそが、あらゆる全体論的政治学の目標となっている
それは、今日我々が知る意味での「政治」の終焉をもたらす政治学なのだ
抜き書き以上です。
学習Ⅲという発想とベイトソンの全体論という世界観からここまで未来予想図が描けるというのが、これが30年前という平成始まってすぐ位のバブル崩壊前に書かれていたということに正直びっくりという感じです。
筆者はここの一群の文章で、ベイトソンの思想から導き出せる未来について、言いたいことを言いまくった後に、改めてベイトソンの考え方について、終焉に向かうべくして反証的に論陣を敷いているのですが、ここも面白い記述があり興味が惹かれる部分がありました。
著者は、抜き書きしたような未来の変化の兆しをベイトソンに触れたことで見出したのですが、生物学的見地からのベイトソンの立ち位置では、「恒常性」や内的一貫性の維持という法則があるから、生命や組織は、最初のナヴェンという性を入れ替える儀式のように、「対称的分裂生成がエスカレートすると、逆に相補的分裂生成が引き起こされ、それによってシステムの崩壊が回避されるという事実」があると言っています。
この恒常性という処を強調して考えると、筆者の考える未来と同様の可能性を工業主義社会の蔓延という形で迎えてしまうというようにも予測できてしまうとのこと。
そして、現実に我々が30年経った今経験しているのは、目下筆者の記述した未来へ挑戦中の我々がいながらも、工業からは脱して、別の道での錬金術的お金を生み出す資本主義の仕組みは今のところ恒常性を保って続いており、言うところの折衷案で進んでいますよという、言えて妙な面白い状態になっていますねというところでしょうか。
進んでいるとも言えますが、一方で、30年前から見えていた人には見えていた未来の枠の範囲から、僕らは抜け出られていないとも言えるわけで、寂しい気もします。
どこかで、恒常性という性質なのかどこかの誰かの意図なのかは分かりませんが、ある意味、新しい未来が見えなくなってしまっているのではないかという気分にもさせられます。
そしてそこから導き出したい希望的観測としては、ベイトソン的に言えば、この30年間の中で巧妙に裏に隠されてきたものが、もう一歩進めて、相補的にもうそろそろ表出してきて良いのではないでしょうかという意味で捉えたいと思っています。
この文章を書いているのは、コロナウィルスの騒動の真っ只中という感じなのですが、戦争や大災害で無数の人が被害にあいながら徐々に変わってきたことと比較すると、外的要因に言い訳できる状態で経済と生活のあり方が変わっていけるきっかけとして、この危機を上手く使えていけたのなら、また新しい全体性への一歩となるのではという希望を持ちたいということで、投稿させてもらいたいと思います。


元というのも気がひける位、通勤ラッシュの皆無な在宅勤務&ノロウィルスで寝たきりになり久々の読書三昧で遊んでいる多読書評ブロガー石井拝