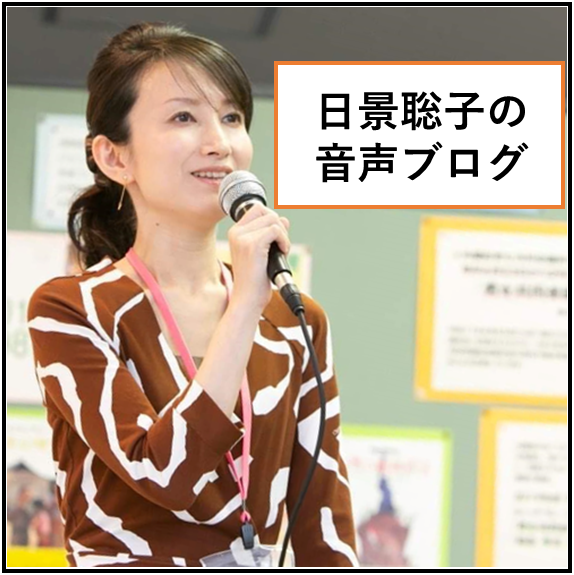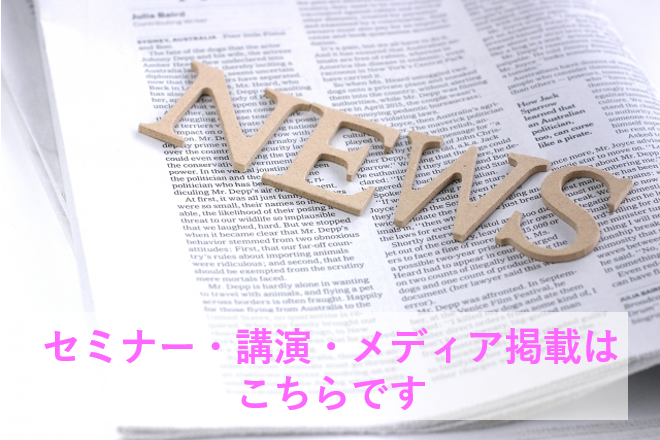刷り込み(imprinting)とは―
「鳥のヒナが自分がどの種族に属しているかを知る、きわめて短期間の、しかもやりなおしのきかない学習」
- コンラート・ローレンツ(2018) ソロモンの指輪ー動物行動学入門ー 日高俊隆(訳)早川書房
「動物の生活史のある時期に、特定の物事がごく短時間で覚え込まれ、それが長時間持続する学習現象の一種。刻印づけ、あるいそのままインプリンティングとも呼ばれる。」
- Wikipedia
先日YouTubeで鳥の生態について観る機会があり、刷り込みについても紹介されていました
。
ふと直美の問題とも関連するなあと思って、今回は取り上げてみます。
ニュースでたびたび話題になっていますが、美容医療の世界では「直美」(ちょくび;初期研修を2年間終えた後、各診療科の専門医養成プログラムに入らず直接美容クリニックに就職する医師)のトラブルが非常に増えています。
病気を治すために必要とされる保険診療の基本技術を習得せずに美容医療のみしか行わないため、いざという時の処置が適切に行えず、医療事故につながっている例が後を絶たないんですね。
やけどから死亡事故まで重症度はさまざまですが、トラブル対応が全くできずに他の医療機関に丸投げし、その後の経過も全く追わない・フォローアップ一切なしというケースもあるそうです。。。
私は美容皮膚科なので死亡事故はないですが、「『うちで対応できないので皮膚科で診てもらってください』と言われました」という方を診察したことは何度かあります。(ちなみに他院の自費施術に伴うトラブルの診療は自費対応になります。)
プロトコール通りにうまく行っているうちはいいのですが、何か不測の事態・合併症が出た時には保険診療の知識や経験が必要になってくることが多いんですよね。
昨今のコスパ・タイパを求める若い先生方は、「美容へ進むことを決めているのに、なぜ保険診療をしなければならないのか」と考えるそうです。
卒後すぐに自分の進みたい道へ行き、できるだけ早く症例数を増やせばいいじゃないかと考えるのも無理ないことです。
キラキラして華やかで、待遇的にも恵まれた世界が輝かしく見える時期もあると思います。
ただ、私の個人的な見解ですが、適当に数をこなせばいいものではなく、自分が施術・手術したお客様(保険医療機関ではないので敢えてそう書きます)の経過をきちんとフィードバックし、検証して技術を磨いていくからこそ症例数の多さがアドバンテージになるわけです。
術式は医師ではなくカウンセラーが決める、カルテは全く書かない(手術記録やレーザーの照射条件などの記録がないので、開示請求や裁判に耐えられないそうです)、執刀医は術後の経過を診ない、トラブルが起きても執刀医の診察を受けさせてもらえずに門前払いされる、という美容クリニックが非常に多いことは伝え聞いています。
高額な費用でオペをしたらそれで終了、ということですね。
あとでカルテを開いても、どういうデザインで縫合糸は何を使って、どのように手術したかが分からないという…
カルテ記載なし、術後診察もなし、トラブル対応もしない、なので自分の手術結果を見直してアップデートすることができないわけですよね。
保険診療の場合は入院される方もいますから、手術したら連日ガーゼ交換をし、糸を抜き、経過をみるという一連のプロセスを担当します。
また、感染や傷口が開いたなどの合併症が起きた時に対応し、その経過も診ていきます。
それがセットで初めて治療したといえるわけで、その積み重ねが自分の技量になるわけです。
私は研修医の時に「カルテを書かない医者はダメだから」「異常所見がないなら『異常所見なし』とカルテに書かなければそれは診たことにならないから」と、上司の先生に厳しく指導されました。(今ではこういう指導も、研修医に気を遣ってなかなか強く言えないみたいですね…)
そして大学病院時代、臨床写真の撮影や整理が若手の仕事だったので、写真の撮り方を詳しく指導されましたし、手術記録をきちんと書くのも当たり前でした。
その時に上の先生の過去の手術記録を見て学び、記録を書きながら手順を覚えていくわけですよね。
保険診療を経験すると、専門医を取る過程でこういうことが当たり前として体に叩き込まれるので、それを自費で展開する時も同じ向き合い方になるのですが、いきなり美容クリニックに就職すると全く違う世界になってしまいます。
臨床写真を撮るのはスタッフが中心ですし、そもそも撮らない施設もあります。
カルテを書かないのが当たり前のクリニックであれば、「そういうものなんだ」と思って書かないままになります。
技術の研鑽より知名度がほしくてTikTokなどのSNSに精を出すようになりますし、利益至上主義のオーナーのもとでは医療として全うな部分を削られてしまうことも多々あります。
ここで冒頭の刷り込みの話になります。(前振りが長すぎましたすみません)
自分で本格的に診療を始めていく医師3年目の時に直接美容クリニックへ行ってしまうと、そこで見たもの体験したもの全てがその人のスタンダードになります。
それ以外の世界を知らないのですから、どうしようもありません。
医師としての診療スタイル、仕事への向き合い方、すべてが弱肉強食の自費診療ベースになってしまいます。
医療機関とはいえ事業が傾けば閉院せざるを得ないので経営に無頓着であってはなりませんが、医療行為を行ううえで大事なものが欠けていることに気づけないのは致命的です。
保険診療であれ自費診療であれ、医療は生身の人間を相手にするため不確実要素が多い仕事です。
「美味しい部分」だけを経験するわけにはいかず、合併症や予期せぬ事態に対しても責任を持って対応しなければならないのです。
でも、トラブルシューティングの引き出しがない直美の先生方は、いざという時にお客様を露頭に迷わせることになってしまいます。
今回は分かりやすく美容外科を例にあげましたが、美容皮膚科も同じことです。
HIFUの合併症についてもニュースになっていましたよね。
直美の問題は実は根深くて、これ以上は書きませんが日本の医療制度の限界に関係しています。
保険診療の修行が5年以上必要な専門医を取得せずに美容の世界に入る先生は、これからも増えてくると思います。
専門医を持って開業した私が言うのも変ですが、たしかに専門医がなくても診療はできます。
しかし、イレギュラーな何かがあった時にどれだけの手を打てるかは、それまでにどれだけ修羅場をくぐったかによりますし、どれだけ責任を持って対応してきたかに尽きると思います。
その気持ちと環境があれば直美の先生でもきっと良い診療ができるのだと思いますが、現状では非常に難しいのでしょうね。
専門医の話や、医師としての修行の話は過去にも書きましたので、ご興味ある方はご覧になってみてください。