着物をもっと身近に
札幌から日々奮闘中の染太郎です![]()
いつもブログを読んでくださってる皆さんありがとうございます![]()
今日は僕がジーンズ着物を作るきっかけになったことを改めてまとめてみました。
自分で着物を一式揃えたことからすべては始まった
今では信じられないことですが、
毎日のように着物に接していながら、自分で着物を着たことがなかった入社当時の僕。(約9年くらい前でしょうか・・・20代前半でした(笑))
正直、着物は特別な時のものだと思っていました。
自分の周りに着物を着ている人は身内以外に全くいませんでした。
着物を身近にするためにはどうしたら良いのだろうと日々考えていましたあるとき自分に思ったんです。
そんなことを考えている僕・・・・なんで、スーツを着ているんだろう・・・・
(まだ20代前半だったので、ビジネスマンはスーツを着なければいけないと思っていたのでしょうか汗)
自分の行動と思いが一致していないことに気が付きました。
まずは、一式揃えてみよう!ということで、着物を着るのに必要なものを購入して着付け教室に習いにいったのを今でも覚えています。
自分で購入して、着方を習い、着用して初めて大切なことに気付く
これは、何とかしないといけない・・・・。
洋服に慣れている現代の人が踏み込むには色々な意味でハードルが高すぎる。
これが実際に感じた正直な感想でした。
着用するのが簡単な「男の着物」でさえ思いました。(←当時の僕の感想です。)
日々の仕事の中にそのきっかけが潜んでいた
ちょうどその時、依頼を受けて手がけていたことがありました。
それは、ジーンズの裾アタリの再現加工でした。
(裾上げしてしまうと、元々あった裾のアタリが無くなってしまうので色の濃淡がなくメリハリが無くなってしまうのです。)
なぜ・・・ジーンズの裾・・・・???
と思う方がほとんどだと思うのですが、「色を抜く」「色を挿す」という技術が当社ではありました。その技術を応用して裾にユーズド感を出す加工の研究を進めていました。
写真で説明するとこんな感じです。
(↑裾上げしたインポートブランドのジーンズの裾)
(裾を自然な感じになるように、色を抜いたり色を挿したりしてユーズド感をだしています。)
高級ブランドを始めインポートブランド、そしてビンテージのジーンズまで、本当にたくさんのジーンズの裾のアタリ再現を行いました。
中には、何度もリペアをして直しているものやかなり履きこんでいるジーンズもありました。
その時、思ったんです。
着用すればするほど味が出るジーンズ。そんな着物があったら僕が感じた着物のハードルをなくすことができるかもしれない!
これが、僕がジーンズ着物を手掛けるようになったきっかけです。
きっかけからの現在までの道のりについてをまとめると、ものすごい時間がかかるのでまた今度にします。(笑)
「何を作るか」「どのように作るか」より前に「なぜ作るのか」
僕はジーンズ着物を作るようになってから、さらに「男の着物」が好きになりました。
それは、洋服と同じように着る場所によって着物をコーディネートする楽しみが増えたのだからかもしれません。
やはり着物は着るものですから![]()
寸法を直すことができ、染めて替えて色を変えることができ、作り直しができる着物。
日本人は昔からモノを大切にすることを日常に当たり前にしていたことに素直にカッコいいと思います。
最近思うのですが、
ブログは読んでくださっている皆さんへの自分の想いを伝える
お手紙なのかもしれませんね。
今日も読んでいただきありがとうございます。![]()
それではまた。
======================
【野口染舗 HP】
創業1948年
着物のしみ抜き・染替えは野口染舗にお任せください
HPはコチラから(無料相談を受けたわっております!)
【野口染舗Fecebook】はコチラから
【Shi bun no San HP】
キモノをファッションへ野口染舗がプロデュース
Shi bun no San(四分ノ三)
ShibunnoSanのフェイスブックページはコチラから
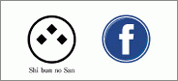
【Shi bun no San ONLINE STORE】はこちらから
======================




