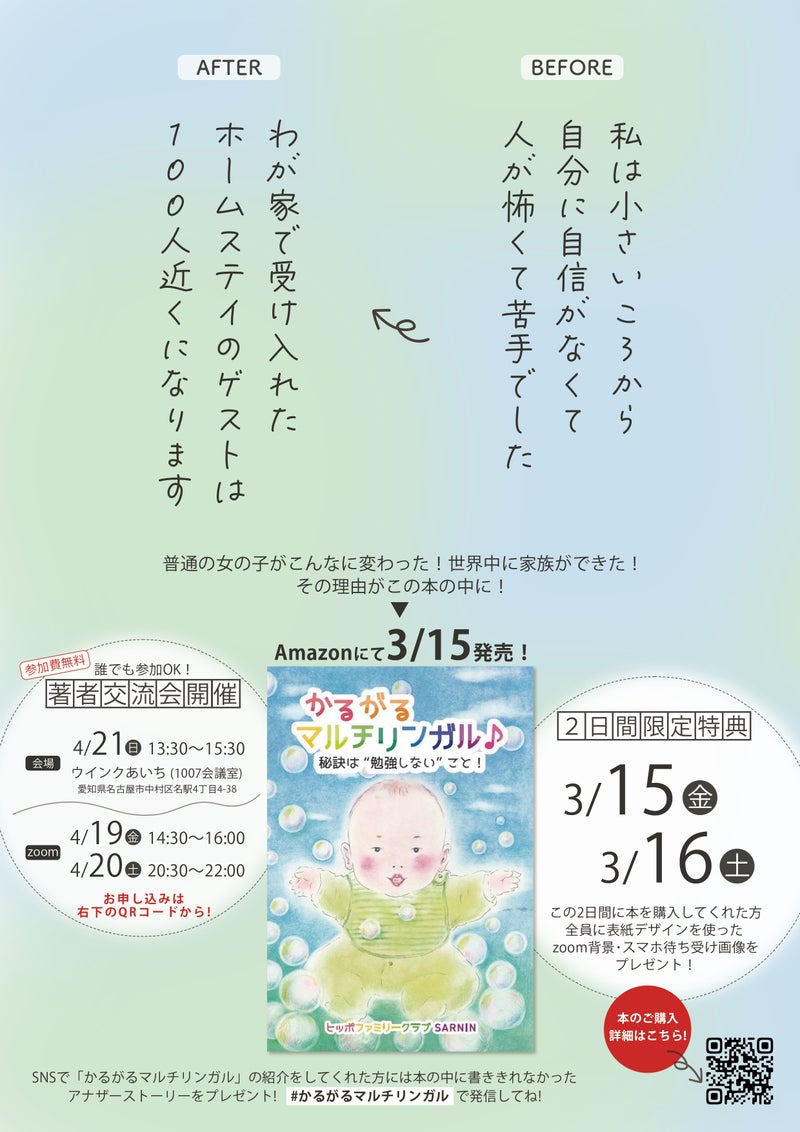ぼんそわー。じゅまぺーるサーニン♪
昨日書ききれなかったので続きです。
昨日は、便利さが不安をうむ、と書きました。
便利さは、持ち前の能力も衰えさせますよね。
私は最近、車に乗ると、何度も行ったところでもついついナビに頼ってしまって、ないとなんとなく不安だし、地図もなかなか覚えられないです。昔は自分で地図を見て道を覚えてちゃんとどこにでも行けたのに…。![]()
ことばも同じで、ことばでコミュニケーションをとることはすごく便利なんだけど、ことばに頼りすぎると、ことば以外のことを感じる力を使わなくなっちゃうのかな?
たとえば赤ちゃんを育てていたら、最初は赤ちゃんの気持ちがなかなかわからなくても、毎日赤ちゃんが今どういう状態なのか?どうして泣いているのか?何をしてほしいのか?一生懸命、見て、聞いて、感じて、想像しているうちに、ことばがなくてもかなりのことがわかるようになっていきます。
先日、イギリスにボランティアに出かけて、難民キャンプで働いていた子が、「英語が話せないナイジェリアの人が言うことを、みんなよく聞かないで遮るように翻訳機を使うのがいやだった。最終的には翻訳機を使うとしても、その前にまず聞いてあげればいいのに。指さしやジェスチャーで一生懸命言ってることも、私には状況とか様子とかを見てちょっと考えればすぐ想像がつくと思うのに、他の人は全然わかってあげられないのがふしぎだった」と話していました。
今、市役所などで「やさしい日本語」が広まり始めています。初めて聞いた時、いいことだな、と思いましたが、なんとなく違和感がありました。
ヒッポの仲間が、市役所の人に「ことばの壁なんてありませんよ。心の壁があるんです。やさしい日本語を使ったところで、心の壁があったら役に立ちません」と言ったそうです![]()
それを聞いて、ああ、そうだ!と腑に落ちました。海外の人に寄り添うことばを使うのはいいことだなーと思いながら、違和感だったのは、「相手の人に寄り添う心があれば、自然にその人に伝わる日本語になっていくんじゃないかな、それがやさしい日本語なんじゃないかな。わざわざやさしい日本語って作らなきゃいけないのかな?」と思ったからなんですね。市役所の人がやさしい日本語講座を学んだとしても、目の前の人をよく見て、聞いて、伝わってるかな?この人に伝わることばはどれかな?って寄り添って想像しなかったら、一人一人伝わることばは違うから、結局ことばの壁はなくならないんですね。ことばと心は切り離せない。ことばだけを心から切り離しても意味がないんです。
赤ちゃんや日本語のわからない海外の人の言いたいことを、大人よりも子どもたちの方が先にわかったりすることがよくあります。子どもたちはまだ、ことば以外の力を使って感じる世界に生きているのかなー、大人がことばに頼りすぎて衰えさせてしまった能力を使っているのかもなーと思います。
多言語の中にドボンと飛び込んで、わからないことばの中に浸っていると、そんな、五感を使って、見て聞いて、感じとり、寄り添い、想像する力がよみがえってくる気がします。
護郎先生が、「TOEICで高得点だからといって、よくコミュニケーションがとれるとは限らない。ヒッポの人の点数に表せない力を可視化するにはどうしたらいいか考えてみたい」と話していました。とっても楽しみです![]()
P.S でも、やさしい日本語が広がることで、市役所の人や私たち一般市民も、外国の人に寄り添う気持ちを持つ第一歩になるかもしれないなら、やっぱりいいことかもしれませんね~![]()
一宮市大和町での体験のお申込みは上記サイトからどうぞ![]()
ヒッポファミリークラブ公式HPはこちら
各地のイベントのお申し込み、日常のファミリー活動の場のご紹介はこちらからどうぞ。