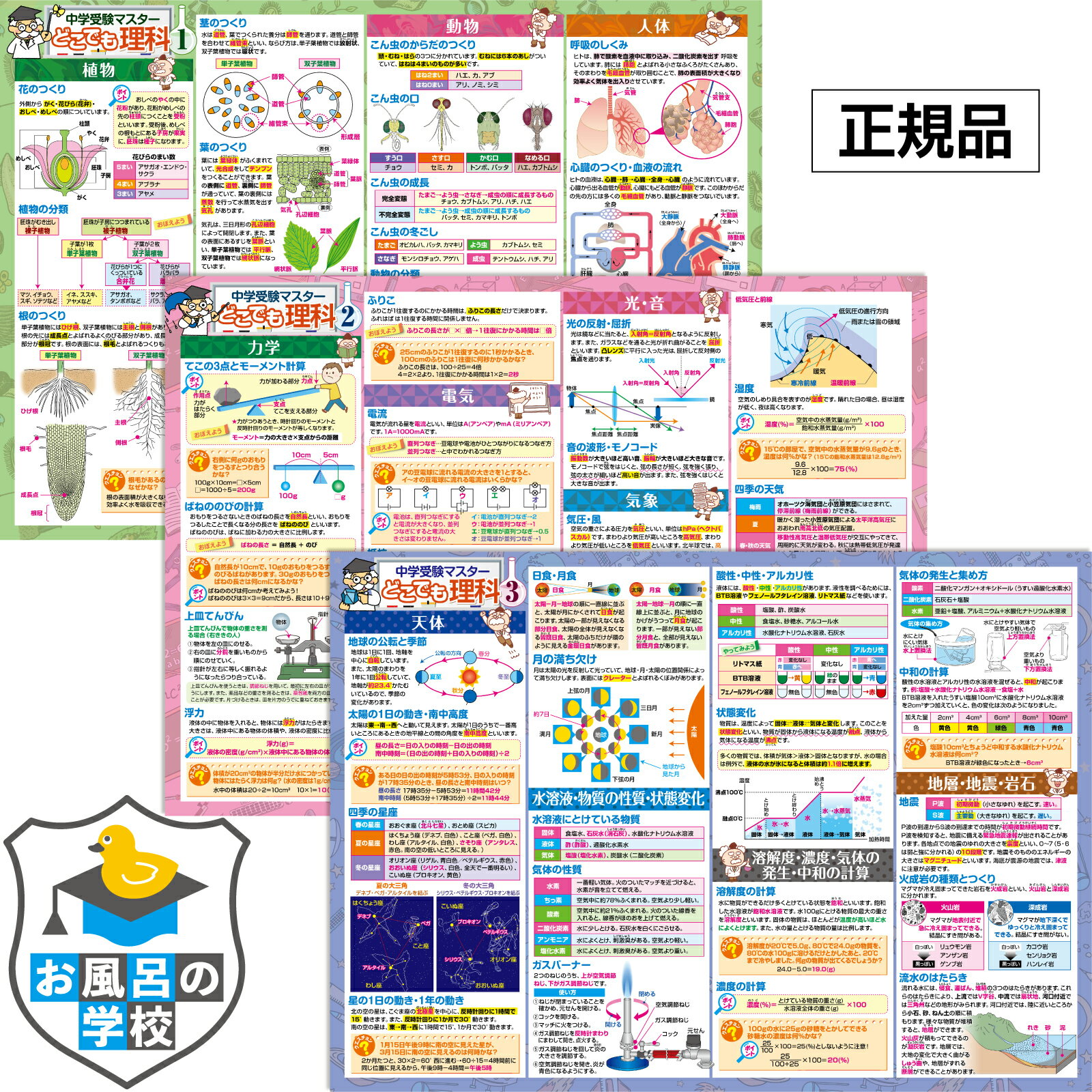ご訪問くださり、いつもお読みくださりありがとうございます。
前回の続きです。
遅くとも塾に新小4から通っていて、現在算数偏差値が50に満たない、という場合を想定して書いています。
繰り返しになりますが、四谷か日能研偏差値での50です。サピ、グノの偏差値50ではありません。
この場合、一にも二にも、「計算だ」ということは前回書きました。
加えてこのレベルの子が出来ていないのが「線分図を描く」「図を描く」「とりあえず書き出して見る」ということです。
この線分図を描く、という作業は出来る子は小1から訓練しているので、浜学園の最レベなどを受講していると小2で描けている子がたくさんいます。
遅くとも本当は小4の夏には出来るようになっていたい。
もし、このブログをお読みの方でお子さんが現在小4の方で算数がイマイチという方は、この夏までに絶対に線分図を描くということが自然にできるように。それだけを夏の目標としてもいいくらいです。小4ならばまだ夏にそこを重点的にやる時間的、カリキュラム的余裕があります。
上位校以上を狙うならば、遅くとも小4夏までには出来ていてほしいことですが、小5の現在算数が低迷しているお子さんは100%これが出来ていないと思います。面積図も自分で描けないでしょう。
加えて、カードの組み合わせを考える問題などでも「順番に書き出す」ということが出来ていないはずです。
飛ばしてみたり、同じものを書いてみたり、そういうことが苦手な子がいます。
小1の単元で、前から何番目、後ろから何番目という問題があると思うのですが、これに躓く子は算数センスが無い場合が多いです。お子さんがこの単元に躓いていた場合は、しっかり図を描いて説明してあげて、本人にも「描く」癖をここからつけてください。私は一つの判断基準にしています。
小さいほうから、大きいほうから、順にただ並べる、書く、いうことが3年生になっても4年生になっても、なかなか出来ない子がいます。
一方でこればっかりは、一度で理解して書き方も方法もマスターしてしまう子もいますので、地頭論にもなってしまうのですが、できないならば「訓練するしかない」のです。
この線分図、面積図、書き出し、これらをしっかり復習できるのは5年生ならゴールデンウィークが最後だと思って必死で取り組んでください。夏からは比が出てきて、図形の計算も複雑になり、ますます置いて行かれてしまいます。
4年生の場合は、まだ夏休み期間にしっかり身につけられればOKです。
言うなればここで身につけずに、4年を過ごしてしまった5年生が今、算数が低迷しているはずです。
きっと、塾の先生も単元のときにしつこく「線分図を描く!」「図を描く!」「手を動かす!」と言っていたはずです。
しかし、やらない子はやらない。
なぜやらないか。
「だって、描かなくてもだいたいわかるし。」「描かなくてもけっこう合ってるし。」![]()
大人からすると、「は??![]() 」何言っちゃってるの??と思いますが、子どもは本気でそう思っているんです
」何言っちゃってるの??と思いますが、子どもは本気でそう思っているんです![]() 。
。
7割くらい正解していれば、「あ、別に描かなくても出来るな~」「わかった、わかった」と講師の話や親の話を流しているのです。
その7割が、実はたまたま、の7割で、「描く」ことをそこで徹底しないせいでその後どんどん正答率が下がっていくわけです。
一見素直な子でも、解説をしたときに全然私の板書を写さない子がいます。
大手塾でわからなかったから、また私のところへ持ってきたのに、解説してもまた、写さないのです![]() 。
。
「この図、大切だから書いて」といっても式しか写さない。![]()
3回くらいその場で促して写さないと、私は諦めてとりあえず次へ進みます。(それ以上言うと雰囲気があまりに悪くなるからです。で、次回また言うようにします。)それくらい頑固な子っているし、「めんどくさい」というマインドが染みついている子は大変です。女子でも男子でも差はないです。
親御さんだったら、たぶんその場で「なんで写さないのよ!だから出来ないんでしょう!」と言うでしょうね![]() 。私もそう言いたい気持ちはありますが、こちらはプロなのでそこは粘り強くいくしかないわけです。感情的に言っても相手には届かないので。
。私もそう言いたい気持ちはありますが、こちらはプロなのでそこは粘り強くいくしかないわけです。感情的に言っても相手には届かないので。
この、「めんどくさい」と、あと4年のうちならば描かなくてもなんとなく正解できるレベルの問題があるので、スルーしてきてしまった子、というのが本当にここから大変です。
嫌がっても、しっかり「描いて解く」「書き出す」この癖を根気強くつけていくしかありません。
つるかめ算や差集め算でつまづくお子さんは、抽象思考も苦手なはずですが、それを補完するのは図しかないと思います。本人が腑に落ちるまで、描いて考えるしかないです。
本当につるかめ、差集め、線分図などが苦手な子にはサイパーからやり直しをおすすめします。
また、5年生の場合はこれから比が出てきますので、割合がしっかり理解できないといけません。この補完にもサイパーはおすすめです。
サイパーは基礎中の基礎から、段階を踏んで進んでいきます。簡単すぎるかも、と思っても算数偏差値40ならば戻るべきです。
また、3年生までの子の先取りにも適しています。
私は個人的な好みでもありますが、スパイラルシステムがあまり好きではなく、単元ごとにしっかり進みたいほうなので分野別の問題集が好きです。
便宜上予習シリーズなどを使いますが、あちこち分野が飛びながら進むのはあまり好きではないです。自宅学習ならではのカスタイマイズで息子はとくにサイパーで算数をほぼ学びました。
現在5年生で算数が苦手ならば、必ずこのサイパーの中に「これ」という苦手分野があるはずです。薄い問題集ですのでまずは1冊、やり遂げることをお勧めします。
あ、線分図のサイパーは、線分図が先に描かれてしまっているのもあって、本当に描けない子はそれを見てステップアップするのですが、そこそこ描ける子は「自分で描く」練習のために親が線分図を隠してコピーしてあげて、やらせるのがお勧めです。そのあたり、たしか過去に線分図の記事を書いたときに細かく書いているかと思います。
今回はとりあえず、まずはコレ!というお勧めの対策をご紹介しました。
また今後も折に触れていろいろな勉強法をご紹介してみたいと思います。
お読みくださりありがとうございました。