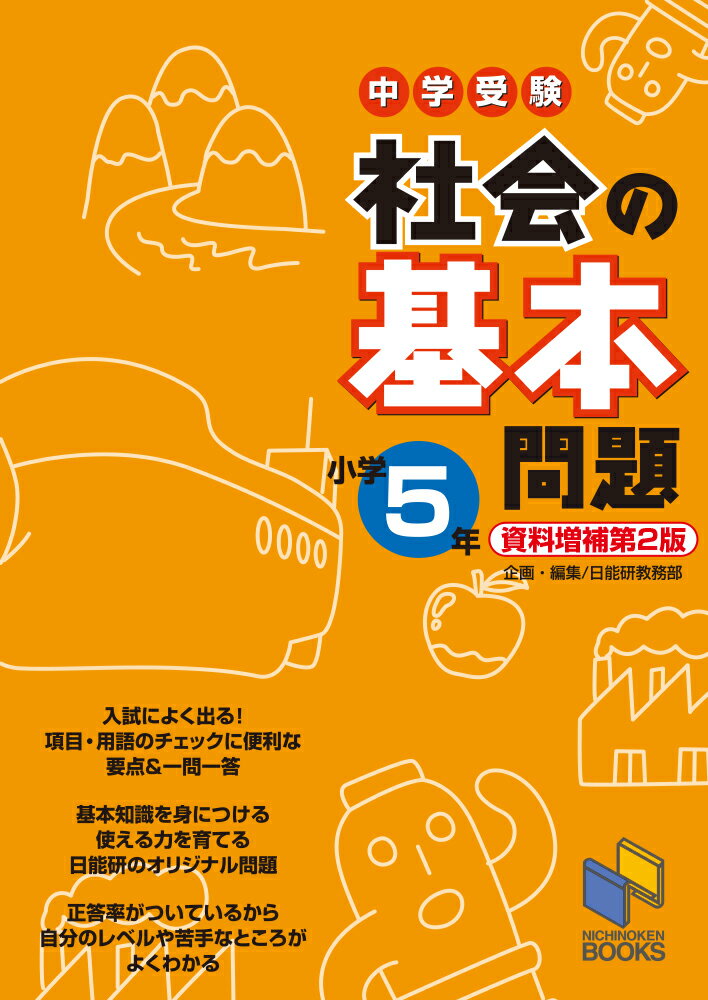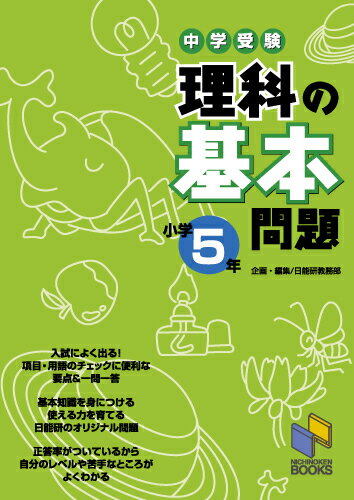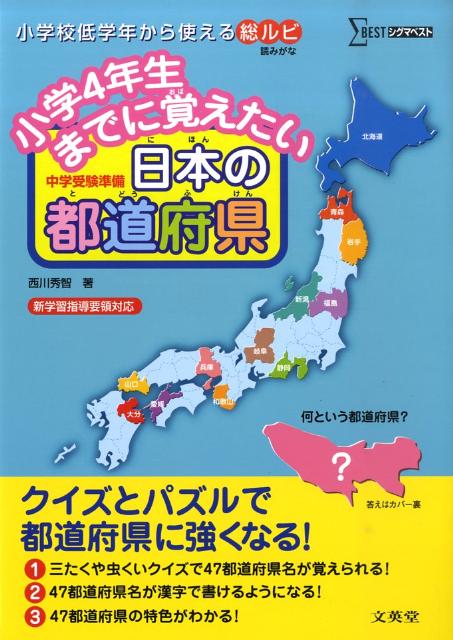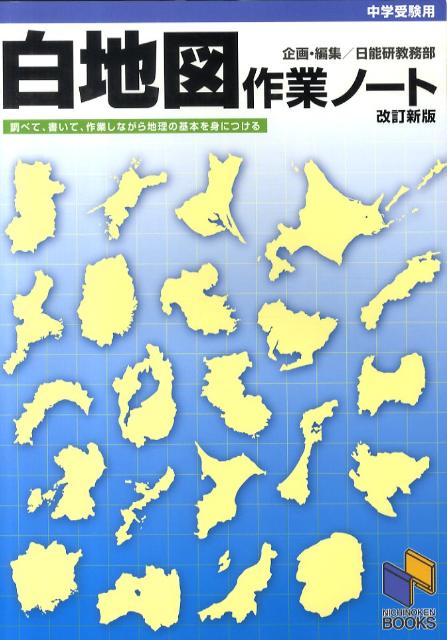いつもお読みくださりありがとうございます。
先日から続きで書いています。
今日は頂いた質問の中での理社対策について、もう少しこうしたほうがいい、と思う点を指摘させてください。
たぶんですがたくさんの方に共通している点がありそうなので取り上げさせて頂いています。決してこの方の方法がいけない、ということではなく、いつも言っていますが「これいいよ」と言われたってその子により出来る出来ない、合う合わないがあります。批判しているつもりはないので同じ方法の方、怒らずに読んでいただくか、これがすべてではないですし私もそう思っているわけではないので違うアプローチのブログをお探しくださいね![]() 。
。
ご質問で上がっていたのは現状として
「理科・社会は週末に演習問題集のまとめてみようと練習問題をやっています。」
「3理科・社会
・テストが解けない
練習問題は、その前にまとめてみようをやっているためかテキストを見ないで7割解けますが、月テストで3割ほどしか正解できません。」
ということでした。
私からすると、至極当然な結果であり、お子さんが特別できないわけではないと思います。普通のお子さん(学校のカラーテストならほぼ間違えない)がその勉強で3割はいたって当然です。
ではまず、月例テスト的な範囲のあるテストにおいて、理社、とくに社会で9割以上取っているお子さんが何をしているか、考えてみましょう。
9割の子その1:テキストの問題や宿題テキスト(演習問題的なテキストがあればそれ)の当該範囲はすべてコピーしています。
9割の子その2:宿題類はテキストには書き込まず、すべてコピー(またはノートなど)にやって、出来なかった問題に印をつけています。
9割の子その3:以上を塾のあった日の翌日までにやっています。
9割の子その4:週末に、最悪でも出来なかった問題すべてをもう一度。余裕があれば一から全部まっさらに解き直ししています。ここで正答できない問題はゼロになるまで繰り返しています。(同じ日に数度でも)
9割の子その5:範囲テストの2日前から前日に、出来なかった問題はすべてもう一度解いています。それでも間違えていれば集中的に確認。
能力が普通だな、と親が思う子、親がやらせないとあまり乗らないタイプの子で、3年や4年のテストで9割以上理社を取っている場合は、ほぼこんな感じの対策を「親が」やらせています。
何度もいいますが、ほっといたら偏差値40台の子が、なぜか理社できてる!という子です。そういう子は見ると大抵親御さんがいい意味管理しており、サポートしています。
私はこのサポートは親子で揉めないならアリだしとくに小5までの社会と理科の暗記系では有効だと思います。
この年までにしっかり覚えさせてしまうと、その後がかなり楽になるからです。
小4の地理と小5の歴史、これはがっつり覚えていればかなりその後がラクです。ただ懸念材料になるのが、小5まで親がかりで理社だけで4科目の偏差値を稼いでしまうと、後半どんどん抜かれる可能性があります。(最悪の場合、実力と四科の偏差値に隔たりがあり、受験がうまくいかないことがあります。)が、一方そのまま理社まで回らず低迷するよりマシ、だとも思います。
一応いつものパターンで(またそれかと言われそうですが)書いておきますが、上位1割くらいに入っている(2割に広げてもいいかも)子は、同じ点数9割以上でも
その1:授業を聞いてくるだけで理社は帰宅したら7割以上問題が解ける。
その2:授業中の様子を確認すると、先生が話していることで板書以外もきっちり自分で判断して「メモ」を取っている。
その3:宿題の問題の間違えたところをもう一度やれば、ほぼ正答できる。
その4:以上のような能力の子に、保護者がさらにコピーした問題を渡すと鬼に金棒となり、満点かそれに近い点数が普通の子より少ない時間で簡単に取れる。
こんなタイプもいますが、大抵は最初のパターンなので安心してください![]() 。
。
最初のパターンの子も理社なら4年5年のうちはそれだけやれば、偏差値55は取れます。そこから6年になって本当に力がある子は上がるし、落ちてももう30台に行くことはないはずです。45以上、50前後はキープできます。なぜなら、基礎をちゃんとやったから。
「やれば取れる」単元が絶対あるからです。理科の物理分野、化学分野になると途端に出来る出来ないの差がつきますが、そこで下がる子は絶対にそもそも生物の暗記分野と化学の基本となる暗記分野ができていません。そうなる前に、お子さんの偏差値を上げたい、でもほっといてもやる子じゃないのなら、「誰か」が見てあげるしか今の中学受験システムでは成績を上げられません。。。![]()
個別指導していて思いますが、親御さんは忙しいので、理社の細かい勉強の付き添いまでできないし、かといって塾も宿題を課すだけで見てくれない。私は理社を見る場合でも宿題の答え合わせと間違い直しまでしますが、正直それに1コマとかかかってしまいます。でも親御さんが見る時間がないのもわかりますし、バトルになることもあるでしょうから、どうしても成績を上げたくて、親塾で無理なら外注するしかないと思います。。。でも、親も「やればできる」かもしれません。4年のうちだけ、5年のうちだけでも見てあげるといいですね。
別立てで書くことですが良くないパターンとして、最初だけ親が張り切って、やたらコピーしたり、計画表作ったりして、でも親が三日坊主。。。。というのがよくあります。それはお子さんのメンタルにも良くないし、良くない勉強の仕方の見本になってしまうので、しっかり覚悟を持って介入してください。
私も親なので、仕事もあるし、大変で無理、というのは理解できます。でも子に無理をさせて中学受験をさせているので、そこは私も頑張ろうと思っています。
話が戻りますが、理社は塾からもらっているテキストを発展問題があればそれは抜かしていい(偏差値40台ならまずは50の壁を突破、次に55,とやり方の段階もありますので。)です。まず40台以下の場合は塾のテキストと宿題のテキストの基本とか練習とか(テキストによって違いますが)のレベルまでは完璧と思うまで仕上げること。それで50の壁だいたい突破できるはずで、しかし範囲のない公開テストになるとたぶん取れないので、そういうときが以前紹介した理社の市販の基本テキストが生かせます。
あとは、塾のテキストだとわかりにくいとか、子どもが飽きているような場合に市販をプラスするといいです。プラスといってもそのレベルの子に全部やらせることはできないので、同じ分野の問題をピックアップしてやらせる、というちょっとだけ負荷をかけていくやり方です。
あ、これはあくまで4,5年生。6年になればもう最後は理社はとにかく大量に負荷をこれからかけるしかないので、また違います。6年生の理社については以前書いているのでそちらも参考にしていただければと思います。
以前も3,4年の理社どうしよう、というテーマで書きましたがそれと今回は少し違うのはおわかりいただけると思います。
あれは、先取りメインの話です。
今回は4年の今の時期、だいぶ塾のテキストも進んでいる中での対策です。
塾の宿題に追われているでしょうから、とにかく理社は塾のテキスト最優先。参考書的に一般のものを追加するのがおすすめです。
一般といっても実は4,5年生向けのしかも基本のものって意外に少ないんです。6年生向けに全分野載ってたりするものが多くなっています。
ですので私が持っているのは
これは日能研が出しているので中学受験対策としてよくできています。とくに基本問題に特化しているので、苦手なところだけやるのもアリです。
ただ、、、、1つ問題は、良くも悪くも日能研が出しているので、今現在日能研に通っていると、テキストや宿題の問題と同じかそっくりなはずです。(最新の4年テキスト等を確認していないので、絶対ではないですが)
なので、理社というのは本来は同じ分野をいろいろな角度から聞かれても答えられるようにしないといけないので、切り口が違うほうがテスト対策にはなります。
ただ、現時点で偏差値40台であればこれをやってみて「簡単すぎる」ということもないと思うのでやる価値はたとえ日能研生でもそうじゃなくてもあると思います。
あとは、都道府県に特化したものなら低学年向けにもたくさん出ていますしそういうもので基礎からやるのもいいです。
もちろん塾で配られている白地図、これも絶対やったほうがいいです。
長くなりましたが今回もお読みくださりありがとうございました。
明日、国語について書いてみたいと思います。
よろしければまたお付き合いください。