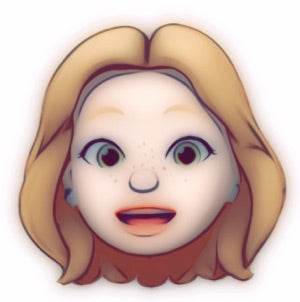「段」の仕組み!!
「段」の仕組み!!

このブログのスタッフのシェリーです
文楽の咲寿太夫さんの文楽の中の人ならではの日常からその魅力をお伝えする記事と、わたしの文楽を中心とした

さてさて今日のテーマは!!!
「段」
文楽のお芝居ではそれぞれのお話のタイトルが「〜の段」という風につけられているの
黒衣の人が出てきて「東西〜このところ相勤めまするは、〜の段」って言う、あれね。
ここで言う「〜の段」は小説でいうところの第○章 ○話 の○話にあたる部分。
文楽ではこの「章」も「話」も「段」に置き換えられるの。
例えば、義経千本桜だと
二段目 大物浦の段
三段目 すし屋の段
四段目
となるの

https://amzn.to/2NF43nx
ストーリーで楽しむ
文楽・歌舞伎物語(3)
「義経千本桜」
さて、文楽のお芝居では、この「○段目」という章にあたるものが、
世話物*は三段構成
時代物*は五段構成
になっている
*世話物は町人のお芝居で、時代物は武士など源平や朝廷や幕府のお芝居。
これは能楽の序破急からきている
この序破急の中の破の中にさらなる序破急があって、それで五段構成になっているのが時代物なの。
のだけれど、じつは外国をみてもこの五部制はよく見られ、フライタークの演劇五部ピラミッドなどが有名
もう一度、義経千本桜を例に出してみるわね

https://amzn.to/2yM6f2b
絵巻「義経千本桜」
まずは
序 (発端)
初段
大序 院の御所の段
中 北嵯峨庵室の段
切 堀川御所の段
破/序 (葛藤)
二段目
口 伏見稲荷の段
中 渡海屋の段
切 大物浦の段
破/破 (頂点)
三段目
口 椎の木の段(小金吾討死の段含む)
切 すし屋の段
破/急 (転向)
四段目
口 道行初音の旅
中 蔵王堂の段
切 川連法眼館の段
急 (解決)
五段目
吉野山の段
とこのような構成になっているの

だいたいが一段目(初段)は悪が台頭するのね。
それで二段目でより深刻になってくるの
三段目になってその事態がいよいよ頂点になって、そこで犠牲者がでて事態に光が見える
そして四段目で善が栄えて悪が滅びるの
五段目で大団円!!
こんな感じね
次回はこの五段構成がもう少し複雑になっていく例をご紹介するわ
また次回お会いしましょう。
シェリーでした
https://www.ntj.jac.go.jp/sp/
日本芸術文化振興会サイト
国立劇場・国立文楽劇場
文楽公演はこちら!
https://www.bunraku.or.jp/index.html
500円で文楽を観られるワンコイン文楽や
文楽地方公演など。
https://www.ntj.jac.go.jp/sp/schedule/bunraku/2019/2523.html
文楽素浄瑠璃の会
https://amzn.to/2yM6f2b
絵巻「義経千本桜」

https://utme.uniqlo.com/jp/t/MgEHNiE
三味線トートバック
LINEスタンプ

https://line.me/S/sticker/8293182


https://line.me/S/sticker/7778886
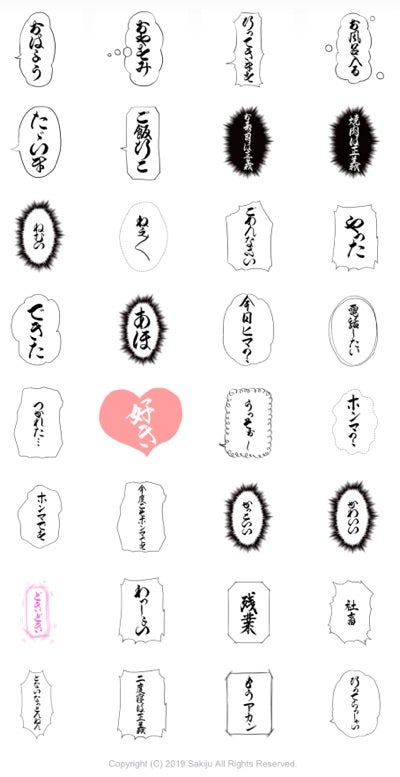

https://line.me/S/sticker/7681030
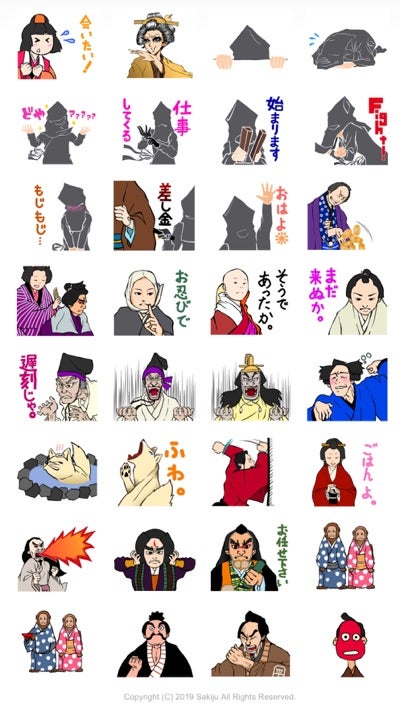

https://line.me/S/sticker/7110818