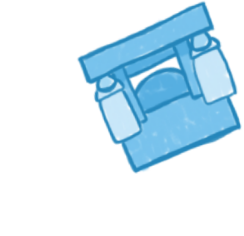 お稽古
お稽古咲寿太夫です。
お客さまやフォロワーさんに、「舞台のない日は師匠のお宅へ行っています」と言うと、「お稽古ですか?大変ですね」と言っていただきます。
いえ、そうではないんです。
普段師匠のお宅でしていることというのは、いわば執事のようなこと。
 https://amzn.to/2lfXpWY 執事だけが知っている 世界の大富豪 58の習慣 | ||||
内弟子を通いでしているようなもので、とくにぼくは末弟なので、事細かに用事をさせていただいております。
落語家さんにも内弟子の修行期間がございまして、ほとんどの方が2年間だそうです。
我々は一生仕えておりますので、文字通り、一生修行期間でございます。
もちろん、それぞれの師弟で修行方針は違いますので、そういった家のことは全く弟子にさせないといった師匠もいらっしゃいます。
人それぞれです。
それで、お稽古はどうしているかというお話です。
これは、床つまり太夫・三味線と人形で形が変わります。
 https://amzn.to/2lhdPyr 仏果を得ず | ||||
人形遣いさんの仕組みとしましては、三人遣いあるうち、主遣いの方が左と足に指示を出して人形を遣ってらっしゃいますので、基本的には主遣いさんの意図でひとつの人形は動くそうです。
ですから、普段のお稽古といいますと、主遣いさんは自分の役の稽古をひとりでされ、左と足の人は舞台稽古(つまりリハーサル)までは三人揃って稽古ということは少ないそうです。
主遣いさんの合図というのは身体の筋肉の動きを伝って足の人や左の人に伝わるものだそうで、いわば、普段の本番の舞台で身体で覚え、いついかなる時、どのような合図がきても身体が自然についていくようにしているのだと聞きました。
実地訓練といいましょうか、本番でないとできないのが、左と足の方のお稽古だそうです。
 https://amzn.to/2jQub0C 簑助伝 | ||||
床の話に戻りますが、太夫・三味線が若手の場合、もちろんそれぞれの師匠方にお稽古をつけていただきます。
が!
もちろんここは学校ではありません。
懇切丁寧に毎日毎日授業があるわけではございませんで、自分たちで稽古をしたものを最後に師匠方に聞いていただくわけでございます。
するともちろん「それでいい」なんてことはあり得ない訳で、そのお稽古でダメ出しをたくさんいただきます。
それで、「そしたら舞台稽古でまた聞くわ」。
もし運がよければ、「そしたら明日もやろか」。
1日、2日していただくお稽古でいただいたご注意は、全て覚えなければいけません。
そうして、最後に公演直前の舞台稽古で床と人形が揃って稽古します。
浄瑠璃がきちんとしていれば人形は遣える、と昔の芸談に書かれてありまして、中にはそんな浄瑠璃じゃあ人形は遣われへん!と怒鳴った名人もいらっしゃるとか。
 https://amzn.to/2lhMMmG 文楽芸段 三味線 竹澤團七 橋寿のつぶやき | ||||
人形遣いの主遣いの方は、浄瑠璃を頭に入れ、そうして人形を遣われるわけですから当たり前のことです。
ですから、舞台稽古一日のみで合いますし、合わなければいけないのです。
これが、文楽のお稽古です。
LINEスタンプ
https://line.me/S/sticker/7110818
LINEスタンプ02
https://line.me/S/sticker/7681030
LINEスタンプ03
https://line.me/S/sticker/7778886
LINEスタンプ04

https://store.line.me/stickershop/product/8293182





