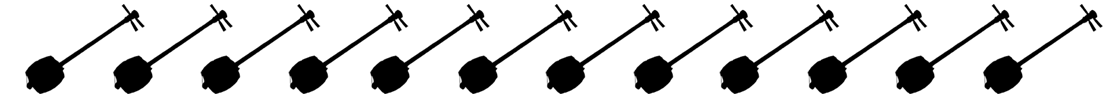■鳴響安宅新関
勧進帳の段
「かやうに候ふ者は、加賀の国富樫の某にて候ふ。さても頼朝義経、御仲不和にならせ給ふにより、判官殿奥秀衡に頼み給ひ、作り山伏となつて御下向の由、頼朝聞し召し及ばれ、国々に新関を建てゝ、山伏を堅く選みもうせとの御事にて候ふ。さる間このところをば某承つて山伏を留めもうし候ふ。今日も堅くもうしつけばやと存じ候ふ。いかに誰かある」
「御前に候ふ」
「今日も山伏の御通りあらばこなたへもうし候へ」
「かしこまつて候ふ」
旅の衣は篠懸の、旅の衣は篠懸の、露けき袖や、しをるらん。
これやこの、行くも帰るも別れては、知るも知らぬも逢坂の山隠す、霞ぞ春は恨めしき。
鴻門楯破れ、都を後に義経公、馴はせ給はぬ旅姿、身は山伏の強力と、袖の篠懸露霜をいつを限りとしら雪の、越路の春に急ぐなる、御心根ぞ、痛はしき。
さて御供の人々には、伊勢三郎、駿河次郎、片岡八郎、常陸坊
弁慶は先達の姿となりて行く空や、海津の浜も、踏分けし芦の篠原波寄せて靡く嵐の烈しきは、花の安宅に着きにける、花の安宅に着きにける。
義経公あたりを見廻し、
「いかに弁慶。かく行く先々に関所を設け、山伏を堅く選むとあれば、所詮陸奥までは思ひも寄らず。名もなきものゝ手に掛からんよりはと、覚悟はとくに極めたれども、その方が諌めを用ひ、かく新客に形を替え、木にも草にも心を置く、微運のわが身。げにや思ふこと儘ならぬこそ浮世なれ。われはいかなる
と仰せに皆々『はつ』とばかり君の御運の拙きを、思ひはかって顔見合はせ、無念と落す涙の雫、安宅の関の道芝に、朝露置きしごとくなり。
『かくては果てじ』と弁慶は気を取直し、
「いかに強力。疲れはさこそいま一息、気を励まして歩むべし。いざとほらん」
ともろともに関の方へぞ立ちかゝる。
弁慶関の戸に声を通じ、
「いかに関守殿。御役目御苦労千万。われわれ同行の山伏通行いたしたし。イザ開門あれ」
と言ひ入るれば、
番卒どもは口々に、
「スハ山伏の来たりしとか。イデ召捕へ一詮議。方々来たれ」
と立騒げば、
「こは粗忽なり関守達。なにゆゑあつて開門もせず、召捕んとは狼籍千万。仔細いかに」
「ホヽ、その仔細といっぱ、頼朝義経御仲不和とならせ給ひ、義経公は作り山伏となって、奥州の御館秀衡に頼り給ひ、下向ある由聞し召し及ばれ、かくのごとく諸国に新関を構へ、堅く詮議を仕る」
「たとへ
「ハヽ委細承りて候ふ。ガそれは作り山伏をこそ留めよとの仰せなるべし。誠の修験者を留めよとの仰せにてはよもあるまじ」
「アアラむつかしの問答無益なり。一人もとほすことならぬ」
「ならぬ」
「ならぬ」
「ならぬ」
「ならぬ」
「ならぬ」「ならぬ」と高呼ばはり。
「ヤレしばらく待たれよ。富樫之介正広、それへ参つて糾さん」
と衣紋正しく立出でて、関の外面に打ち向かひ、
「ノウノウ客僧達。われは当所の関主、
と望む詞に、弁慶は、『はっ』と思へど、さあらぬ体。
「ハヽア仰せに従ひ、ただいま読上げもうすべし」
と笈のうちより往来の巻物取出し、勧進帳となづけつゝ、高らかにこそ読上げけれ。
「それつらつら思んみれば、大恩教主の秋の月
と『天へも響け』と読上げたり。
「ホヽ勧進の趣意承つて殊勝に存ずる。某も心ばかりの寄付仕らん。ヤアヤア者ども、布施物これへ持ち来たれ」
『はっ』と心得士卒ども、持運びたる白木の台、加賀絹袴そのほかに、多くの布施物取揃へ、御前にこそは並べけれ。
「いかに先達殿われ幼少のころよりも仏陀を帰依し、多くの聖に逢ふたびごと、その宗門の旨を聞けり、しかるにいまだ先達のごとき名僧に逢はざるゆゑ、修験の法の委細を知らず、いまわが尋ぬる趣を、一々お答へ下されうや」
「ホヽいしくも問はれし関主殿。愚僧が心得居るかどは、残らずお答へもうすべし」
「ホヽ早速の御承知過分に存ずる。さらばお尋ねもうすべし」
「しからばお答へ仕らん」
と互に形改むれば、義経主従息を詰めて『やうすいかが』と守りゐる。正広膝を進ませて、
「いかに先達。そも世に仏徒の姿種々あるうちに、山伏達の異形の姿は、いかなる仔細に候ふぞ」
「それ修験の法といっぱ、胎蔵金剛両部の旨を修し、嶮山悪所を踏開き、世に害をなす、悪獣毒蛇を退治して、難行苦行の功を積み、悪霊亡魂を得脱成仏させ、天下泰平の祈祷を修す。表は降魔の相を顕はし、悪鬼外道を降伏さす。これ神仏の両部にして、百八のいら高数珠に、仏跡の利益を顕す」
「シテまた袈裟を身にまとひ、仏徒の姿にありながら、頭に頂く兜巾はいかに」
「ヲヽ即ち兜巾は、五智の宝冠にして、武士の兜に等しく、十二因縁のひだをすゑてこれを頂く」
「シテ
「これぞれ
「黒き
「
「八つ目の草鞋は」
「八葉の蓮花を踏むにかたどる」
「シテ山伏のいでたちは」
「すなはちその身を不動明王の尊容にかたどるなリ」
「出入る息は」
「阿吽の二字」
「ムヽさてまた寺僧は錫杖を携ふるに山伏修験の金剛杖に、五体を固むるいはれはなんと」
「ことも愚かや、金剛杖は、
「ムヽシテ仏門にありながら、帯せし太刀はただものをおどさんためなるや。誠に害せんためなるや。これにもいはれあるやいかに」
「ヲヽこれぞ、柴打と号し、わが中興の聖人、大峰山に入りし時、深山幽谷を切り開き、御山に住む毒蛇を退治し、成仏させたるその功徳、また王法仏法に害をなす者は、一殺多生の理によつて、たちまち切って捨つるなり」
「ムヽ眼にさへぎり、形あるものは切るにもせよ、もし形なき陰鬼妖魔が、王法仏法に障碍なす時は、なにをもつて切り給ふや」
「ホヽ無形の陰鬼妖霊は、九字の真言をもつて切断せん」
「ムヽシテ九字の真言といふはいかなる義かや、ことのついでに問ひもうさん。サヽヽヽヽヽいかにいかに」
「ウムその九字の真言は、わが宗門の秘密なれども、関守殿の懇望黙し難く、いざ説き示さん。サつぶさに聞かれよ。
それ九字の真言は、
と、よどみ濁らぬ弁舌に、
富樫を始め並みゐる士卒、皆一同に舌を巻き感じ入つてぞ見えにける。
「ハヽかほど尊き客僧を、しばしも疑ひもうせしは、某が不念。アヽラ恥づかしや畏れあり。イザ布施物を御受納下されなば、某が悦びこの上なし」
「ハヽアコハありがたき大檀那。現当二世安楽、なんの疑ひあるべからず。重ねてお頼みもうしたきは、われわれは近国を勧進して、卯月半ばに登るべし。嵩高き品々は、それまでお預けもうし置く、鏡一面砂金一包は受納いたさん」
「ホヽなるほどご尤もなる御頼み。委細承知仕る。イザいづれも、心置きなくお通りあれ」
と赦しの詞に、先達は、
「コハありがたし」
と一礼述べ、
「イデイデかたがた急ぐべし」
と詞に銘々うち連れてしづしづ、関をとほりける。
はるか下つて強力は、悩める足を踏みしめながら、後に続いて出で行くを
「強力待て。イヤサ新客待て」
と、
聞くより皆々『はっ』とばかり、『スハわが君を怪しむるは、一期の浮沈極まりぬ』と皆一同に立帰る
「アヽしばし、あわてゝことを仕損ずな。ヤイ強力め、はやく通りをらぬか」
と叱りつくれは、
「アヽイヤあれはこなたより止めたり」
「ムヽなにゆゑあつて止められしぞ」
「サヽヽヽヽさればこそ。あれなる新客、九郎判官」
「なに」
「アハヽヽヽヽ、サ義経殿に似たるゆゑに止めもうす」
「ムヽスリヤアノ強力が、判官殿に似たるとな」
「いかにも」
「ハヽヽヽヽ、
ヤイ新客の強力め。日高くば能登の国まで参らうずると思ひしに、僅かの笈を負ふて後に下ればこそ、関守殿に怪しまれ、修行の邪魔なす奇怪者。惣じてこのほどより、なにゝつけても教へを背く憎い奴。エヽヽヽヽヽ、イデ物見せてくれんず」
と金剛杖を追取つて、情け容赦もあらばこそ、背骨腰骨きらひなく、さんざんに打榔し、
「いかに、かたがた賤しき強力が成敗に、御身達の太刀刀を借らんより、この杖にて打投さば、かれも成仏いたすべし」
とまた打ちかゝるを
「ヤレしばらく。それにて心中の疑ひ晴れもうしたり。われ等の不明は新客の災難。偽りならぬ先達の誠を見るその上は、鎌倉殿への恐れもなし。はやはや通行いたされよ」
「ハヽアありがたき関主殿のお詞。ヤイ強力め。大檀那の仰せなくば、打殺しても捨てんずもの。命冥加に叶ひし奴。以後をきつと心得をらう」
と鋭き眼にねめつけたり。
富樫之介は突立ち上り、
「われはなほも厳重に警固をなし、義経殿を詮議いたさん。いかに客僧、またの再会いざさらば」
『さらば、さらば』といひ捨てて、関のかなたへ入りにける。
後に皆々安堵の思ひ、
「またもやことのなきうちに、イザ急がん」
と関守に、暇を告げて主従は、関を遥かに。
***
「先の関をはや抜群にほど隔りて候ふ間、このところにしばらく御休みあらうずるにて候ふ。皆々近う御参り候へ」
「心得て候ふ」
「いかにもうし候ふ。さてもただいまの気転、さらに凡慮よりなす業にあらず」
「ただ天の加護とこそ思へ」
「関の者ども君をあやしめ、生涯限りありつるところに」
「とかくの是非をもんだはずして」
「わが君を助くること、われわれの及ぶところにあらず」
「驚き入つて候ふ」
「それ世は末世に及ぶといへども、日月いまだ地に落ち給はず。危き難を避けたるも、全く君の御武運を、神明仏陀の守護ある印。ハヽアありがたしありがたし。
さりながら敵を欺く計略なれど、正しき君を強力とするさへも、冥加至極と思ふ上、杖にて主君を打つ咎めの、空恐ろしき天罰を、受くべきわれは
と土にひれ伏し三拝九拝君を敬ひ奉り、つひには泣かぬ弁慶も、一期の涙ぞ殊勝なる。
「ノウノウ客僧達。某先刻各々方へ
と勧むれば、
武蔵坊心得て、
「げにげにこれも心得たり、人の情の盃を請けて心を取らんとや。
これにつけてもなほなほ人に、心なくれそ、くれはとり。怪しめらるゝな面々」
と弁慶に諌められて、この山陰の一宿りに、さらりとまとひして、ところも山路の、菊の酒を呑まうよ。
面白や山水に、面白や、山水に盃を浮べては、流に引かるゝ曲水の手まづさへぎる袖ふれて
「いざや舞を舞はうよ」
もとより弁慶は、三塔の遊僧、舞延年の時の和歌。これなる山水の落ちて巌にひびくこそ、鳴るは滝の水。
「食べ酔ひて候ふほどに、先達お酌に参つて候ふ」
「食べ候ふべし。いかに先達。とてものことにひとさし御舞ひ候へ」
「さらば舞はふずるにて候ふ」
鳴るは滝の水、鳴るは滝の水。日は照るともたえずとうたり。
「とくとく立てやたつか弓、心赦すな関守の人々。暇もうさんさらばや」
と笈を押取り、肩に打掛け、虎の尾を踏み毒蛇の口をいまこゝに、逃れ出でたる心地して
陸奥の国へぞ