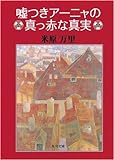米原万里を読まずして国際関係の学科を卒業したことを恥じた。
それほど、彼女の著書は1960年代~1990年代の中・東欧の混乱を詳細に示し、
かつそこに「歴史」や「民族」という集団でひと括りにしない、
歴史の上にたつひとりひとりの生々しい肉声が聞こえてくる、ほかに例をみない本だった。
米原万里さんは、こども時代の9歳~14歳、
1960年から1964年までチェコスロバキア(当時)に住み、
様々な国のこどもたちが通う8年生小中学校・「在プラハ・ソビエト校」に通う。
それは1980年代・激動の社会主義体制崩壊という歴史に進むすこし前の
その混乱にいたる背景となるできごとに溢れた時期だった。
一度も見たことのない祖国を、まるで見てきたかのように自慢し、
本来はムスリム人なのにイスラム教徒ではなく、アイデンティティもないと言ってのける。
そんな、様々な背景をもって育ってきた同級生たちに囲まれて米原さんは育ったのである。
その後、彼女はロシア語通訳として80年代、90年代を駆け抜ける。
『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』は、米原さんの60年代のこども時代と
80年代に大人になって3人の友人たちを大人になってから
確実な住所も情報も分からないまま訪ね歩くという描写になっている。
米原さんは日本に帰国してからも、プラハの春やユーゴの紛争など、
中・東欧での情勢が変わる度に「在プラハ・ソビエト校」の友人たちを想う。
どこの国が、民族が、という「マス」を見るのではなく、
生身の人間が頭の先をかすめながら国際情勢を見たのだろう。
私は国際関係論をやっていて、本当に腑に落ちなかったのは人を集団で扱うことだった。
そこに存在して、根をはって、暮しを紡いでいるひとりひとりの顔が見えず、
ただただ「~国」とか「~民族」、「~宗教」などと
乱暴に人を集団の中にいれこんで解釈しやすいようにし、
国際関係を、なんとも平和な大学の校内で述べる。
そういう自分に耐え切れなくなって、国際関係という分野をすぐに放棄した。
国際関係論を批判しているのではまったくない。
人の顔を見つつ、冷静に各国の背景と言語を考察し、
未来への解決策と本質を探るこの分野は
グローバリゼーションがすすむ現代に必要不可欠な分野だ。
ただ、ここで事実としてあるのは、私が、
人を「集団」の中に入れ込んでそれらを語ることを拒否した、ということ。
それは、先日小学校の行事で引率をしたときに、
こどもひとりひとりの顔も見れないままに集団の予定を確実に遂行しようと
「はやくはやく!」とせかして自己嫌悪に陥ったのとも似ている。
そんな中、米原さんの文章は出会ったひとりひとりの顔をまじまじとのぞきこみ、
葛藤も持ち合わせながらも、一歩引いた冷静さと人間らしい温かみを感じる文体で
友人たちを描写していた。とても共感のもてる文体だった。
「ユーゴスラビアを愛しているというよりも愛着がある。
国家としてではなくて、たくさんの友人、知人、隣人がいるでしょう。
その人たちと一緒に築いている日常があるでしょう。
国を捨てようと思うたびに、それを捨てられないと思うの」
米原さんの友人・ユーゴスラビアに住み自身はムスリム人であるヤスミンカの言葉である。
ナショナリズムではない、そこで暮らす人の顔、息遣い。
そこに愛着を持つこともアーニャが言うようにまた偏狭な民族主義なのだと言われるのかもしれない。
けれど、毎日、朝起きて、家族におはようを言って、ご飯を食べて、
洗濯をして、稼ぎに出て、仲間や友だちと会っておしゃべりして、勉強して、
近所の人におすそわけをもらって、ご飯をつくって、お風呂に入って、寝る。
毎日の暮しの中に、「ひと」がいる。
それは、国やその地域・民族への愛というたぐいではなくて、
有形無形の「ひとやものとのつながり」という財産なのではないか。
ナショナリズムとは違ったひとつの「生き方」のヒントがこの本にあるような気がしてならない。