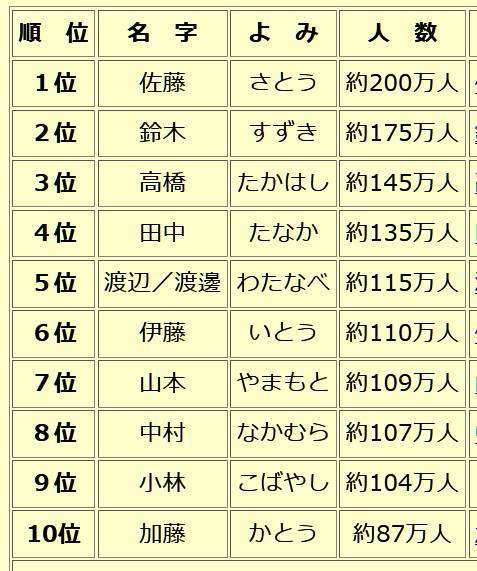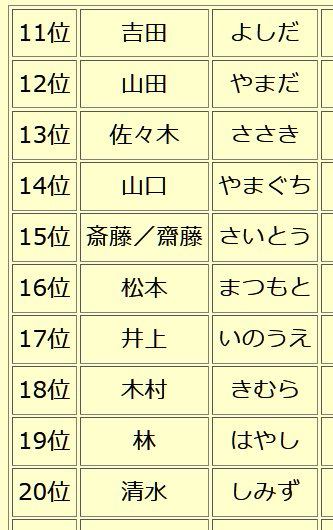光の存在がものを見えるようにし、また見えなくもしている。
けれどたとえこの上なく気高い創造物でさえ、暗黒と地上の影がなければ、いつまでも人の目に止まらない。そして天空の星も見えなくなる。 トーマス・ブラウン
太陽と月と・・・・
沖縄は太陽のイメージがありますが実は太陽よりも月の影響が大きいです。
それは旧暦が今だに生活に根付いているからです。旧暦とは、月の満ち欠けで時を刻む太陰暦が基本です。古代では太陰暦を基本に自然の移り変わりを見極めました。農業や漁業のタイミングを知らせてくれたのです。
しかし太陰暦だけでは四季がずれていってしまうという不便が出てきました。そのため、約半月ごとの季節の推移を表す二十四節気を組み合わせたのが「太陰太陽暦」いわゆる旧暦です。
この旧暦は琉球王朝時代に沖縄へ導入されました。そして暦に基づくさまざまな祭事・行事が行われるようになったとされています。
でも、なぜ沖縄は旧暦は今だに生活に根付いているのでしょうか?まず言われているのが中国の影響です。琉球王朝時代は中国と琉球は密接な関係がありました。
当時、大国だった中国と良い関係を維持する事で琉球は地理を活かした中継貿易を発展させました。中国アジアは中国との貿易の際には共通言語である「太陰太陽暦」つまり旧暦を使う事が何かと便利だったのです。
他にも、当時から沖縄を襲う台風や、農業や航海にも旧暦はしっかりとフィットしていたので生活に便利だったという事があります。
沖縄は正月が2回ある?
旧暦を日常的に使う事で非常に特徴的なのが「旧正」です。これは旧暦の暦上の正月です。現代の西暦の暦では1月の終わりから2月にこの旧正のタイミングがきます。しかし毎年同じではありません。
なぜ、毎年同じ日にならないのか?これには「月」を基準とする旧暦ならではの理由があります。
新暦では、地球が太陽を1周する日数を1年=365日とし、生じる誤差を4年に1度の閏年(うるうどし)に1日閏日を入れて調整しています。
一方、新月から満月、さらに新月までを1か月とする旧暦では、ひと月平均が29.5日となり、12か月では354日にしかなりません。この誤差を埋めるため、旧暦では約3年に1度の閏年に、閏月(うるうづき)を1か月入れて13か月にします。3年ごとに、13ヶ月の年がくる。旧正月が毎年変わるのはこのためです。
しかし、なぜ沖縄ではまだ旧暦は生活に息づいているのですが日本本土では使われなくなったのでしょうか?歴史を紐解くと意外な事が分かりました。
それは当時の明治政府の逼迫した財政事情が影響したものなのだそうです。wikipediaによれば
旧暦のままでは明治6年は閏月があるため13か月となり、月給制に移行したばかりの官吏への報酬を1年間に13回支給しなければならない。これに対して、新暦を導入してしまえば閏月はなくなり12か月分の支給ですむ。また、明治5年も12月が2日しかないので、11か月分しか給料を支給せずに済ますことができる。さらに、当時は1、6のつく日を休業とする習わしがあり、これに節句などの休業を加えると年間の約4割は休業日となる計算である。新暦導入を機に週休制にあらためることで、休業日を年間50日余に減らすことができる・・・
このような裏事情があり、旧暦が廃止され半ば強引に新暦が導入されたそうです。実際、この改暦は、布告がその一カ月前にも満たない旧暦11月9日という、非常にスピーディーなものであった事が歴史から見て取れます。政府も大変だったんですね。
もちろん、日本本土でも旧暦が生活にはピッタリくるはずです。それはアジア各地で旧暦を今だに使用している国が多い事でも分かります。
実は、旧暦1月1日を「旧正月」と呼ぶのは日本だけだという事です。中国をはじめとする多くのアジア圏では「春節(しゅんせつ)」と呼んでいます。今でも新年を祝う大事な日です。
中国語である春節は、中国語では「チュンジエ」韓国では「ソルラル、クジュン」北朝鮮では「ソルミュンジョル」ベトナムでは「テト」と呼ばれます。
さらに、この日は、ほとんどの国で祝日となっており、生活に根ざした大切な日だという事が分かります。ちなみに中国では、旧暦大晦日から7日間、香港・シンガポールは旧暦元日から3日間、韓国は旧暦大晦日から3日間、ベトナムは旧暦大晦日から4日間と長いものになっています。
ですから、沖縄に旧暦が息づいているのはむしろ自然な事で、日本本土に旧暦が無いのがむしろ不自然な事なのです。
私が幼い頃は、新暦の正月(こちらが一般的ですが)と旧暦の正月の2回の正月を祝いました。お年玉も少しづつを2回もらいました(笑)でも旧暦の正月の方が盛大でした。幼心に覚えています。ちなみに今でも旧正を盛大に祝う地域もたくさんあります。
他の旧暦行事
・生年祝い(トゥシビー)
旧暦1月2日~13日に行われる行事。沖縄では、12年ごとに巡ってくる生まれた干支の年が厄年とされ、火の神(ヒヌカン)や仏壇に安全祈願をします。そして来客者の祝いの心で厄を落とすために生年祝いを行います。数えで13歳、25歳、37歳、49歳、61歳、73歳、85歳、97歳に行われます。97歳の祝いであるカジマヤーは最も盛大にお祝いされます。また地域で合同の生年祝いを行うところもあります。まだ地域がコミュニティとして生きている沖縄ならではですよね!
清明祭(シーミー)
本土の方からは「お墓でピクニックをする変わった風習」と思われているようですが実は中国から伝わった祖先供養の行事です。
写真引用:結不動産情報ネットワーク
お盆、正月と並ぶ沖縄の人にとっては大事な行事なのです。旧暦の3月にあたる、4月中旬頃には家族や親戚で先祖が眠るお墓へ行き、みんなで重箱のお供え物をお墓の前で全員で食事をします。最近ではお供え物ではなくバーベキューやピザをする人もいます(笑)でも、家族や親戚でワイワイガヤガヤと楽しそうに食事をする風景はとても微笑ましいものです。形は変わっても先人もこのように一族の和をつないできたのがこの清明祭(シーミー)という行事だったのではないでしょうか。
旧盆
旧暦にもとづく沖縄のお盆です。旧暦7月13日?15日の3日間にかけて行われます。この期間、人々はお中元を携えて親戚を訪ねあい仏壇にお線香をあげます。旧盆は沖縄の重要な年中行事として、生活の中に浸透しています。
13日の「お迎え」(ウンケー)はあの世から祖先の霊をお迎えする日。14日は「ナカヌヒ」つまり中日です。、最終日の15日は「お送り」を(ウークイ)と言います。
沖縄のお盆の中で一番大切な日で、家族や親戚が集まり食卓や仏壇を囲んで過ごします。フィナーレの祖先をあの世にお送りする「精霊送り」は15日の夜更けに行われます。これも中国の影響を多分に受けているのですが線香と一緒に紙でできたウチカビといわれる天国でのお札も一緒に燃やして供養します。天国でお金に困らないようにとの思いがあるのです。でも天国でもお金を使わなきゃ何もできないのはイヤですね(苦笑)
写真引用:最初はスズメ
この旧盆のタイミングであの有名なエイサーが各地を練り歩きます。月が煌々と照らす中、踊られるエイサーはとても神秘的です。
これが新暦ではこのタイミングでは無理なので、やはり旧暦は沖縄の生活にしっかりと息づいている事を実感できます。
旧暦と琉球舞踊
沖縄では旧暦8月15日の夜は八月十五夜(ハチグヮチジューグヤ)といい、古くからお月お祭り(ウチチウマチー)という月を愛でるお祭りが多くあります。
この日の前後3日間、農村では豊年祭の村遊び(ムラアシビ)が盛大に行われたり、狂言、組踊り、獅子舞、棒術、綱引き、宮古ではクイチャーの踊りなどがあります。今も生活の中にこの旧暦8月15日の夜の八月十五夜(ハチグヮチジューグヤ)は息づいています。
写真引用元:©OCVB
十五夜に芸能を奉納するのって素晴らしくないですか?
琉球舞踊で「旧暦」と言えば、旧暦八月十五夜の舞踊で、「瓦屋」(カラヤー)という女踊りがあります。別名、月見踊りとも言われているんですよ。
瓦屋節は『ナガラタ節』、『瓦屋節』、『シャウンガナイ節』の3曲で構成される女踊りです。月を眺め想いをはせるる女性を歌っています。
できやよ押し連れて眺めやり遊ば
今日や名に立ちゆる十五夜だいもの
押す風も今日や心あてさらめ
雲晴れて照らす月の清らさ
月も眺めたりできやよ立戻ら
里やわが宿に待ちゆらだいもの
【意訳】
さあ連れ立って眺めて遊びましょう。今日は名に立つ十五夜ですから。
そよ吹く風も今日は心あるもののように、空も晴れ渡って照り輝く月がなんときれいなことか。
月も眺めたし、さあ、急いで帰りましょう。愛しい人がわが家で待っているはずですから。
爽やかなさらっとした雰囲気を琉舞では表現します。私も踊るのが好きな演目です。
一方で
瓦屋頂登て真南向かて見れば
(瓦屋根に登り、真南の方を見てみると)
島うらど見ゆる里や見らぬ
(私の生まれた里は見えるけど、愛しいあの方を見る事は出来ない)
この琉歌には悲話があると言われています。
首里王府は中国から瓦を作る技術をもった職人を呼び寄せ帰化させました。その帰化した中国人から見初められてしまった人妻が「旦那や子どもと別れて、瓦職人の妻になりなさい」と琉球王から言われたのです。哀しみの中で生活したその人妻が詠んだと言われる琉歌だと伝わっています。
瓦屋節の歌碑
写真引用:琉球の風光
彼女は瓦職人の妻となった後も元の旦那や子どもの事が忘れられず、小高い丘の上に立ち、自分のいた村の方向を眺めては涙を流していたとか。何と哀しい話でしょう。
写真引用:沖縄の風景
旧暦8月15日の夜は八月十五夜(ハチグヮチジューグヤ)には現代も語り継がれるそんな逸話があるんです。

現代科学では太陽系の中心には太陽があり、その周りを地球や他の星が回っています。太陽は主人公のような存在です。
でも一度、人間の生活を考えた時、月の満ち欠けに基づく暦がしっくりとくるのは面白いです。そして沖縄においてはこれから先も旧暦が廃れることなく続くでしょう。タイムマシーンがもしあるとしたら、昔の人がまだ続いている事にきっと驚く事でしょうね。
西暦を否定する訳ではないですが生活にピッタリとあった旧暦は一言で言えば「居心地が良い」です。この「居心地の良さ」が生活の質や満足度に繋がっているのなら、もしかしたら今、日本に必要なものかもしれませんね。(^_^)
そんな想いで今宵の月を眺めてみてはいかがでしょうか?
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました!
■ポチッと押していただくと嬉しいです!■
![]()
![]()