お休みだった今日は、お昼を回ってすぐに、ショルダーバッグに文庫本を入れて公園に向かった。下り坂の天気も、予報によればせめて夕方ぐらいまでは持ちそうだ。
けれど、公園で頁を開いて間もなく、雨粒がひとつ紙面に落ちた。
やれやれ。
少々の雨の中で自転車を走らせることはいとわないけれど、さすがにそこで本を広げることはできない。
諦めた僕は文庫本を閉じて、ブラックの缶コーヒーをショルダーバッグのサイドポケットに押し込んで自転車にまたがった。滞在僅か7、8分だった。
そうか、そんな時期だったんだ。
河原の土手に出た僕は、赤く燃える彼岸花を見つけた。群生はしていない。まるで飛び火のように赤い群れが点在している。

別名「曼珠沙華」は、ある日突然咲いて、僕たちを驚かせる。
河原の土手に、数本から十数本がまとまって、あちらこちらに赤を散らしている中を、ゆっくりと自転車をこいだ。
まるで焔(ほむら)のように、女の情念のように咲く花。
僕はふと、石川さゆりの歌を思い出した。
舞い上がり 揺れ墜(お)ちる
肩の向こうに あなた 山が燃える
それまでのイメージにない曲だったために、歌いたくなかったと、本人が明かしている記事を読んだことがある。
けれどいまは、「津軽海峡冬景色」と並んで石川さゆりを代表する曲になった。
「赤」は、本来は「閼伽」と書き、もともと仏前に供える浄水の意味するサンスクリット語の「アルガ」が語源。水が冷たいように他人にも冷たいという事で、縁のゆかりもない人の事を「赤の他人」と呼ぶようになった。
サンスクリット語 古代から中世にかけて、インド亜大陸や東南アジアにおいて用いられていた言語。古代インドの標準文章。梵語(ぼんご)。
─由来・語源辞典より─
でもこれは、俗説ですね、たぶん……。
水が冷たいように他人にも冷たいという事で、縁のゆかりもない人の事を「赤の他人」と呼ぶようになった。
これはこじつけを感じます。素直に信じ込まない方がいいでしょうね。
赤という言葉は、もともと「明(=明るい)」という言葉が語源になるので、あきらかで疑いのないことを意味しているものです。
「赤の他人」にはこっちの方がしっくりきます。
「真っ赤なウソ」の赤もその類ですね。
黄色?
いや、白だったか。
かつて欠かさず訪れていたころは、確か咲いていたはず。

白い彼岸花を探して自転車を走らせると、数本がすっくと立つひと群れだけ見つけた。
でもそれは、一部しぼみかけの花だった。彼岸花の命は短い。
河原のサイクリングロードに降りて、さらに自転車を走らせたけれど、結局見つけることはできなかった。
あ、あれ……登場の時の顔、どことなく篠原ともえを思わせるんじゃないの?!↓↓↓↓
ま、それはさておき、たまにはこんな曲もいいですね。
僕の中には明らかに、日本人のDNAが流れているんだなと感じる瞬間です。
まだ若い石川さゆりと、どろどろとした曲のギャップが妙にマッチして、加えて声量的にも一番いいころかもしれません。
刻んで畳み込んでくる詞も、メタファーを思わせる「山が燃える」の部分もいいですね。
─石川さゆり/天城越え─
ポチポチッとクリックお願いします。
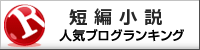
短編小説 ブログランキングへ