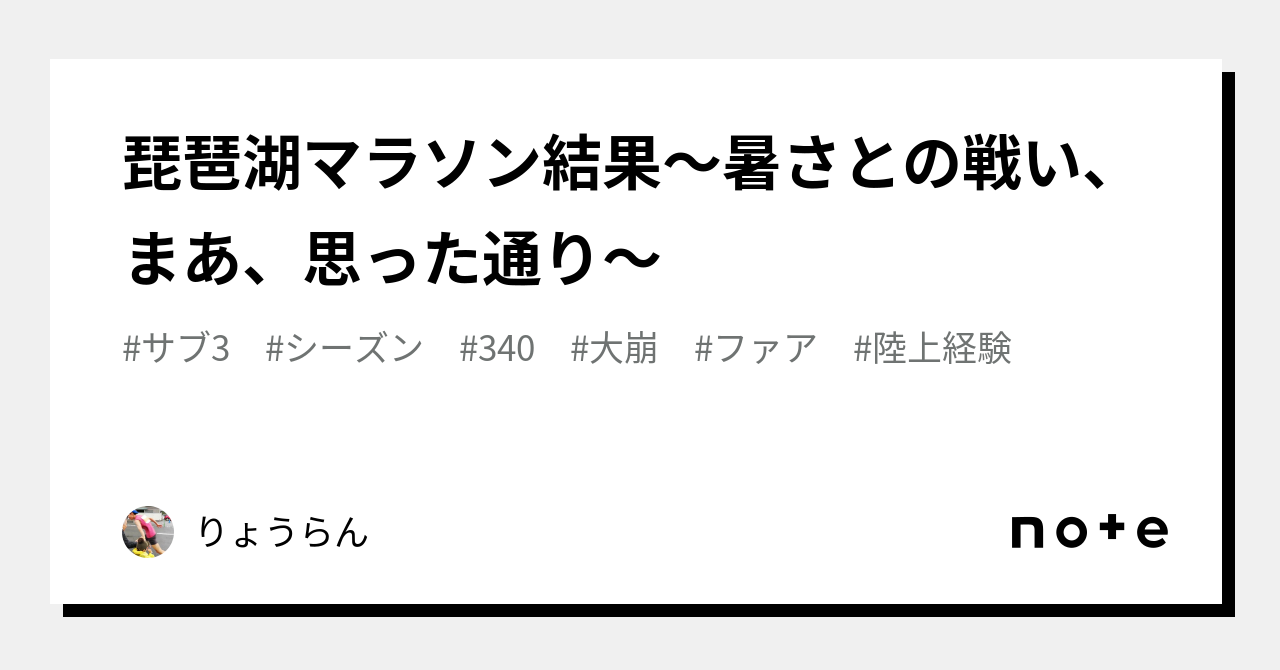3月10日びわ湖マラソン。
例年3月に入ると気温が確実に上がってくるので、記録を狙う攻める走りはできない。去年もかなり気温が上がるレースで超守りのレースでした。
今年もどうせ気温が高くなるから先月走った京都マラソンで実質終わりと気楽にかまえてましたが、1週間前の予報見てると、寒気が来て最高気温一桁の予報。
予報が変わることなく、実際も当日の気温は自分にとってベストコンディションでした。
気温一桁のレースを走れるのは4年ぶり。それが3月のレースとは思ってもみませんでした。
今シーズンの3回のレースは15度超え、去年も、一昨年も、3年前も。10度台前半のレースさえ走れてなかったです。
スタート待ちでカッパを被っても、ぶるぶる震える、この感じ、4年ぶりでした。ただ4年前のPB2:29を出したときの走力はない、32,3分を出せれば、と思ってスタートしました。
ペースはキロ335くらい、30キロ過ぎてからは少し落ちてぐらいでいければと。
先に結果を言えば、2:31:36。3rdベストでここ4年ではベスト。上手くレース運びできたので、その内容書きます。
最初の5キロくらいは330前半のペースで20人以上の大集団。その後ろの方。近江大橋を超えたあたりで先頭が少しペースアップし320後半。ここで人数が減り12,3人。
上がったのはその1キロでまた330前半に落ち着く。余裕があり、この集団の後方で力を使わず走れればと思ってましたが、、
14キロ過ぎの少しの下りを利用して先頭が一気に320付近まで上げました。ここで先頭につくか、つかないかが、今回のレースの一番のポイントだったと思います。
この時点でつける余力はありましたが、ここにつくと後半に必ず潰れると考え、つきませんでした。ついていく人のほうが多く前の集団は7,8人。つかなかったのは自分含め5人。
このあたりの判断は経験も必要だと思います。ハーフならついていくだけついていくですが、フルの場合、余力があってもつかないという選択も時にはするのが結果に繋がると思います。結果的にその集団の5人くらいは後半で抜かしました。
琵琶湖博物館のあるフィニッシュ会場の少し前ぐらいまで、その5人くらい、あまり固まれず、ついたり離れたりでした。その途中でハーフの電光掲示板があり、経過時間が1時間15分を3秒程度切ることを確認しました。
ここではイーブンでは到底無理、後半2,3分落ちに抑えられるかと思いました。
フィニッシュ会場前25キロくらいで3人集団になりました。うち1人が半島を出る少し手前からペースアップ。330を切るペース。
ここはつこうと2キロぐらいつきましたが、、今回はそれほど余力なく自然にその1人とは離れていきました。
半島から出て、北風の影響もあってペースが落ち、琵琶湖大橋近くのコースの北端35キロ付近まではペースが落ちました。
あと一人とも少しずつ離れていきました。ペースは340台前半で単独走。落ちてはいるものの、初代アルファフライのフォア、エアポッドでまだ踏めていたので、最後まで走りきれる感覚はありました。
北端を過ぎ、競技場も超えて南下すると、追い風方向になり一気に楽になりました。風速数メートルでそんなには強くはなく、風を感じることはなかったですが。
ここから340を切るペースで40キロまで。きついはきついですが、まだ足も残っていて、30キロからついていけなくなった1人も含め、数人拾いながらの走り。
40キロを超えて、1人拾い、ラスト1キロの看板が見えたとき、2時間28分だったので、これは31分台は行けると確信し、少しペースアップ。残り500メートルくらいでまた1人拾い、最後、琵琶湖博物館の丘を上り下ってゴールでした。直後は数分座り込むほどの追い込みでした。
5キロ毎。総合14位。
特に後半順位を上げていることがわかります。

ということで、いい形でシーズン最後のフルを走れました。気候が良ければ、タイムが出せるということも証明できたレースでした。
厳しい見方をすると、分かってはいたことですが、ベストコンディションでもサブ2.5はできない、今その走力はないということになります。
やはり、加齢に伴うスピード低下を感じたシーズンだったので、マラソンオフシーズンの夏場だけでなくシーズン中もスピード練習を欠くことがないようにして、次シーズンはまたサブ2.5を狙える状態に持っていきたいです。今でもかなり難しいですが、加齢すればするほど難しくなっていくので。