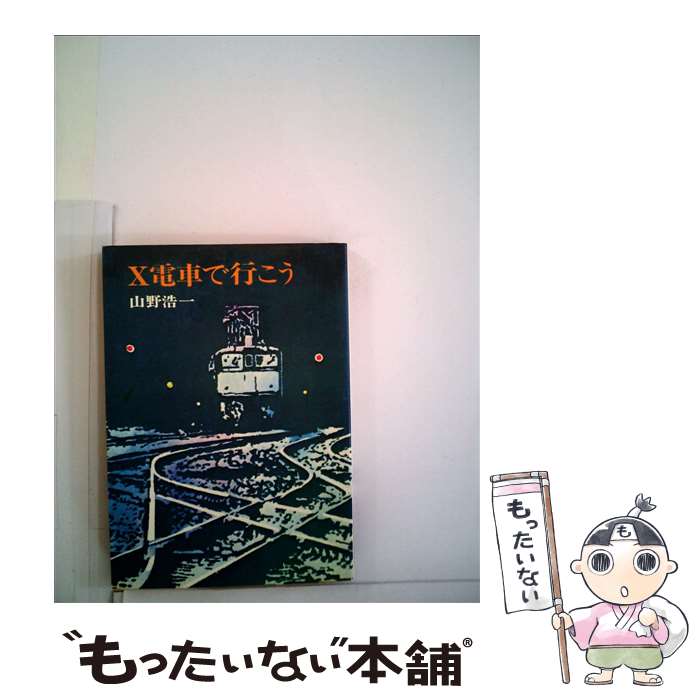<田中光二、
高斎正、
山野浩一>
942「幻覚の地平線」
田中光二
中編 伊東典夫:解説 早川文庫
目次
1.幻覚の地平線
2.閉ざされた水平線
”幻覚境”
と呼ばれるヒッピーたちの楽園から
忽然と消え失せた人々。
その謎を調査するべく、
ロスはLSDの妖しい幻覚が支配する世界へと
足を踏み入れていく……
管理社会に反抗する人々を描く表題作他、
抹殺しあうことを宿命とされた人工受精児の話
「閉ざされた水平線」等、
俊英が描く二大中篇。
<1986:ハヤカワ文庫解説目録>
70年代から登場し始めた、
”SF作家第二世代”
の先陣を切るのは、この人。
後になって知った、
あの 『オリンポスの果実』 の作者、
田中英光の息子さん。
そう、太宰の墓の前で自決した――。
それはともかく、このお話。
アメリカ全体がヒッピーの解放区、
「幻覚共和国」(サイケデリア)
となった時代。
ロス・グリーンフィールドは密輸の罪で挙げられ、
釈放の条件として「サイケデリア」に潜入することになる――。
ここから露わになる、超能力者やドラッグの存在。
そう、ディックの世界観と相似している。
サイケデリアの長たちは、
”トリップ”
するのですが、
それが超能力によるものなのか、
幻覚キノコによる暗示によるものなのか。
で、ロスの報告以外にも、
いろいろな諜報作戦が並行していて、
最終的にはこのサイケデリアに
核が打ち込まれることになる――。
だがそこに残されたものは……。
旧世界と新世界の闘争は、
殺戮を伴わざるを得ないってことでしょうか。
ミュータント狩りなんかを大規模に扱うと、
こうならざるをえない。
『スラン』 とか 『さなぎ』 とか。
943「ムーン・バギー」
高斎正
短編集 豊田有恒:解説 早川文庫
目次
1.スポーツカー
2.三菱の亡霊
3.謎の山岳コース
4.五郎のサスペンション
5.メルセデスがレースに復帰するとき
6.巨星おちる日
7.ニュルブルクリンクに陽は落ちて
8.ムーン・バギー
9.自動操縦車時代
10.ル・マン一九五五
11.死のレース
12.馬は目ざめる
13.オリムポスの神々
未到の月面最長走行距離記録に
文字どおり生命を賭けて挑戦する孤独な男の姿を描く
タイトル・ストーリイ 「ムーン・バギー」 ほか、
「スポーツカー」 「オリムポスの神々」 など、
こよなく自動車を愛する著者が
余命いくばくもない二十世紀のシンボルである自動車に対して
二一世紀からの郷愁をつづって送る短篇十三篇。
<1986:ハヤカワ文庫解説目録>
私の虎の巻、
【世界のSF文学・総解説】 には、
この短編集の中から、
『ニュルブルクリンクに陽は落ちて』
がピックアップしてありました。
短いあらすじなので、例によって丸写しします。
夕暮れのドイツ、
ニュルブルクリンク・サーキットで、
憑かれたように銀色のメルセデスベンツW一九七を駆って
サーキットレコードに挑戦する主人公ハインツ。
ピットには彼を見守る恋人クララの姿もあった。
だが、本来なら、彼とスピードを競い、
勝利の栄光を奪い合うはずの
世界の強豪マシンの姿はどこにもない。
なぜなら、地上に生き残っているのは、
彼とクララの二人だけなのだから。
宣戦布告も告げず世界中を襲った細菌戦争によって、
人々は死に絶えたのだ。
そのため完成したばかりのW一九七は、
世界の一流マシンに一歩も劣らぬその秘めた性能を
一度も発揮することなく朽ち果てようとしていた。
ハインツはそれが耐えられなかった。
せめて由緒あるこのサーキットで
レコードを更新させてやりたかった。
<安田均:『世界のSF文学・総解説』より>
”マンマシン”
(人と機械の有機的で幸福な結婚)
のカリスマ、高斎正さんの短編の代表作。
で、この作品集にも収められている、
『○○が××に△△する時』
のシリーズが続きます。
◯ホンダがレースに復帰する時
◯ロータリーがインディーに吼える時
◯ニッサンがルマンを制覇する時
◯ランサーがモンテを目指す時
◯トヨタが北米を席捲する時
◯レオーネが荒野を駆ける時
etc.
<余談 1>
インディー500,ル・マン、モンテカルロ――。
こうして見ると、
モンテカルロ、すなわち、
『モナコ・グランプリ』 なんだよなあ。
私の衝撃度と興奮がMAXになったあのグランプリ。
セナが<モナコ・マイスター>の名を
不動にした1992のレース。
アイルトン・セナとナイジェル・マンセルの
壮絶な一騎打ちがいまだに蘇ります。
スピードに劣るセナのマクラーレンが、
ウィリアムズのマンセルのピットインの隙をついて
トップに出たんですが――。
そこから先がまあ、歴史に残る凄い戦いで、
誰もがセナを応援したくなるような展開が続き――。
ああ、オンタイムで中継を見ることが出来て、
ほんとに幸せでした。
(多分)三宅アナの、
「ここはモナコ、絶対に抜けない!」
の絶叫に近い実況が今でも蘇ります。
<余談 2>
高斎正さんの作品に戻ると、
私個人としては、
アメリカのインディに、”日・独・伊” が揃ってしまうという、
『ロータリーがインディーに咆える時』
が一番興味深かったなあ……。
実際、佐藤琢磨選手が優勝しちゃったし。
でもこの辺になると、もはやSFではないような……。
<余談 3>
F-1ついでに。
メルセデスというとベンツ以外に、
”マクラーレン・メルセデス”
という名称がすぐに出てきます。
ホンダのあとフォード、プジョーと来てのメルセデス。
世代ですね。
セナはすでに故人となっていて、
ハッキネンの時代かな。
しかし往年の勢いは感じられず、
フェラーリのシューマッハ、ウィリアムズのヒル、
の後塵を拝していたような気がする……。
それにしても、F-1、
全然見なくなっちゃったなあ……。
944「X電車で行こう」
山野浩一
短編集 諏訪優:解説 早川文庫
目次
1.闇に星々
2.雪の降る時間
3.消えた街
4.赤い貨物列車
5.恐竜
6.列車
7.X電車で行こう
”口に出さなくても考えただけで”
相手のすべてがわかってしまう超能力者ピート 「闇の星々」、
国鉄の待避線にドイツ連邦鉄道の特急
”ラインゴルト” が停車する 「赤い貨物列車」、
驚くべき想像力と鉄道に関する
マニアカルな愛着をえがく傑作 「X電車で行こう」
ほか四篇を収録。
山野浩一の処女短篇集!
<1986:ハヤカワ文庫解説目録>
車の次は電車(列車)と来たもんだ。
田中光二、高斎正、とSF第二世代が続いた後に、
山野浩一も――
と、行きたいところですが、
この作品集は70年代ではなく、65年に上梓されたものです。
筒井さんの 『東海道戦争』 出版と同年。
だから世代的には第一世代にはいっていても
おかしくないのですが……。
山野浩一は昭和一四年生まれ。
処女作以来一貫して、
内的世界の幻想性を探求している。
同時に日本におけるニュー・ウェーブ運動の主唱者として、
精力的な創作・評論活動を続けている。
<新戸正明:『世界のSF文学・総解説』より>
『X電車で行こう』
この表題が、
デューク・エリントンの 『A列車で行こう』
のモジりであることは言うまでもありません。
さて物語は、
”鉄道好き” の主人公が新聞の片隅に掲載された、
小さな記事を見つけるところから始まります。
幽霊列車?
東武鉄道野田線に出現
俺は何よりも 『幽霊列車』 というフレーズが気に入った。
しかし、日本中にこれだけ鉄道があって、
これだけ列車が走っていれば、
一列車ぐらいダイヤ通りに走らないものがあっていいはずだ。
『幽霊列車』 というものが存在すれば、
それは俺が考えていたあらゆる空想を超えた
鉄道の世界を実現するものだ。
<本編から>
やがて 『幽霊列車』 は 『X電車』 と名を改められ、
大々的に報じられることになっていきます。
X電車は鉄道を選ばず、
日本中のレールの上を走ることになる――。
X電車に魅入られた主人公は、
仕事がおろそかになって会社をクビになり、
X電車が現われるであろう場所を探す、
”X電車出現の予想屋”、
といわれるようになってきます。
その彼が立てた予想のなかには、
私の馴染み深い鉄道も含まれていました。
曰く、
天王寺ー梅田 (地下鉄一号線)
折尾ー博多 (鹿児島本線)
福岡ー大牟田 (西鉄本線)
ここにもX電車は通ったのでしょうか?
<余談 その1>
いまだに間違える、
デューク・エリントンの 『A列車で行こう』
と、
グレン・ミラーの 『イン・ザ・ムード』。
ジャズ愛好家からしたら、
「アホちゃうか」
と言われそうだけど。
<余談 その2>
『幽霊列車』
って言うと、
世代的に赤川次郎さんの名が勝手に浮かんできます。
土曜ワイド劇場で映像化されたことも
記憶の劣化に歯止めをかけているようです。
田中邦衛さんと浅茅陽子さんのコンビ。
最後、浅茅さんが、パッと裸になって――。
こんなシーンが記憶を塗り固めるんでしょうね。
<余談 その3>
戦後すぐにおきた ”国鉄三大ミステリー” のうち、
<三鷹事件>が重なるかな。
”無人列車の暴走” っていうやつ。
<余談 その4>
ついでに
<ゲゲゲの鬼太郎>に、
『まぼろしの汽車』 ってのもあった。
時間を逆走する、親の(子に対する)愛情が走らせる汽車。
目玉の親父さんが、吸血鬼と化した鬼太郎を救う。
<余談 その5>
中山千夏さんに
『とまらない汽車』 ってのがあった。
人生幸朗師匠のネタに、
”止まらない汽車に、どっから乗るんじゃい!”
っていうボヤキがあったっけ。