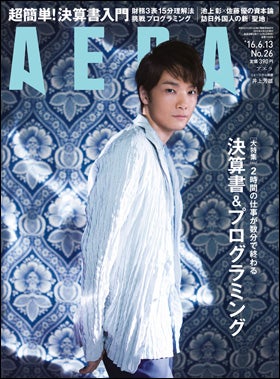子どももママも未来に希望が持てる家庭療育
おうち療育アドバイザー浜田悦子です。
こんにちは^^
先月Facebookライブで
数のお勉強についてお話ししました。
一緒にライブをしている
さおりさんが小学1年生の長男さんに
早速わたしのアドバイスを実践して
レポを書いてくださいました^^
結論からいうと、
「お子さんのつまずきが分かった」
ということなのですが、
これがとっても大切です^^
シンプルなことですが、
つまずきが分かれば
対処の仕方が分かるんですよね!
でも、ついついわたしたちは
お子さんのつまずきに対して
同じレベルの問題を与えてしまいます。
こんな時、例えばわたしには、
「やればできるはず!」
という気持ちが隠れているのかもしれません。
排水溝が詰まったら
そのつまりを取り除かないと解決しないって
分かっていても、
子どものことになると
どうしても自分の期待や願望で
押し通してしまいます(汗)
でも、安心してくださいね!
つまりの原因がわかったら、解決できますから^^
さおりさんのブログには、
「数は理解しているが、
数字を覚えられていない。
5までは覚えているけど 7.8.9がごちゃまぜ
長男にはほとんど同じように見えているみたい。」
と、書かれていました。
その様子が動画に添付されているんですが
動画を見て、気付いたことがありました。
さおりさんは
長男さんが間違えた数字を聞き直したり
違う数字を出して質問したりしていたのですが、
実はあまりオススメできない対応なんです。
分からない数字ばかりだと混乱するので
ひとつずつ教えていく必要があります。
例えば、「7」が分からない時には、
(7を指さしたり、見せたりして)
ママ 「これは何?」「な・・(ヒントを出す)」
子ども「8」
ママ 「7だね」
ママ 「これは何?」「な・・(ヒントを出す)」
子ども「8」
ママ 「7だね」
(7を指さしたり、見せたりして)
ママ 「これは何?」「な・・(ヒントを出す)」
子ども「7」
ママ 「うん、7だね」
(7を指さしたり、見せたりして)
ママ 「これは何?」「な・・(ヒントを出す)」
子ども「7」
ママ 「うん、7だね」
(7を指さしたり、見せたりして)
ママ 「これは何?」
子ども「7」
ママ 「うん、7だね」
こんな風に。
お子さんが間違えた数字を言う前に
最初の一文字を言ってヒントを出し
正解に導いていきます。
もし、間に合わずに間違ってしまったら
一言で訂正。
ヒントを出して正解率を上げ、
徐々にヒントを無くしていきます。
最後は必ず正解で終わらせます。
ただ、これだとつまらなくなってしまう
お子さんもいるので、
分かる数字(絶対間違えない数字)と合わせて
やっていく方がやる気がでるお子さんもいます。
そして、「7」が定着してきたら
次は「8」というように、
ひとつずつ教えていくと
お子さんの理解につながっていきますよ^^
これは、数に限らず色んな場面でも
応用できます。
例えば、挨拶ができないお子さんには、
「おは(よう)」「さよ(うなら)」
とヒントを出すことで、挨拶に結びつけていきます。
(専門用語ではプロンプトといいます)
こんなにヒントを出したら
ひとりで考えられなくなるんじゃない?
と感じちゃうママもいらっしゃるかもしれません。
でも、間違うことは失敗体験になるんです。
発達障害やグレーゾーンのお子さんは
「正解が分からない」「自分では導きだせない」
ということがたくさnあります。
まずはヒントを出して成功体験を積み重ねていき
そして、成功率が上がってきたら
少しずつヒントを減らしていけば大丈夫。
ぜひ、試してみてくださいね^^
さおりさんのブログの動画を見ると
イメージがわくと思います。
さおりさんの動画で
ぜひ練習してみてくださいね!
動画はこちら
**掲載していただきました!!**
(ひよこクラブ:2018年3月号)
神奈川、横浜、川崎、東京、千葉、埼玉、
茨城、栃木、群馬、23区、青葉区、静岡、
浜松、山梨、仙台、大阪、神戸、京都、
名古屋、石川、和歌山、岡山、福岡、
全国からご相談いただいております。
発達障害、グレーゾーン、発達の遅れ、
発達遅滞、知的障害、療育、家庭療育、
癇癪、パニック、こだわり、きょうだい喧嘩、
他害、暴言、宿題の悩み、身支度、着替え、
登園拒否、登校拒否、不登校、友達関係、
おまかせください。
(AERA:2016年6月号)