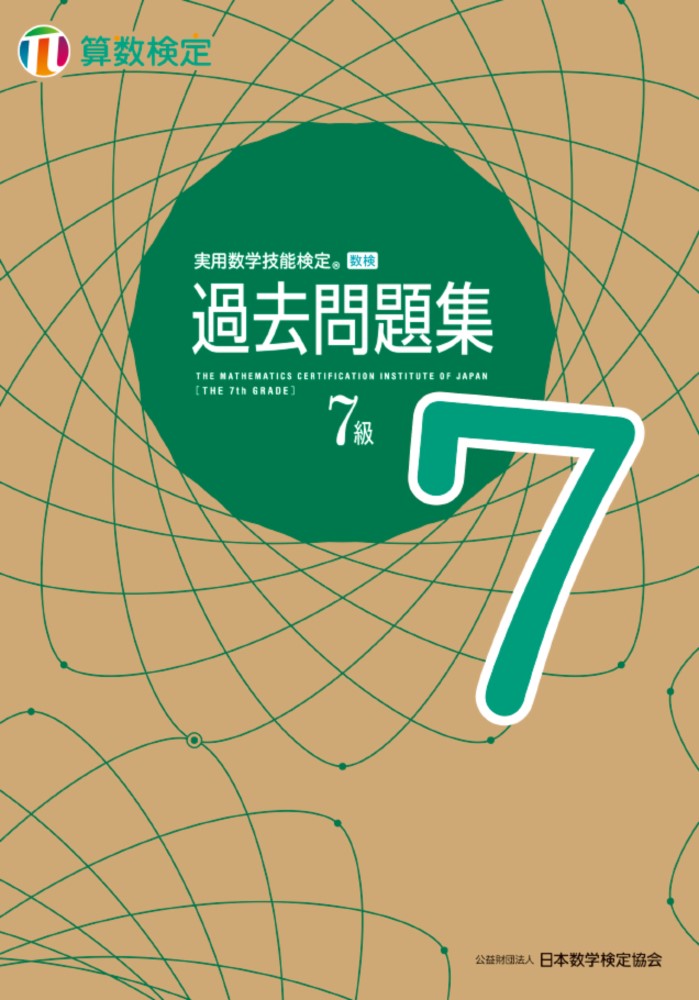前回からの続き、、、
- 日程
3/1 で申し込み完了
もう引き返せません![]()
模試自体は、すでに数回経験済なので、本人も特に嫌がることはなかったので(本音は面倒だとは思っていそうですが、、、![]() )受験を決定
)受験を決定
- 試験範囲
幸いにも(?)図形は、ひねった問題はほぼなく、定義や決まり事さえできていればいけそう、かなと思います
- 合格点数と対策
合格点数は全問題の70%程度とのこと
問題数は30問なので、21問正解はマストでしょう
22問以上が望ましく、24問取れていれば、まず合格できそうですが、最後2問は難しく実際は28問満点で考えておかないと厳しいかなと![]()
ひとまず28問中22問以上正解を目指します
最初に12問計算問題があるので、ここは全問正解を目指したい
さらに見開き右には、概数の1行問題等があり、そこを含めるとだいたい17問
できればここまで満点を取ってくれるとだいぶ楽になります![]() というか、ここまで満点取れないと五分五分以下の大変厳しい戦いになってしまいそう
というか、ここまで満点取れないと五分五分以下の大変厳しい戦いになってしまいそう
最終問題を抜いた28問のうち、前半17問を終えて残り11問中、5問正解すれば合格、という目論見。。
ただ計算含め前半を全問正解というのを前提にしているのがだいぶ皮算用とも言えますが![]()
使用している問題集は主にこちら
こちら、9級から持っていますが、全6回分はいっていて、非常に使いやすいです![]()
ただ逆に、ここから大きく逸脱した問題が出ると、本番に弱いかも![]()
6回分は入ってますが、それしか入っていない、という見方もあります
演習量の少なさは、6級、8級からも類似問題をピックアップ予定でカバーします
あとはたぶお式プリントでも該当部位を勉強しています
主にブロック2-3です
割合以外にも円周、面積等々もプリントがあるので、実はたぶお式プリントで大方の範囲をカバーできそうな気がしています![]()
たぶお式は、幼児~低学年でも理解できるくらい簡潔にまとまっているので、使いやすさを改めて実感、、、
3月以降落ち着いたら、たぶお式からコツコツやるかな、、、
- 具体的な学習内容
試験まであまり時間がないため、必然的に準備していくところはできるだけ全問正解を目指す形になります
とにかく計算含めて既習単元は満点目指してきっちりしあげていかないといけません、、、
ざっと見渡してみて、ここから新たに習得したい未習単元は、下記の通り
・割合
・円と半円の周りに長さ
・正〇角形の角度など
・体積
・台形、ひし形など図形関連
・平均
上記のうち、円と半円~、体積なんかはスムーズにいけば習得にそこまで時間はかからない見込みですが、今の時点での鬼門はやはり割合でしょうね
ひとまず割合に取り掛かっていますが、ちょっとやってみたところ、割合の肝というか本体は、小数分数の変換、%、そして歩合を覚えるところがスタートラインなのかなと思いました
その後多少覚えたかな、と思って文章題に取り掛かってみましたが、さっぱり![]()
そんなにスムーズには行かないですね、、(さくっと理解出来たら苦労しません![]()
抽象的な分野なので、もしかすると本質的な意味が分かっていないのかもしれません、、、(そうであれば問題が解けないことになってしまいます
合わせて週末に子供が体調崩して思うように学習が進まず、、、体力(だけではいけませんが)がないとどうしようもないですね
改めて低学年では、座学<<<体力づくりかな、とも![]()
でもまだ慌てる時間ではありません、コツコツ進めます
あまりできないのに焦って無理に取り組ませると、余計に苦手意識が増してしまいそうなので、とりあえず歩合、%などの基礎の基礎を徹底してみます
→2週間くらいやっても手ごたえがないようであればまた考えます![]()
2月に入ったら図形関係も開始予定としています
次回も続く?