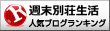(八ヶ岳南麓小淵沢の樹木葬霊園「八ヶ岳フラワージュ」同社HPより)
小淵沢にある樹木葬霊園に資料請求したところ、同霊園の運営主体である「松戸屋」から各種パンフレットがどっさりと送られてきた。紛らわしい屋号だが「大戸屋」とも「松屋」とも関係はない模様。
(墓じまいのへ関心は高い)
同社の「樹木葬ガイドブック」によると、樹木葬の一般的なデメリットとして「後で気が変わっても遺骨の返還が難しいこと」が挙げられている。その点同社の樹木葬霊園は個室型とか、ペット同伴型とか、各種ニーズに応えられます、とのこと。
それにしても何故人はここまで遺骨に拘るのだろう。戦没者の遺骨収集は戦後76年を経た今でも世界各地で行なわれている。
この「遺骨信仰」とでもいうべきものはどうやら仏教国固有のもので、釈迦の遺骨を貴ぶ「仏舎利信仰」がベースとなっているようだ。もっとも釈迦の涅槃の直後にはその遺骨の争奪戦があったというから、仏教が広まる前からインドの地にはなんらかの遺骨信仰があったのだろう。
一方キリスト教国、イスラム教国では「魂の復活」との関係で土葬が一般的らしい。特にイスラムは
100%土葬で、日本に永住するムスリムは墓地の確保に大層苦労しているとのこと。
また米国では墓地のスペース確保が次第に難しくなってきていて、古い墓地を壊して更地にすることも珍しくないという。そんなところに「ポルターガイスト」のような名画が産まれる素地があるわけだ。
(1982米製作・脚本S・スピルバーグ
カリフォルニア郊外の新居に引っ越した一家を超常現象が襲う そしてある日娘のキャロルアンに恐ろ
しいことが 「ゾンビ」、「シャイニング」、「エルム街の悪夢」と並ぶホラーの傑作)
そんなわけで彼の地でも火葬が一般的になりつつあるらしいが、元々遺骨信仰のようなものは皆無だから遺族が遺灰(高熱処理で灰にする)を引き取らないことが普通で、引き取る場合でもシェーカーサイズの小さな容器に入れたものを故人の思い出として暖炉の上なんかに置いておくことが多いようである。そういえばタイトルは忘れたが、なんかの映画でシャンパンを抜いたところコルクが見事骨壺に当たって部屋中灰神楽、というシーンがあったっけ。
信仰心というものが微塵もない私にとっても、米国人同様遺骨はただの産廃物である。
出来うれば米国のように遺骨を受け取らなければ墓地で悩むこともないのだが、何故だか分からないが我が国では遺骨を一片たりとも受け取らない、というのは火葬場のルールで認められていない。特に関東では全部持ち帰り(?)が原則のようだ。
となると、一番手っ取り早いのは庭に散骨すること。
この行為自体は「節度をもって」やる限りは法律違反ではない(1991年法務省見解)し、骨粉はリン酸分豊富ないい肥料だから一石二鳥である。
ただし骨片が大きすぎると(2ミリ以下のパウダーにすればOKらしいがこの辺りの有権解釈は存在しない)刑法190条(死体遺棄)違反となるおそれがあり、土中に埋めたり墓標を建てると埋葬法違反に問われることになりかねない。そんなこんなで、信心深いお隣さんに見咎められて大騒ぎされると「節度」の問題が浮上してくることになるわけだ。
結局のところ散骨よりは1回のみの出費で済む樹木葬の方がマシかもしれない。
一方「墓じまい」であるが、大戸屋の「墓じまいガイドブック」によると、
・ 既存遺骨の移転費用(永代供養塔とか樹木葬とかに改葬)
・ 墓所の現状復帰費用
・ 離檀料(手切れ金)
が発生することになる。上記二つは相場がかなりはっきりしているが、離檀料は例によって曖昧模糊としていて、どうやら数十万円は覚悟しなくてはいけないらしい。
う~む。「進退窮まる」とはこのことか。
長い間に培われたシガラミや利権でがんじがらめ、
何かを変えようとすると膨大な労力とコストがかかる、
こんな私の状況はまさに我が国が抱える困難の縮図である。そういえば河野太郎行革担当大臣は最近何をやってるのだろう。
そうこうしていると、突然北の国から朗報があった。
長男が4月に転勤することになり、それを機に結婚するというのである。今まで想像したこともなかったが、ことによると孫の顔も見れるのかも、だ。
そういうことなら墓をどうするかは私がジタバタするのでなく、次世代、つまり息子や孫の世代に委ねてもいいかもしれない。
そんなわけで「墓じまい問題」はとりあえずこれにて一件落着。私自身は生を全うするための終の棲家に集中することにした。