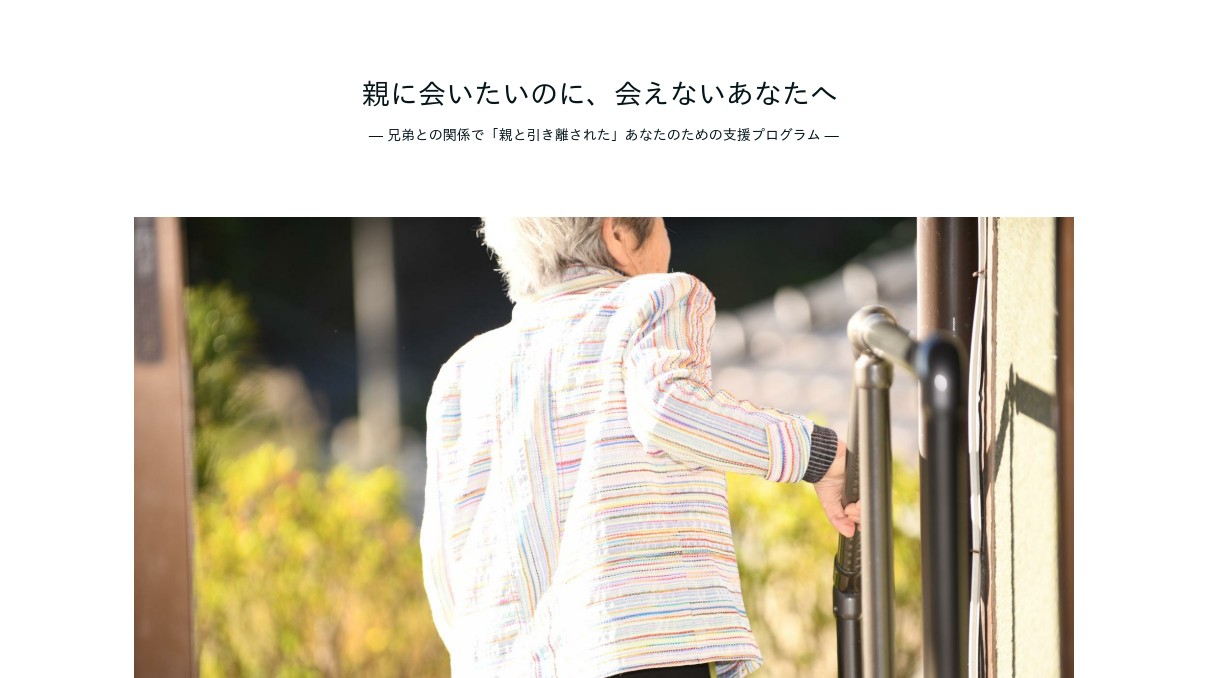公認会計士・税理士、高齢親の囲い込み解消コンサルタント 白岩俊正/静岡市・オンラインです。
無料オンライン相談 受付中
「お母さんは私がいちばん面倒見てきたんだから、他の兄弟に口出しされたくないの」
そう言って高齢の親を自宅で介護するきょうだい。周囲は「献身的で立派だ」と褒め称えるかもしれません。でも――その介護、本当に「親のため」になっていますか?
高齢親の“囲い込み”という現象が、家庭の中で静かに進行しています。善意と支配は、ときに紙一重。この記事では、自宅介護の現場で見えにくい「囲い込み」の境界線を、一緒に考えていきましょう。
1. 「自宅介護=正義」とは限らない
多くの人は「親を自宅で介護している=愛情深くて立派」と感じます。もちろん、そうした方も大勢います。
でも、その裏で問題になっているのが「囲い込み」です。
囲い込みとは、一人の子が親を自宅や特定の施設に囲い込むように住まわせ、他の家族との交流や面会を制限することを指します。
たとえば──
- 電話を代わらず「親は寝てるから」と毎回断る
- 「家の外に出すと混乱する」と、他のきょうだいの訪問を拒否する
- 親の意向を確認せず、「親は会いたがっていない」と代弁する
このような対応が続くと、親の「会いたい」「外に出たい」という意思が封じられ、本人が社会的に孤立する結果になります。
2. 善意から始まり、支配に変わるとき
最初は善意だった。そういうケースも少なくありません。
しかし、自宅介護は体力的にも精神的にも負担が大きく、「自分がこんなに頑張ってるのに」という気持ちが強くなると、
他のきょうだいの関与を「邪魔」と感じるようになります。
やがて──
- 親の通帳を一人で管理し
- ケアマネや施設職員とも自分だけがやり取りし
- 面会や情報共有の主導権をすべて握る
という「実質的な支配」が生まれます。
この段階になると、介護は「親のため」ではなく「自分の正当性を守るため」になりがちです。
3. 判断力の低下が「囲い込み」を助長する
特に問題が深刻化しやすいのは、親が認知症などで判断力を失い始めたときです。
親自身が「他のきょうだいに会いたい」と思っていても、
- その意思をうまく伝えられない
- 伝えても「そんなこと言ってないでしょ」と否定される
- 会いたいと言うと怒られるので言わなくなる
といった状況が生まれ、親が孤立していきます。
その結果、介護している子どもが「親の代弁者」としてふるまう構造が固定化され、
他の家族が関与しづらくなるのです。
4. 「親の意思」は本当に尊重されているか?
囲い込みが問題なのは、「親の意思」が実際には無視されている可能性があることです。
介護者の
- 「親は喜んでいる」
- 「混乱させたくない」
- 「外に出すのはかわいそう」
という“代弁”が、本当に親の意志を反映しているのか?
それを確認する手段が、他のきょうだいや第三者にはないことが問題なのです。
5. 解決の糸口:孤立を防ぐ「ゆるやかな関与」
完全に任せるでもなく、過度に介入するでもなく。
「ゆるやかな関与」が囲い込みを防ぐカギになります。
たとえば──
- 定期的にLINEや電話で親の様子を確認する
- 施設やケアマネに連絡を取り、情報共有を依頼する
- 「会えない理由」を記録に残す(訪問拒否の有無など)
また、本人の意思を確かめるために、認知症の程度に応じた面会機会をつくることも大切です。
結びに:
親を思う気持ちは、誰にとっても本物です。
でも、その「思い」が他の家族や親本人の意思を抑え込むとき、
そこには「支配」と「正義の暴走」が潜んでいるかもしれません。
「親は家族みんなのもの」
この原点に立ち返ることで、囲い込みではない、本当の介護と支え合いが始まります。
ブログのご紹介
ブログ主宰 しらいわ は以下のブログも作成しています。併せてご覧ください。
1. EQモンスター対策室 ~感情的な人に振り回されている方向け~
2. あなたのメンタルを守りたい ~心が少し軽くなるメンタルケアの情報を発信中~
3. インナーチャイルド解放コーチ しらいわとしまさ 幼少期の心の傷が未処理のため大人になっても生きづらさを感じる方へ
4. 感情の地図 〜EQナビゲーターが届ける“心の航海術”~感情と向き合う「心の航海術」を発信中
5. 高齢親の囲い込み 解放アドバイザー ~介護が必要になった高齢親が自分以外のきょうだいに囲い込まれて会えなくなった方へ~
6. 女性起業家×アドラー心理学(準備中)