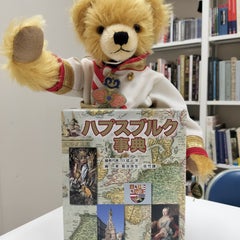クンツェ&リーヴァイが手がけるウィーン・ミュージカル。そこには必ず何かしらの「悪役」が登場し、主人公に立ちはだかります。その定番の悪役として、実はある職業の人物が多いことにお気づきでしょうか?
神に仕える「聖職者」です。
「マリー・アントワネット」のロアン大司教、「モーツァルト!」のコロレド大司教、「レディ・ベス」のガーディナー主教。歴史を題材にしたウィーン・ミュージカルには、いずれも悪者の聖職者の存在が欠かせないようです。これらの実在した聖職者が本当に「悪者」であったかどうかは別として、いずれせよ彼らはみな歴史上に実在しました。
ロアン大司教(「マリー・アントワネット」)
コロレド大司教(「モーツァルト!」)
ガーディナー主教・大法官(「レディ・ベス」)
「エリザベート」に登場する悪役たち
まず、黄泉の帝王トートは「悪役」なのでしょうか?皇妃にまとわりつくストーカーのような死神なわけですから、「悪役」といえば「悪役」です。惚れた相手の娘や息子を死に追いやるあたりは、完全に「悪役」の所業です(幼い長女ゾフィーを殺めるシーンは、宝塚版にはなく東宝版に限られます)。ところが、彼を「悪役」ではなく、エリザベートに恋する「主役」として見ることができてしまうのも、この作品の魅力の一つです(宝塚版はまさにその色を濃く出しています)。
では、皇帝の母でありエリザベートの姑になるゾフィーはどうでしょう?彼女を「悪役」と捉える方は多いかもしれません。たしかに息子である皇帝を操ったり、嫁いびりをしたりするあたりは相当悪く見えます。ただ、それもすべて王家を守るため心を鬼にして!と深読みすると、彼女はもしかしたら「悪役」ではないのかもしれません。だらしない男だらけの宮廷で、ひとり気を吐き懸命に帝国を守ろうと奮闘する「鉄の女」?(「鉄の女」といえばイギリスの元首相マーガレット・サッチャー。彼女も実は在任中に多くの人に嫌われた女性でした)。東宝版の第2幕に追加された「ゾフィーの死」で描かれる切ない最期と心情告白に触れると、ゾフィーを「悪役」呼ばわりするのに気が引けてしまうのは私だけでしょうか。
進行役であるルッキーニは「悪役」でしょうか?彼は、エリザベートをおとしめ民衆を焚きつけます(「ミルク」や「キッチュ」のシーンなど)。その意味でも、作品のなかでは「悪役」の立ち位置といってもいいでしょう。史実からしても、彼はエリザベートを刺殺する犯罪者でありテロリストです。ただし、このミュージカルをエリザベートとトートの純愛物語と捉えると、ルッキーニは「愛の橋渡し役」「愛のキューピット」という逆の位置づけになってしまうのが面白いところです。
というわけで、ミュージカル「エリザベート」の悪役をめぐる思索は、どうやら着地点がなかなか見つかりそうもありません。見る視点によって「悪役」が誰なのか変わってしまうからです。もしかしたら、主人公のエリザベート自身、ハプスブルク帝国の歴史物語のなかでは「悪女」だったのかもしれませんし・・・・。実際に、彼女は帝国にあらがうハンガリーの肩を持ったり、皇妃の務めを放棄したりと、王家のことよりも己の生き方を優先させました。歴史に目を向けるときには、誰かが作った「善」「悪」のラベルや先入観にとらわれることなく、まずは自分で自由に考えてみることが大事なのかもしれませんね。
ところで、冒頭の話に戻りますが、ラウシャーという聖職者だけは、エンディングまで結局名誉が回復されることなく、ある種「悪い」まま人物像が劇中で完結しています。彼はいったい何者なのでしょうか?
ラウシャー大司教とは?
ラウシャー大司教は、ミュージカルの第1幕でカトリック教権派の筆頭として登場します。宮廷を仕切る大公妃ゾフィーと組み、自由主義を弾圧する「悪役」のイメージが彼にはつきまといます。さらに後半の第2幕では、保守派の復権をめざす陰謀の輪の中に彼の姿を再び見ることになります。妻の美貌のとりこになった皇帝を皇妃から引き離すため、保守派は皇帝に娼婦をあてがい、夫婦関係を引き裂こうとします。その際、娼婦の「宅配」に熟知した淫らで堕落した聖職者としてラウシャーはずいぶん悪く描かれます。もちろん、この陰謀はフィクションであり、フランツ・ヨーゼフ1世が娼婦の「宅配」を取った事実は史料から確認することはできません(愛人はいましたが)。
とはいえ、この実在のラウシャー大司教は、皇帝とエリザベートの結婚式において中心的な役割を担った人物であることをご存知でしょうか?彼こそが、1854年4月24日、アウグスティーナ教会での挙式に居並ぶ何十名もの聖職者の中心に立ち、夫婦間の指輪の交換や神前の宣誓を執り行ったオーストリア第一の大物聖職者なのです!
では、当時の新聞記事をもとに、ラウシャーという人物の経歴を整理してみましょう(『オーストリア絵入り新聞』1853年8月29日付)。
ラウシャー(Joseph Othmar Ritter von Rauscher)は、1797年、功績のある政府高官の息子としてウィーンで生まれました。法学と神学を学び、1823年に司祭、その後まもなく主任司祭となった彼は、敬虔かつ穏やかで気高い聖職者として人々の信望を集めたそうです。やがてザルツブルクで教会史と教会法の教授職に就き、1837年には帝国オリエント・アカデミーの所長と大修道院長に就任します。1843年に司教となったラウシャーは、1853年4月5日、功績が認められてウィーン大司教に任命されることになりました。1853年8月15日、聖母マリア被昇天の日、ウィーンのシュテファン大聖堂で大司教の叙階式が催され、参列した多くの信者の前でラウシャーは大司教としてお披露目されました。1716年以来、彼は第7代目のウィーン大司教となるわけですが、この位に就いた初めてのウィーン出身者でもあったそうです。
この「大司教」の肩書で、彼はミュージカル「エリザベート」に登場するわけですが、最初の登場シーンのとき、正確にはまだ「大司教」ではありませんでした。どういうことでしょうか?ミュージカルでは、皇帝がバート・イシュルのお見合いに出発する直前のシーンでラウシャーは「大司教」として登場し、カトリックに歯向かう過激分子の弾圧を皇帝に進言します。しかし実際は、このときまだ正式には大司教ではありません。その後、皇帝がバート・イシュルへ向かい、エリザベートと運命の出会いを果たしたころ、彼はウィーンで叙階式を迎え、晴れて大司教の職に就きました。