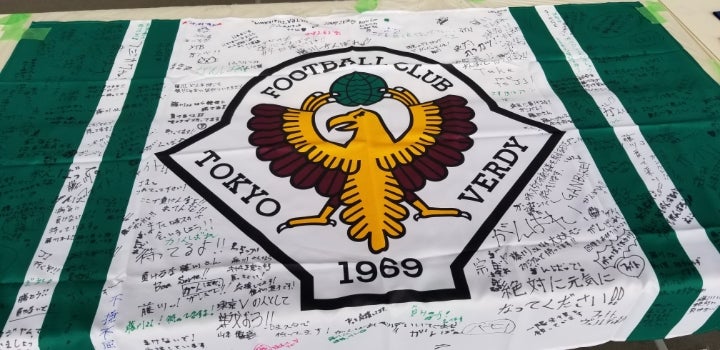ヴェルディの星
東京ヴェルディ1969応援ブログ 懐かしモノ、音楽、クルマ・モタスポも
プロフィール
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
ブログ内検索
2014-06-05 11:06:08
日産ル・マン参戦の歴史・其の五 「三年目の転換」
テーマ:クルマ・モータースポーツ18年ぶりにレース専用エンジンを投入しながら、ニスモ社長の難波からして「はちゃめちゃな負け方だった」と言わしめた1987年の日産。1988年、日産は捲土重来を期したニューマシン&ニューエンジンを搭載します。
まずはっきり言って失敗作だった日産久々のレース専用エンジンVEJ30。この大改良を任されたスポーツエンジン開発室長に就いた林義正は、「あれもこれも」と改良していくうちに、ほとんど新型のエンジンを作り上げてしまいました。当時の雑誌ではサラリーマンらしく「VEJ30の素性良かったから改良しやすかった」と答えてましたが、後に日産を辞めてフリーになった時に「どうしようもないクソエンジンだった」と暴露してますw この新エンジンはVRH30と名付けられました。しかし林の本命とするエンジンとはこれとは別に開発が進められていました。これは後の項で。
このVRH30型エンジンを積むマシンは純粋の新車でなく、前年のR87E(マーチエンジニアリング製)を大改造したR88Cとなります。シャシーのホイールベースを延長するなど手を加え、日産の風洞を利用して作った日産製ニューボディを纏いました。チームの体制も変わり、前年までのホシノインパル、ハセミモータースポーツに貸出してエントリーすると言う形から、ニスモが2台ともメンテナンスしエントリーすると言うフルワークス体制となったのです。星野も長谷見もヘルメットだけ持って来れば良いと。
デビュー戦となったJSPC開幕戦富士500kmでは、直前に降った大雪のためテストが十分にできないまま臨み、長谷見車が電気系トラブルで、星野車がガス欠(規定のガソリン量で完走できる燃費にまで仕上げることができていなかった)で共にリタイヤとなります。
2戦目鈴鹿500km、3戦目富士1000kmでは2台揃って完走。この時の日産はJSPC前半戦を完全に「ル・マンのテストの場」と割り切っていました。
そして迎えた3年目のル・マン。この年はメルセデスワークスが復活し、ジャガー、ポルシェ、メルセデスの3大ワークスの激突で話題を呼びました。これに日本の3ワークス(トヨタ、日産、マツダ)が加わり6ワークス。まさにバブルへ向かう勢いの年でした。ただし日本車が欧州ワークス勢と真っ向から戦えるようにまだ少し時間が必要でした。欧州3ワークスの優勝争いとは別に「日本車クラス」の勝利を目指すと。
残念ながら予選でのタイヤトラブルでメルセデスは欠場してしまうのですが、この年はポルシェとジャガーの歴史に残る大バトルが演じられます。
日産はワークスのニスモから2台のR88C、前年参加したサテライトチームのチーム・ルマンもこの年は2台(R88V、R86V)持ち込み、日産は総勢4台となります。マツダ3台、トヨタ2台と日本車は過去最多の9台の参加となります。
日産R88C
この年日産は長谷見が不参加で、星野/和田/鈴木亜久里の日本人組23号車と外国人組32号車となります。この年の日産の目標は「4800km走破する」こと。順位に関係無く自分たちのペースで走りデータを集め、翌年以降優勝争いのための準備の年とすると。
結果的には、23号者は序盤コレクタータンクにひびが入ると言うトラブルで大きく遅れるもその後は順調に走るが、20時間目でリタイヤ、32号車はマツダ、トヨタと「日本車クラス」を争うも終盤ミッショントラブルで遅れ、結局14位で完走。12位のトヨタに「日本車クラス」優勝争いに敗れます。しかしこの年の日産にはどうでもいいこと。1台が目標には届かないもの完走し、もう1台も20時間走った。これが翌年につながると。この頃既に翌年のニューマシンの青写真は出来ていました。
この年のル・マンはポルシェとジャガーの歴史的バトルで394周も走りながら同一周回と言うすごいレース。この大バトルを制したのは37年ぶりの優勝となるジャガーでした。ドーバー海峡から渡って来たジャガーサポーターは大きな声で「GOD SAVE THE QUEEN」を歌います。まるでサッカー場のように。この大バトルに翌年は加われる自信を日産関係者は持っていたはずです。
帰国後のJSPCでは日産は速さも見せるようになります。実は帰国後初レースとなる富士500マイルには「ほとんど新型」の3.4リットルにスケールアップしたVRH30Aをニスモは持ち込んだのですが、上司にあれこれ言われないよう、林はその新エンジンをマスコミにも言わず投入したのでした。当時の日産らしい閉鎖的な面が…。これも林が日産退社後暴露しています。
富士500マイルでは予選ポールポジション獲得、決勝でも2年ぶりとなる3位表彰台をゲットします。続く鈴鹿1000kmでも3位表彰台。最終戦WEC-JAPANでもおおいに期待されましたが、予選は天候に翻弄され2位、決勝ではマイナートラブルで9位に終わります。ノートラブルで行けばジャガー、ポルシェ、メルセデスの欧州ワークス勢相手に5,6位くらいは狙えたのだが…。
このレースから日産/ニスモ陣営は、当時F1では普及していたテレメトリーシステムを導入しています。マシンから通信で送られてくる情報をピットで瞬時に解析すると言うもの。日産もいよいよ「本気」になって来たのでした。結果的には3位2回でしたが、この年の日産は前年の「はちゃめちゃ」な負け方からすると明らかに進歩していました。そして翌年投入されるR89Cは、日産が本気でル・マンを戦うためのマシンとなるのです。
日産が、いや日本車が初めてル・マンでトップ争いをすることになるR89C、次回はこのマシンを投入する日産4年目のル・マンについて語ります。ご期待ください。
(文中敬称略)