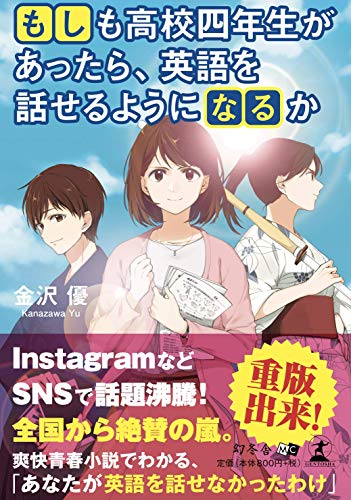【コトバンク】大和言葉(読み)やまとことば
- 漢語や外来語が入る前から日本語にあった単語をさす。 「和語」 (古くは「倭語」) ともいう。 狭義の国語。 日本語の基礎語彙の圧倒的多数がこれで,単語の音形は短く,「手」「雨」などのように1~2音節から成り立っているものが多い。
・・・
日本語の場合、昔から存在した「和語/ひらがな言葉」がその基本ロジックを形成する一方、途中から輸入された「漢字」が語彙を豊富にし、複雑で高度な内容を表せるようにしています。
同様に、英語の場合は、「アングロサクソン語(=話し言葉)」がその基本ロジックを形成する一方、「ラテン語/フランス語(書き言葉)」が語彙を豊富にし、複雑で高度な内容を表せるようにしています。
すなわち、日本語も英語も「混血言語」なのです。
しかるに、現行英文法は「ラテン語/フランス語」をベースに造られてしまっています。この「齟齬」が存在するために、現行英文法を学んでも(私たちのようなノンネイティブは)一向に「日常語/口語英語」を駆使できるようにならない、という訳なのです。
上記に関する歴史的経緯などについては、VSOP英語研究所を主宰している西巻尚樹氏が以下の記事の中でとても興味深いまとめと考察をされています。ご関心のある方はぜひ一度ご一読ください!
■英語は「漢字カナ混じり文」