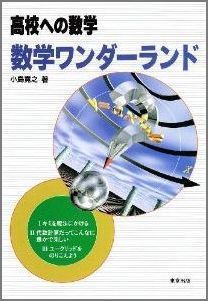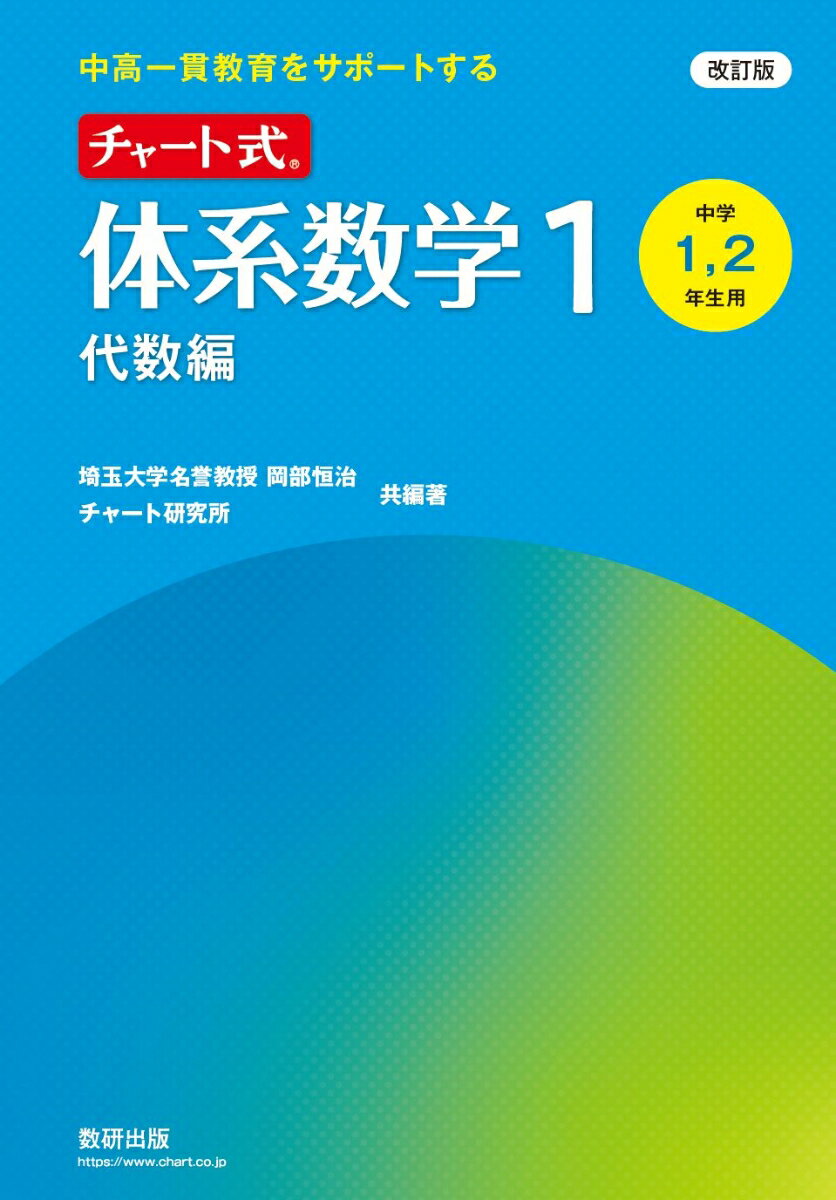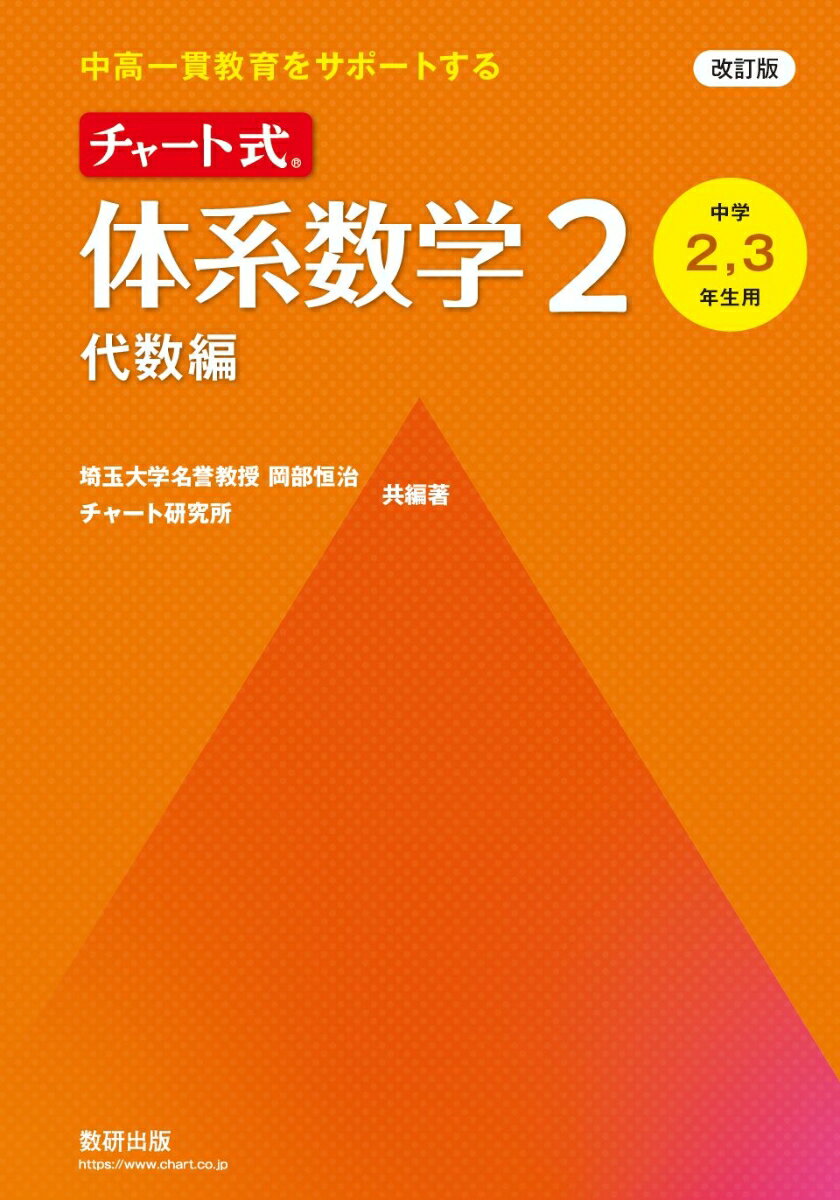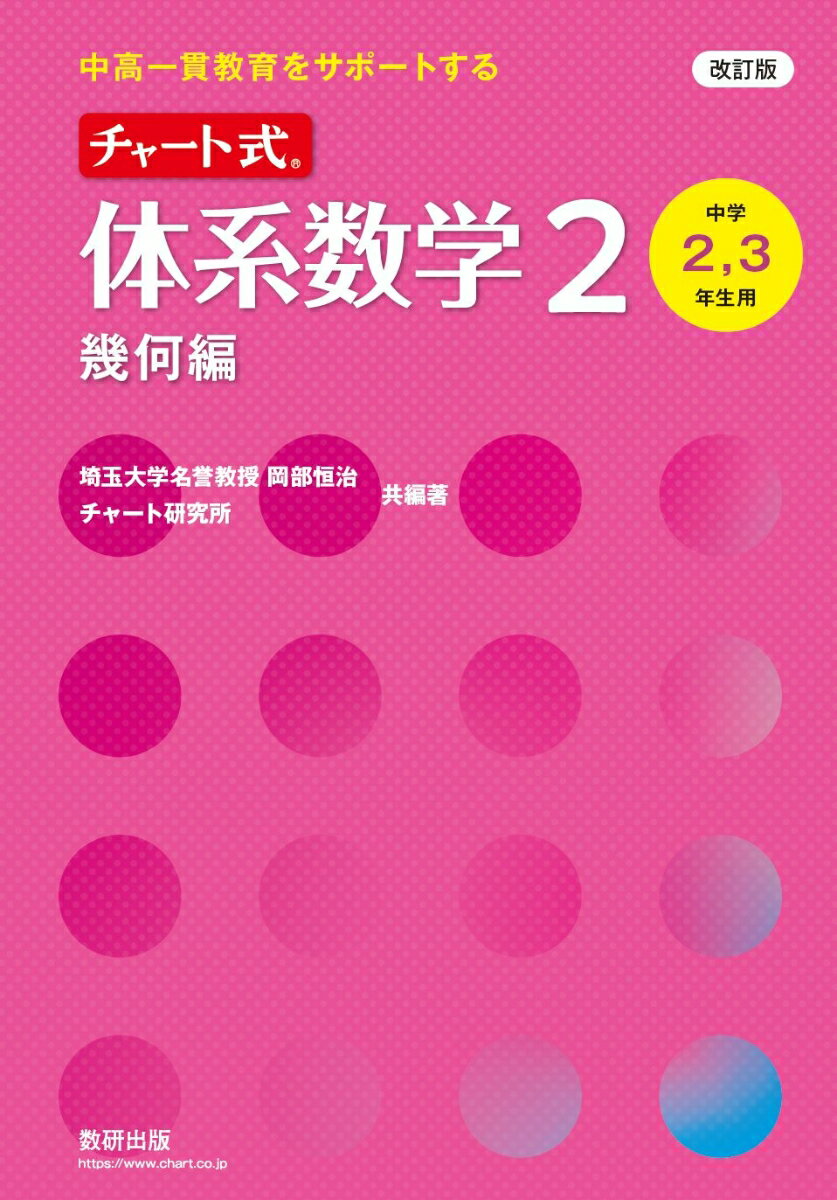数学の中学準備講座の授業の内容を紹介します。
数学の中学準備講座の授業から(001) | 中学受験算数プロ家庭教師
(3x-2y)(x+3y)を展開しなさい。
展開公式がありますが、公式を当てはめて解くのではありません。
最初は、面積図の利用と分配法則の利用を確認します。
面積図の利用
分配法則の利用
与式
=3x(x+3y)-2y(x+3y)
=3x2+9xy-2xy--6y2
(前半のカッコは3xを分配しても係数の比率が変わらないこと、後半のカッコは-2yを分配しても係数の比率が変わらないことと符号の関係(同符号か異符号かということ)は変わらないことの確認)
=3x2+7xy-6y2
実際には、次のように行います。
① 3x2
② +9xyと-2xyで+7xy
③ -6y2
(実際には、計算できるところを頭の中でキープして結果だけ書くのがポイントです。)
さらに、応用的な展開の仕方も学習します。
前の( )内も後ろの( )内も1次の項のみだから、計算結果は2次の項のみとなり、x2とxyとy2が出てくることがわかります。
この係数を決定するだけですが、x2が出てくるのは、両方の( )で文字xを採用するときで、係数は(3×1=)3、xyが出てくるのは、一方の( )で文字xを、もう一方の( )で文字yを採用するときだから、係数は(3×3と(-2)×1=)7、y2が出てくるのは、両方の( )で文字yを採用するときで、係数は((-2)×3=)-6となります。
(x-2y)3を展開しなさい。
一応高校の範囲ですが、中学生でも普通に解けます。
私立の中高一貫校であれば、中2の途中から高校数学に進むところもありますからね。
高校受験をしなくて済むメリットの1つに、意味のない中高数学の垣根を取っ払って学習できることがあります。
私が数学と英語を教えた教え子で、中2で2学年上の駿台、河合塾の高1模試で全国1位を獲得した子が2人います(それぞれ東大理Ⅲと京大医学部に現役合格)。
仮にこの子たちが高校受験をするのであれば、高校数学に踏み込む範囲を制限せざるを得ないので、同じような結果は出せなかったと思います。
さて、この問題ですが、地道に展開することももちろんできますが、面倒なので、頭を使って計算します。
高校の範囲では3乗の展開公式がありますが、公式を当てはめて解くのではありません。
先ほど紹介した最後の展開方法を利用します。
(x-2y)(x-2y)(x-2y)
① ② ③
①、②、③の( )内はすべて1次の項のみだから、計算結果は3次の項のみとなり、x3とx2yとxy2とy3が出てくることがわかります。
この係数を決定するだけですが、x3が出てくるのは、①~③の( )で文字xを採用するときで、文字の採用の仕方は1通りあり、係数は1×1×1×1=1(実際は、式を考えるまでもなく1ですね)、x2yが出てくるのは、2つの( )で文字xを、残り1つの( )で文字yを採用するときだから、文字の採用の仕方は3通りあり、係数は3×1×1×(-2)=ー6(実際は、3×(-2)=-6)、xy2が出てくるのは、1つの( )で文字xを、残り2つの( )で文字yを採用するときだから、文字の採用の仕方は3通りあり、係数は3×1×(-2)×(-2)=12(実際は、3×(-2)×(-2)=12)、y3が出てくるのは、①~③の( )で文字yを採用するときで、文字の採用の仕方は1通りあり、係数は1×(-2)×(-2)×(-2)=-8となります。
文字yの係数が-2だから、文字yを1個採用するごとに-2を1個かけていくことに注意するだけです。
言葉で書くと長々しくなります(書いている私自身が面倒くさいなと思いますからね)が、実際にはこの作業を口頭で繰り返すことでスピードが上がります。
しかも、将来習う二項定理も暗記することなく当たり前の式として自分で導き出せるようになります。