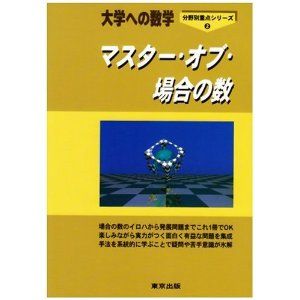最初、Aさんは50円玉を1枚、10円玉を4枚、5円玉を1枚、1円玉を4枚持っていて、Bさん、Cさんは何も持っていない。中の見えない箱の中に、1円、2円、・・・、99円と書かれたカードが1枚ずつ計99枚ある。Aさんはこの箱からカードを1枚引き、そのカードを箱に戻さずに続けてBさんがカードを1枚引く。
Aさんが自分の引いたカードに書かれている金額をBさんに支払い、その後Bさんが自分の引いたカードに書かれている金額をCさんにちょうど支払うことができたとき「成立」とする。
(1)Aさんが引いたカードに23円と書かれていたとき、「成立」となるBさんのカードの引き方は全部で[ ]通りある。
(2)「成立」となる確率を求めよ。
(注)
確率→小学生の場合、とりあえず、すべての場合に対してある場合が起こる割合と考えればよいでしょう。
灘高入試の場合の数・確率の問題は灘中受験生なら解けるものが多いですが、今回取り上げた問題もそうですね。
今年の灘高入試では、もう1問確率の問題が出ていましたが、灘中受験生なら「手の運動」にしかならないような問題でした。
さて、今回取り上げた問題は、(1)が微妙な感じの問題で、(2)だけ出したほうがよかったでしょうね。
23というのが中途半端に小さな数なので、すべての場合を書き出してしまっても解けてしまい、却ってメインの問題の解決の妨げになりかねないですからね。
例えば87円とかであれば、書き出そうとは思わないので、メインの問題の解決につながる解法に行きつく可能性高くなるでしょうね。
問題自体は、中学入試でも出される、ちょうど支払える金額が何通りになるかという典型問題にすぎませんが、その合計を求めないといけないので、(小学生には)若干難しくなっています。
とはいえ、約数の総和の求め方(神戸女学院中学部1995年算数2日目第4問の解答・解説を参照)や九九の計算結果の和の求め方(2025年の中学入試に出されそうな算数の問題(その1)を参照)をきっちり理解していれば、それと同じやり方でできるので、灘中受験生なら解けてほしい問題です。
因みに、硬貨の枚数の設定は、2025年の入試にふさわしいものとなっています。
優秀な出題者が、適切な解き方にたどり着いた受験生に喜んでもらおうとしたのでしょうね。
今年の灘中入試では、1日目の計算問題(下の(参考問題))で、2025の桁を落とした数が露骨に出ていて、しかもその数値に何の意味もないつまらない問題でしたが、この灘高の入試問題はかなりおしゃれでいい問題です。
詳しくは、下記ページで。
(参考問題)灘中学校2025年算数1日目第1問
(1+3/2-5/4+7/6-9/8-11/10)×45/23+2.025=□
(解説)
( )の中で1から11までのすべての整数が順に並んでいますが、出題者の遊び心によるものでしょう。
( )の中の仮分数を頭の中で帯分数に直すと、整数部分がすべて消えることがすぐにわかりますね。
1/2-1/4+1/6-1/8-1/10を計算することになりますが、1/2-1/4が1/4になり、1/4-1/8が1/8になることがすぐにわかるので、あとは1/8+1/6-1/10を通分して計算することになり、(15+20-12)/120=23/120となることもすぐにわかるでしょう。
23/120×45/23=3/8=0.375と2.025の和の2.4が答えとなります。
灘中受験生なら、上記の計算をすべて暗算で行うことができて当たり前でしょう。