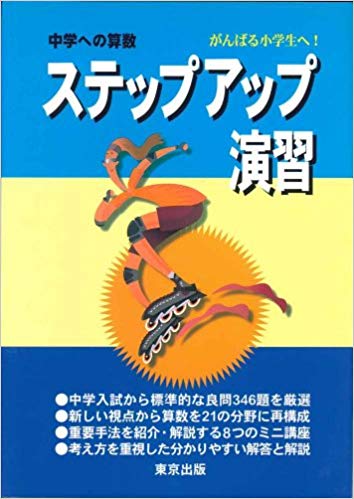2、3、4の3つの数の中から1つを選んで0に足していく操作を繰り返します。足した数の合計がちょうど8になって操作を終了したとき、次の①、②の場合、数の足し方はそれぞれ何通りありますか。
①足した数の順番が異なるものも同じものとして数える場合
②足した数の順番が異なるものは別のものとして数える場合
中学入試だけでなく大学入試でも昔からよく出されている問題です(慶應義塾中等部2007年算数第6問、久留米大学附設中学校2020年算数第1問(5)、京都大学2007年理系乙数学第1問 問2など)。
レベルの高い中学校では露骨な誘導をつけずに出されるのが普通です。
ところが、今年の甲陽の問題(甲陽学院中学校2025年算数2日目第4問)もそうでしたが、今回取り上げる久留米大附設の問題もなぜか誘導がついています。
同様の問題が5年前に附設で出されたときには誘導がついていなかったのに、一体どういうことなのでしょうかね。
レベルが下がっている中学校ならわかりますが、そうでないので謎ですね。
さて、今回の附設の問題ですが、それほどレベルの高い問題ではないので、誘導がなくても誘導と同じ解き方で解くのがいいでしょう。
別解で紹介した考え方を使うまでもありませんからね。
ただし、別解で紹介した考え方もしっかりマスターしておくべきでしょう。
実際、上で紹介した慶應中等部の問題、5年前の附設の問題、京大の問題では、別解の解き方のほうが明らかに楽ですからね。
詳しくは、下記ページで。
久留米大学附設中学校2025年算数第1問(2)(解答・解説)