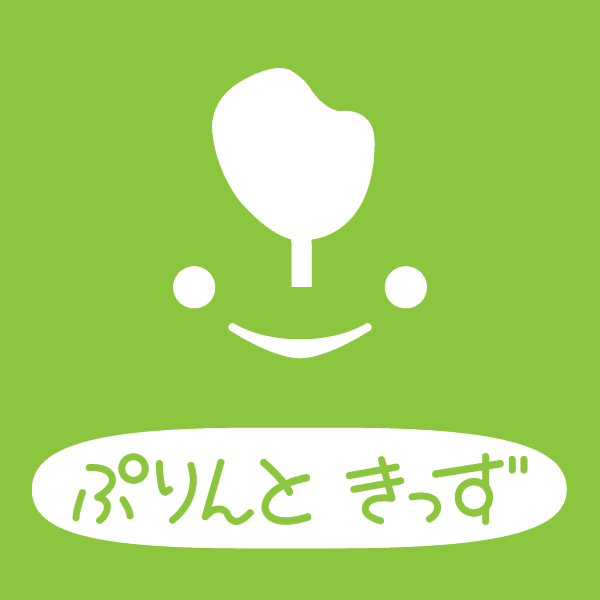こんにちは、プログラマーパパ🥷🏻です。
2月11日(日)〜2月17日(土) 🧒🏻の勉強を振り返りました。
前回の振り返り
算数
●公文小学ドリル、足し算・引き算、11~15、9~13
引き続き2年生に向けて繰り上がり・繰り下がりをメインに学習
2周目を終えてそれなりに正解率は高くなってきた
来週はナンバーを少し先へ進める
正解率向上以上に良かった点は下記の補助書きを習慣化できるようになってきている点(前は面倒がってサボったりしていた)
【学習設計】補助書き
- 繰り上がりで10の位の上に1を書く
- 繰り下がりで10の位の数字nを、n-1, 1 へ分ける表記を書く
補助書き忘れると1の位の結果を答案に書き終わった後、全体として繰り上がりがあったかどうかを忘れてしまうことがあるので、ミスが起きないように🧒🏻に習慣付け
●時刻と時間
ぷりんときっず様教材継続
🧒🏻にとって難易度”難しい”がちょうど良いレベル感になってきた
【学習設計】ちょうど良いレベル感の定義
- 答えを出すまで少し時間がかかる
- 即答はできない
- 自力で正解に辿り着く術は知っている
- 1つの数字を進むたびに5ずつ増やして数える
- 正解率は7〜8ぐらい
上記の難易度難しい問題相当の問いかけを実生活で時計を見せて時間感覚を身につけさせる練習は継続
【学習設計】時間の問いかけ
- 8時まで後何分?
- 今から15分後・前は何時何分?
- 今から30分後・前は何時何分?
- 今から1時間後・前は何時何分?
●お菓子をおもちゃのおかねで支払う練習
3桁の数を書くはできるようになってきた
実生活に近い支払いシミュレーションはまだ手付かず
そろそろ実店舗での買い物を始める頃合いかもしれない
国語
●学研おはなしドリル
今週は1.2 を実施
- 『ネコの目はなぜかたちがかわるの?』
- 『アリのすはなぜ土の中にあるの?』
やってみた感じ結構良い👍
物語ではなく客観的な事象に対してサイエンスの観点からの説明が入っていて親目線で子供に補足説明しやすい
- こういう現象がある
- それはなぜだと思う?
- こういう理由だから
これらが文章や問題文に書かれていてそれを読み解くという観点で作られている🥷🏻
さすが学研。いい教材作ってる👍
(🥷🏻は学研と聞くと科学と学習を思い出す世代ですが、どちらもやってなかったです)
物語文をできなくて良いというわけではなく、はじめに取り組むジャンルとしてこの手の文章は取っ掛かりやすいと感じる
これは問題集というより読み聞かせの題材として日々取り組むことを検討中
- 読書教材としてみると長くないので取り組みやすい
- 簡単な設問付きの読書として捉えれば日々の本読みとして位置付けられる
●公文国語
引き続き継続
こちらは目立って大きな進歩はないが、目立って大きな悪い点もない
欲を言えばもう少し早い時間で完了できると良いが😅