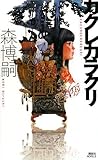¥461
Amazon.co.jp
皆さんこんばんは。
朝夕冷え込みますが、いかがお過ごしですか。
冷え性の管理人は冬がつらすぎてつらすぎて叶いません。冬こそゆっくりお風呂に入って体を温めようと思います。
さて、本日の本は筒井康隆さん『旅のラゴス』です。裏表紙の売り文句には「物語を破壊しつづけた筒井康隆が挑んだ堅固な物語世界!」とあります。確かに私の知っている筒井康隆さんは「これって小説としてありなの?」という作品を書いていた人のはず!!気持ち悪くて不快で下品で面白い小説を書いていた人なはず!(印象には個人差があります)
で、でもほら……『時をかける少女』みたいにピュアッピュアなのもお書きになるし。よし、読もう!!と思って手に取りました。
本作はタイトルのとおり、ラゴスという名の青年が旅をするお話です。
ラゴスのいる星は、高度な文明を持ったご先祖さんが逃げ込んできた星で、その文明はポロという場所の1室にある書物に記されて残っているばかりで、かなり原始的な生活に戻ってしまっているようです。もちろん高度な文明を持った2200年前の人が地球人とは一言も書いていないのですが、私はそう考えて読んでしまいました。
そんな未発達の文明に逆戻りしてしまったラゴスたちですが、私たちには出来ないような特殊な能力を持っている人がたくさん居ます。「転移」という、心の中に浮かべた景色に瞬間移動できる能力や、家畜や人の感情を読み取る能力、心に浮かんだ人の顔をたちまち再現してしまう能力……ラゴスはいろんな能力を持った人に出会います。
ラゴスの旅は基本的に一人旅なので、出会いもあれば別れもあります。カットインしてきたと思ったらカットアウトしていっちゃうモブ。いつまでも心に残り続ける女性や当時の仲間。余分な描写は一切なく、分かれてしまった彼らのその後を知るすべはありません。旅は一期一会ですからね。
以下ネタばれ
ラゴスは目的の書物を見つけ、その知を赴くままに享受し成り行きから旅の出発点、つまりは自分の家に戻ってきます。でもその途中で本を書き写した貴重なメモを山賊に捨てられてしまうのですね。知識・学問を最高のものだとして考えていたラゴスにとっては身を切られるような壮絶な辛さだったのではないでしょうか。
しかし、紙を捨てられてしまったラゴスは『その十五年のうちにお前は、人間の生み出した知の遺産が、十五年どころか、ひとりの人間が一生かかろうが、二生、三生かかろうが学びきれぬほどの膨大なものであることを身にしみて悟ったのではなかったのか(以上引用)』と気づきます。文明に対して常に謙虚であったラゴスにも傲慢さがあったのだということなのでしょうか。
故郷に帰ったラゴスは今、自分ができる役目をすべて終え、再び旅立ちます。今度は自分の心の赴くままに。解説の鏡明さんは、この物語における未来が、過去そのものである、と書いていますね。再び旅に出るには、一度帰郷せねばならんということらしいです。なるほどなぁ。
読んでみた感想は、なんだろう。思考停止してます。馬鹿たれな自分にはうまい感想など書けそうもないです。ただ、ラゴスの旅は人生そのもので、私の人生にもきっと到達点があって、帰るべき原風景があって、そしてまたそれを知って旅に出ることになるのだろうなぁと思いました。旅に出るというのは、生きるということで、ラゴスが旅をやめないというのは、生き続けることを辞めないということだと今の私は思いました。
不思議なパワーと切なさを与えてくれる本です。とても好きな本に出会えました。