想像ラジオ/河出書房新社
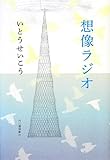
¥1,512
Amazon.co.jp
いとうせいこうさんっていったい何やってる人なんだろう。
昔大食い選手権みたいなやつの司会をやってらっしゃった記憶もあるし、みうらじゅんさんと仏像を見に行っていた記憶もあるし……。一番印象に残っているのはシティーボーイズさんのライブで舞台に出ていらっしゃったときのこと。管理人はシティーボーイズが好きなんですが、昔は毎年のように出ていらっしゃったんですよね。中村有志さんと。5人の公演が大好きでした。『マンドラゴラの降る沼』はもちろん『スイカ割りの棒 あなたたちの春に 桜の下で始める準備を』も生で見に行きました。素敵でした。
そんな「なんかちょっと面白いことをする人」という印象だったいとうせいこうさんなんですが、小説もお書きになるんですよね!むしろこっちが本業なのかな?『ノーライフキング』をずっと昔に読んだ記憶があります。忘れちゃいましたけど……。
本作はラジオのお話。DJアークという箱舟みたいな名前の人が送るラジオです。
でもこのラジオ、AMにあわせてもFMにあわせても聞けないんです。ではどうやって聞くかというと、ただ想像するだけでいい。だから「想像ラジオ」なんです。
この話はラジオを聞いたことがある人とない人で印象が違うんじゃないでしょうか。ラジオを聴いていた人って、青春の中にラジオの記憶があるもので、嫌でもそのときのノスタルジックな雰囲気が思い出されてしまいませんか……?私も深夜ラジオを馬鹿みたいに聞いていた世代なので、なんだろうな、ラジオを聴いていた人たちの中に変に芽生える孤独な連帯感みたいなものを思い出しました。
ラジオってたぶん一人で聞くことが多いと思うんですよ。テレビと違って。しかも夜に。でもラジオの中には自分に話しかけてくれるDJさんがいて、面白い話題を提供してくれるはがき職人さんが居て、恋愛に悩んでいる学生のリスナーさんがいて……ってなんだか孤独を慰めてくえっる存在じゃなかったですか?
このお話の中でラジオを聴いているのは死んでしまった人たちです。しかも、東日本大震災で。生きている人たちと死んでいる人たち、それぞれの想いが切々と語られていきます。
印象に残ったのは「死んだ人を忘れよう忘れようとしている」という箇所でしたね。もう震災から3年半経ちますが、確かに当時は「早く忘れなきゃ前に進めない」と自分たちに言い聞かせていたような気がします。でも、忘れなくてもいいのではないかとこの本はいうわけですね。死んだ人はそれをうらみ続けていいし、生きている人は死んだ人を思い続けても良い、それが本当の死者との共存なんじゃないかって。
誰も幸せにはならないけれど、どこかで誰かが自分のためにこんなラジオをしていてくれたらなと感じた本でした。
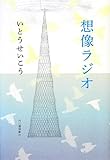
¥1,512
Amazon.co.jp
いとうせいこうさんっていったい何やってる人なんだろう。
昔大食い選手権みたいなやつの司会をやってらっしゃった記憶もあるし、みうらじゅんさんと仏像を見に行っていた記憶もあるし……。一番印象に残っているのはシティーボーイズさんのライブで舞台に出ていらっしゃったときのこと。管理人はシティーボーイズが好きなんですが、昔は毎年のように出ていらっしゃったんですよね。中村有志さんと。5人の公演が大好きでした。『マンドラゴラの降る沼』はもちろん『スイカ割りの棒 あなたたちの春に 桜の下で始める準備を』も生で見に行きました。素敵でした。
そんな「なんかちょっと面白いことをする人」という印象だったいとうせいこうさんなんですが、小説もお書きになるんですよね!むしろこっちが本業なのかな?『ノーライフキング』をずっと昔に読んだ記憶があります。忘れちゃいましたけど……。
本作はラジオのお話。DJアークという箱舟みたいな名前の人が送るラジオです。
でもこのラジオ、AMにあわせてもFMにあわせても聞けないんです。ではどうやって聞くかというと、ただ想像するだけでいい。だから「想像ラジオ」なんです。
この話はラジオを聞いたことがある人とない人で印象が違うんじゃないでしょうか。ラジオを聴いていた人って、青春の中にラジオの記憶があるもので、嫌でもそのときのノスタルジックな雰囲気が思い出されてしまいませんか……?私も深夜ラジオを馬鹿みたいに聞いていた世代なので、なんだろうな、ラジオを聴いていた人たちの中に変に芽生える孤独な連帯感みたいなものを思い出しました。
ラジオってたぶん一人で聞くことが多いと思うんですよ。テレビと違って。しかも夜に。でもラジオの中には自分に話しかけてくれるDJさんがいて、面白い話題を提供してくれるはがき職人さんが居て、恋愛に悩んでいる学生のリスナーさんがいて……ってなんだか孤独を慰めてくえっる存在じゃなかったですか?
このお話の中でラジオを聴いているのは死んでしまった人たちです。しかも、東日本大震災で。生きている人たちと死んでいる人たち、それぞれの想いが切々と語られていきます。
印象に残ったのは「死んだ人を忘れよう忘れようとしている」という箇所でしたね。もう震災から3年半経ちますが、確かに当時は「早く忘れなきゃ前に進めない」と自分たちに言い聞かせていたような気がします。でも、忘れなくてもいいのではないかとこの本はいうわけですね。死んだ人はそれをうらみ続けていいし、生きている人は死んだ人を思い続けても良い、それが本当の死者との共存なんじゃないかって。
誰も幸せにはならないけれど、どこかで誰かが自分のためにこんなラジオをしていてくれたらなと感じた本でした。

