大金塊―少年探偵 (ポプラ文庫クラシック)/ポプラ社
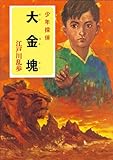
¥583
Amazon.co.jp
今日、ストーブを出しました。管理人です。
北のほうではもうとっくにストーブを出しておられるのでしょうか。ヴィクトリア時代の生活を夢見る管理人は電子暖炉がほしいのですがちょっとお高いので今年はストーブで我慢しようと思います。
本日の本は江戸川乱歩の少年探偵シリーズ『大金塊』です。
いわゆる本の虫!とおっしゃる方は、かなりの確率で小学校のときに少年探偵シリーズを読んでいたなんて話をどこかで聞いた気がします。
私も本の虫ではありませんが、小学校の図書館にあったこのシリーズを読んでいました。一番好きだったのは『海底の魔術師』。おどろおどろしい海の魔人と沈没船に隠された宝という王道のお話に興奮し、海底の描写を何度も何度も読み返していた記憶があります。
今回は宮瀬家に伝わる財宝をめぐるお話。
父親が不在のため、小学6年生の宮瀬不二夫君が家人たちと留守番をしていたある夜、宮瀬家に賊が忍び込み一枚の紙切れを奪っていきます。それには、現当主の鉱造氏の先祖が残した財産の隠し場所を示す暗号が書かれていました。しかし、用心深い鉱造氏は暗号の半分を自分の指輪に隠していたため賊はもう半分の紙を奪うために、不二夫君の誘拐を企てます。
しかし、名探偵明智小五郎は一計を案じ、小林少年を不二夫君に変装させ敵のアジトに潜入させます。小林君は盗まれたもう片方の暗号を奪い返すという大活躍。二つの紙を合わせてみるとこんな暗号が浮かび上がってきました。
『ししがえぼしをかぶるとき からすのあたまの
うさぎは三十 ねずみは六十 いわとのおくを さぐるべし』
さて、この暗号はいったいどこを指し示しているのでしょう。
一度童心に返ったつもりで、続きを読んでみてください。忘れかけていたどきどきワクワクの冒険心がよみがえってくること間違いなしです。
このシリーズは『K-20』という怪人二十面相の映画ができたときに文庫になっているようです。また全部読みたくなっちゃったな~。
そういえば読み返していて少し驚いたのが小林少年の年齢と身長。小林少年は少なくとも中学生以上で、身長が女性位には高い。私のイメージではちびっこい小学生だったんですけど……小林君結構大きかったんだな……まぁしっかりしてるもんな……。
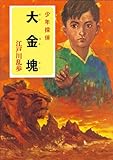
¥583
Amazon.co.jp
今日、ストーブを出しました。管理人です。
北のほうではもうとっくにストーブを出しておられるのでしょうか。ヴィクトリア時代の生活を夢見る管理人は電子暖炉がほしいのですがちょっとお高いので今年はストーブで我慢しようと思います。
本日の本は江戸川乱歩の少年探偵シリーズ『大金塊』です。
いわゆる本の虫!とおっしゃる方は、かなりの確率で小学校のときに少年探偵シリーズを読んでいたなんて話をどこかで聞いた気がします。
私も本の虫ではありませんが、小学校の図書館にあったこのシリーズを読んでいました。一番好きだったのは『海底の魔術師』。おどろおどろしい海の魔人と沈没船に隠された宝という王道のお話に興奮し、海底の描写を何度も何度も読み返していた記憶があります。
今回は宮瀬家に伝わる財宝をめぐるお話。
父親が不在のため、小学6年生の宮瀬不二夫君が家人たちと留守番をしていたある夜、宮瀬家に賊が忍び込み一枚の紙切れを奪っていきます。それには、現当主の鉱造氏の先祖が残した財産の隠し場所を示す暗号が書かれていました。しかし、用心深い鉱造氏は暗号の半分を自分の指輪に隠していたため賊はもう半分の紙を奪うために、不二夫君の誘拐を企てます。
しかし、名探偵明智小五郎は一計を案じ、小林少年を不二夫君に変装させ敵のアジトに潜入させます。小林君は盗まれたもう片方の暗号を奪い返すという大活躍。二つの紙を合わせてみるとこんな暗号が浮かび上がってきました。
『ししがえぼしをかぶるとき からすのあたまの
うさぎは三十 ねずみは六十 いわとのおくを さぐるべし』
さて、この暗号はいったいどこを指し示しているのでしょう。
一度童心に返ったつもりで、続きを読んでみてください。忘れかけていたどきどきワクワクの冒険心がよみがえってくること間違いなしです。
このシリーズは『K-20』という怪人二十面相の映画ができたときに文庫になっているようです。また全部読みたくなっちゃったな~。
そういえば読み返していて少し驚いたのが小林少年の年齢と身長。小林少年は少なくとも中学生以上で、身長が女性位には高い。私のイメージではちびっこい小学生だったんですけど……小林君結構大きかったんだな……まぁしっかりしてるもんな……。


