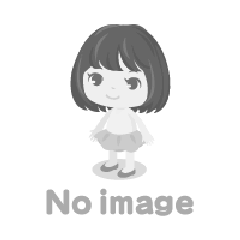写真パート8
科学と法医学
カメラには、ダゲールとフォックス タルボットが顕微鏡の接眼レンズに取り付けて天文現象 (日食など)、小さな生き物や植物などの科学現象を記録する手段として長く傑出した歴史があります。 (顕微鏡観察において)およびより大きな標本のマクロ写真撮影に適しています。 このカメラは、犯罪現場や 1861 年のウートン橋崩落などの事故現場の記録にも役立つことが証明されました。訴訟で使用するために写真を分析するために使用される方法は、総称して法医学写真として知られています。 犯罪現場の写真は通常、俯瞰、中距離、クローズアップの 3 つの視点から撮影されます。
1845 年、キュー天文台の名誉所長であるフランシス・ロナルズは、気象パラメータと地磁気パラメータを連続的に記録する最初の成功したカメラを発明しました。 さまざまな機械を使用して、大気圧、温度、湿度、大気電気、地磁気の 3 つの成分の分ごとの変化の 12 時間または 24 時間の写真トレースを作成しました。 カメラは世界中の多数の天文台に供給され、一部は 20 世紀まで使用され続けました。 少し後にチャールズ・ブルックがグリニッジ天文台用に同様の機器を開発しました。
科学では、レンズによって引き起こされる歪みを避けるために、ピンホール カメラの設計から派生した画像技術が定期的に使用されています。 X 線装置はピンホール カメラに似た設計で、高品質のフィルターとレーザー放射を備えています。 写真は、科学や工学、犯罪現場や事故現場での出来事やデータの記録に広く使われるようになりました。 この方法は、分光法だけでなく、赤外線写真や紫外線写真などの他の波長を使用することによって大幅に拡張されました。 これらの方法はビクトリア朝時代に初めて使用され、それ以来さらに改良されました。
最初に写真に撮られた原子は、2012 年にオーストラリアのグリフィス大学の物理学者によって発見されました。
社会的および文化的影響
写真のさまざまな側面に関して、多くの疑問が現在も続いています。 スーザン・ソンタグは、『写真について』(1977)の中で、写真の客観性を否定しています。 これは写真コミュニティ内で非常に議論されているテーマです。 ソンタグは、「写真を撮るということは、写真に撮られたものを流用することである。それは知識のように感じられ、したがって権力のように感じられる世界との特定の関係に自分自身を置くことを意味する。」と主張する。 写真家は、何を写真に撮るか、どの要素を除外するか、どの角度から写真を撮るかを決定しますが、これらの要素は特定の社会歴史的文脈を反映している可能性があります。 これらの線に沿って、写真は主観的な表現形式であると主張することができます。
現代の写真は、社会への影響について多くの懸念を引き起こしています。 アルフレッド・ヒッチコックの『裏窓』(1954) では、カメラは盗撮を促進するものとして描かれています。 「カメラは観測ステーションではありますが、撮影という行為は受動的観測以上のものです。」
カメラは、強姦したり、所有したりすることはありませんが、推定、侵入、不法侵入、歪曲、搾取、そして比喩の最も遠いところでは暗殺を行う可能性がありますが、性的な押しや押しとは異なり、すべての活動は、感情的に行うことができます。 距離があり、ある程度の分離を伴います。
デジタル画像は、後処理でのデジタル写真の操作が容易なため、倫理的な懸念を引き起こしています。 多くのフォトジャーナリストは、写真をトリミングしない、または複数の写真の要素を組み合わせて「フォトモンタージュ」を作成し、それらを「本物の」写真として渡すことを禁止すると宣言しています。 今日のテクノロジーにより、初心者の写真家でも画像編集が比較的簡単になりました。 ただし、カメラ内処理の最近の変更により、法医学写真の目的で写真のデジタル指紋採取により改ざんを検出できるようになりました。
写真は認識を変え、社会の構造を変える新しいメディアのひとつです。 カメラ周りでは減感に関してさらなる不安が生じている。 不快な画像や露骨な画像が子供たちや社会全体に広くアクセスできるのではないかという懸念が提起されています。 特に戦争写真やポルノ写真が物議を醸している。 ソンタグは、「写真を撮るということは、人々を象徴的に憑依できる対象に変えることである」と懸念している。 減感作に関する議論は、検閲された画像に関する議論と並行して行われます。 ソンタグは、写真を検閲できるということは、写真家が現実を構築する能力を持っていることを意味する、という懸念を書いている。
写真が社会を構成する実践の 1 つは観光です。 観光と写真が組み合わさって、地元住民がカメラのレンズによって位置づけられ、定義される「観光客の視線」が生まれます。 しかし、先住民の写真撮影者が観光客の写真家を浅はかな画像消費者として位置付けることができる「逆の視線」が存在するという主張もある。