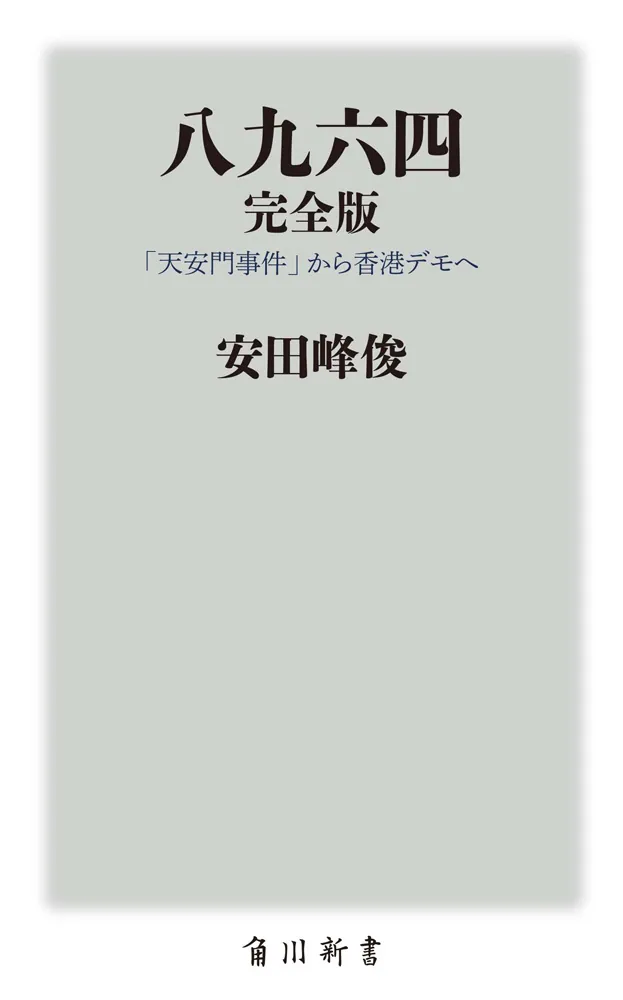1.共産党員の思考は類似?
未来社会としての中国の共産主義について書こうと思っていたら、日本共産党員を名乗るchocolateさんが、パトラとソクラに「中国の人権状況に対する日本共産党の考え方としては、2023年6月4日(日)の「しんぶん赤旗」の『主張』に掲載された 「天安門事件と中国 厳しく問われ続ける武力弾圧」が参考になるかと思います。」と書き込みをしてきました。
それで、その記事を見て、反論をしました。
そうしたら、こういう書き込みがまたありました。
>パトラとソクラさん
もうご覧になっておられたようですね。失礼しました。
これを読まれても、党の見解について納得がいかれなかったのでしょうか。
03月19日 22:45 chocolate
翌日さらにこういう書き込みがありました。
結果的に日本共産党の「地域安全保障」の考え方を知っていただく、たいへん良い機会を提供していただいたように思います。
このコメント欄に参加なさっている皆さんでこの分野に関心をお持ちの方がおられましたら、ぜひ【 日中関係の前向きの打開を――日本共産党の「提言」について[2023年5月13日(土)、「しんぶん赤旗」] 】をご一読いただきたいものと思います。(※もし可能でしたら「提言」そのものについてもご覧ください。[3/30発表])
私たち日本共産党が、どのような姿勢でもって外交問題に取り組んでいこうとしているのかが、大変よくご理解いただける「提言」であると私は思っています。
03月20日 07:18 chocolate
いやあ、これには呆れました。
もし、この団体がカルト宗教なら、脱会不能でしょう。
天安門事件は中国国内で全容が報道されていません。
犠牲者になった遺族が真相究明と謝罪を求めても、政府も共産党も応じません。
しかし、中国政府は天安門事件について、「事件を口実に中国を中傷し、内政に干渉するいかなるたくらみも、思いどおりにならないだろう」と言っています。
これは、cocolateさんの話法とも似ています。
パトラとソクラのが、今の日本共産党の内部で起きている表現の自由と結社の自由をめぐる問題と、中国共産党が天安門事件で取っている態度は類似なのですと主張しました。
日本共産党は、党内民主主義で「表現の自由」をめぐる社会的批判を「結社の自由」として拒むのでなく、すべての人権と基本的自由の発展に努めるべきです、と書いたのです。
その答えが上のchocolateさんの書き込みなのです。
私たち日本共産党が、どのような姿勢でもって外交問題に取り組んでいこうとしているのかが、大変よくご理解いただける「提言」であると私は思っています。
自分の都合のいいようにすべてを解釈するのです。
「内政干渉」という拒否の仕方と「結社の自由による内部問題」という突っぱね方が似ているとは思わないのです。
中国共産党にとっても日本共産党にとっても「幹部の見解」が常に正しいのです。
2020年時点での中国共産党の党員数は約9200万人。中国の人口が、去年末の時点の推計で14億967万人なので、人口の約6.5%です。
日本がもし共産主義国家なら、中国と日本の人口を比較して、chocolateさんみたいな人が今の日本に780万人くらいいる感じなのでしょう。
パトラとソクラと話が通じる人のほうが少ないと思います。
かなり生きづらい国になるんじゃないかな?
2.八九六四(第二次天安門事件)は民主集中制のトップの闘い?
ソ連・東欧では、人々が表現の自由や政治的自由を求めて社会主義国家が崩壊しました。
その国家を作るために主導した共産党は解体し、消滅しました。
では、中国ではどうしてそうならなかったのか?
今も共産主義国家は消滅する兆しもない。
それはどうしてなのでしょうか?
そこに天安門事件が果たした役割とそれを契機として中国が取った政策の成果があると思います。
よく知られている1989年の天安門事件は正確には、第二次天安門事件と呼ばれています。それは、1976年に周恩来国務院総理(首相)追悼の為に捧げられた花輪が撤去されたことから抗議した事から起きた天安門広場の暴動と区別するためです。中国では六四天安門事件(ろくしてんあんもんじけん)と呼ばれています。
日本では、安田峰俊氏が関係者に取材をして全貌をまとめた『八九六四』という本も出版されています。
この本を読むと、六四天安門事件が中国の人々に与えた、いや今も与え続けているプラスとマイナスの影響がわかります。
六四天安門事件は、1989年6月4日(日曜日)に中華人民共和国・北京市にある天安門広場に民主化を求めて集結していたデモ隊に対し、軍隊が実力行使し、多数の死傷者を出した事件です。
六四天安門事件の背景としての社会主義国での「自由化」
この事件の背景には、社会主義国のソ連で起きた「自由化」に遠因があります。
1985年3月にソビエト連邦共産党書記長に就任したミハイル・ゴルバチョフは、「ペレストロイカ」を表明しました。
これはソビエト共産党による一党独裁制が続く中で、言論の自由への弾圧や思想・良心の自由が阻害されたことや、官僚による腐敗が徐々に進み、硬直化した国家運営を立て直すことが目的でした。
ソ連が民主化を進めるなか、中国でも、1986年5月に中国共産党中央委員会総書記の胡耀邦が「百花斉放・百家争鳴」を再提唱して言論の自由化を推進しようとしました。
これに対して鄧小平ら党内の長老グループを中心とした保守派は、「百花斉放・百家争鳴」路線の推進は、中国共産党による一党独裁を揺るがすものであり、ひいては自分たちの地位や利権を損なうものとして反発したのです。
1986年9月に行われた六中全会では、国民からの支持を受けて、胡耀邦が押し進めようとした政治改革は棚上げされ、逆に保守派主導の「精神文明決議」が採択され、胡耀邦は長老グループや李鵬らの保守派の批判の矢面にさらされました。
12月に、北京や地方都市で学生デモが発生すると保革の対立は激化し、胡耀邦は1987年1月16日の政治局拡大会議で、鄧小平ら党内の長老グループや保守派によって辞任を強要され、事実上失脚しました。
胡耀邦の後任として、改革派ながら穏健派であった趙紫陽総理が総書記に選出されました。
胡耀邦の死と民主化を求める運動
胡耀邦は失脚後も政治局委員の地位にとどまりましたが、北京市内の自宅で警察の監視のもと外部との接触を断たれるなど事実上の軟禁生活を送り、1989年4月8日の政治局会議に出席中心筋梗塞で倒れ、4月15日に死去しました。
胡耀邦が中国の民主化に積極的であったことから、その死を契機として、民主化推進派の大学生を中心としたグループが北京市内などで民主化を求めた集会を行いました。
これらの集会は最初は、小規模でしたが、4月18日には天安門広場に面する人民大会堂前で座り込みのストライキに発展しました。同時に別のグループが中国共産党本部や党要人の邸宅などがある中南海の正門である新華門に集まり、警備隊と小競り合いを起こしたのです。4月21日の夜には10万人を越す学生や市民が天安門広場で民主化を求めるデモを行うなど、急激に規模を拡大していきました。
4月22日には午前10時、人民大会堂で胡耀邦同志追悼大会が開催されました。
学生を中心とした民主化や汚職打倒を求めるデモは、中国全土に広がっていきました。
西安では車両や商店への放火が、武漢では警官隊と学生との衝突が発生しました。
趙紫陽は「国外に動揺を見せられない」として北朝鮮への公式訪問を予定通り行うことを決め、李鵬に「追悼会は終わったので学生デモを終わらせる、すぐに授業に戻すこと、暴力、破壊行為には厳しく対応すること、学生たちと各階層で対話を行うこと」とする3項目意見を託しました。
しかし、趙紫陽が出国してすぐの4月25日、保守派の李鵬や李錫銘北京市党委書記、陳希同北京市長らが、鄧小平の談話を下地にした「旗幟鮮明に動乱に反対せよ」と題された社説(四・二六社説)を4月26日付の人民日報1面トップに掲載しました。
北朝鮮訪問前に趙紫陽が示した「3項目意見」は全く反映されず、社説は胡耀邦の追悼を機に全国で起こっている学生たちの活動を「ごく少数の人間が下心を持ち」、「学生を利用して混乱を作り出し」「党と国家指導者を攻撃し」「公然と憲法に違反し、共産党の指導と社会主義制度に反対する」と位置づけていました。
学生の自由化を求める要求に対する趙紫陽ら改革派と李鵬ら保守派の対立
上海市の週刊誌である『世界経済導報(英語版)』は改革派であった胡耀邦の追悼をテーマとした座談会を開き、その中で参加者が胡耀邦の解任を批判したり名誉回復を要求する発言を報じました。
校正刷りの段階で内容を把握した上海市は、党委員会書記(当時)の江沢民が宣伝担当の曽慶紅市党委副書記と陳至立市党委宣伝部長に命じ、問題の箇所を削除するよう命令を出しました。
しかし、『世界経済導報』の社長である欽本立がこの要求を拒否したため、同紙は発行停止となりました。この事件は学生だけでなくジャーナリストの反感をも買いました。
4月29日午後に、袁木国務院報道官が高校生と会見したとき、袁木は党内に腐敗があることを認めたものの、「大多数の党幹部はすばらしい」と述べ、『世界経済導報』事件があった直後にもかかわらず「検閲制度など無い」と否定し、「デモは一部の黒幕に操られている」との述べました。この模様が夜に放送されると、学生たちは抗議デモに繰り出しました。
趙紫陽は4月30日に北朝鮮から帰国しました。
5月1日の常務委員会で秩序の回復と政治改革のどちらを優先させるかで李鵬首相と対立しましたが、5月4日の五・四運動70周年記念日までにデモを素早く抑えることで一致しました。
五・四運動の70周年記念日である前日5月3日に開かれた式典では、北京の学生・市民ら約10万人が再び民主化を求めるデモと集会を行っていました。趙紫陽は学生の改革要求を「愛国的」であると評価し、5月4日午後からはアジア開発銀行理事総会でも同様に肯定的な発言をしました。
この頃、中国全土から天安門広場に集まる学生や労働者などのデモ隊の数は50万人近くになり、公安(警察)による規制は効かなくなりました。天安門広場は次第に市民が意見を自由に発表できる場へと変貌していました。
この民主化運動の指導者は、漢民族出身の大学生である王丹や柴玲、ウイグル族出身のウーアルカイシ(吾爾開希)などで、5月18日午前に李鵬、李鉄映、閻明復、陳希同らが彼らと会見しました。
まず李鵬が「会見の目的はハンストを終わらせる方法を考えることだ」と発言すると、ウーアルカイシは「実質的な話し合いをしたい。我々は李鵬を招待したのであって、議題は我々が決める」と反論しました。
学生側は「学生運動を愛国的なものとすること」と、「学生と指導者の対話を生放送で放送すること」を要求しましたが、李鵬は「この場で答えることは適当ではないし、2つの条件はハンスト終結と関連付けるべきではない」と話し、会見は物別れに終わりました。
このような状況下で、5月15日にはミハイル・ゴルバチョフ書記長が、当初の予定通り北京を公式訪問しました。
中国共産党は、ゴルバチョフと鄧小平ら共産党首脳部との会談を通じて中ソ関係の正常化を確認することで、「中ソ間の雪解け」を世界に向けて発信しようとして綿密に受け入れ準備を進めていました。
しかし、天安門広場をはじめとする北京市内の要所要所が民主化を求めるデモ隊で溢れており、当局による交通規制を行うことが不可能な状況になっていました。
ゴルバチョフと会見に臨んだ趙紫陽は当日、人民大会堂での会見で記者を前にこう話しました。
鄧小平同志は1978年の第11期三中全会より国内外が認める我々の党の指導者だ。第十三回党大会における彼の要求に基づき、中央委員会、政治局と政治局常務委員会からは退いたが、我々全党は彼から、彼の知識と経験からは離れられないことを知っている。1つ秘密を話そう。第13期一中全会では正式な決定を行っている。これは公布していないが重要な決定だ。 つまり、我々は最も重要な問題において彼の指導を必要とするというものだ。
この頃の中国共産党指導部は、改革派の趙紫陽総書記や胡啓立書記などと、李鵬首相や姚依林副首相らの強硬派に分かれていましたが、5月17日にゴルバチョフが北京を離れるまでの間は、この様な事態に対して事を荒立てるような政治的な動きを見せませんでした。
5月16日夜、趙紫陽、李鵬、胡啓立、喬石、姚依林の5人の政治局常務委員会が開かれ、学生たちの要求する「四・二六社説」の修正について話し合われ、趙紫陽は修正に賛成、李鵬は反対したため、決着しませんでした。
5月17日午後に改めて、党長老で事実上の最高権力者である鄧小平中軍委主席に加え楊尚昆国家主席を含めた会議が鄧小平の自宅で行われたところ、戒厳令の布告について趙紫陽と胡啓立が反対、李鵬と姚依林が賛成、喬石が中立の意見を表明し、5人の政治局常務委員会は割れました。
政治局常務委員ではない楊尚昆が賛成を表明した後、政治局常務委員会による投票をすることなく、鄧小平は以下のように発言し戒厳令の布告を決定しました。
「事態の進展を見ればわかるように、4月26日付社説の判断は正しかった。学生デモが未だ沈静化しない原因は党内にある。 すなわち、趙(紫陽)が5月4日にアジア開発銀行の総会で行った演説(学生の改革要求を「愛国的」と話した)が原因なのだ。今ここで後退する姿勢を示せば、事態は急激に悪化し、統制は完全に失われる。よって、北京市内に軍を展開し、戒厳令を敷くこととする。」
— 鄧小平
これに対し、趙紫陽は以下のように述べ、戒厳令の発動を拒否したため、鄧小平は李鵬、楊尚昆、喬石の3人を戒厳令実施の責任者に任命しました。
「決定を下さないよりは下した方が良いけれども、今回の決定が招くであろう深刻な事態を大変憂慮している。総書記として、この決定内容を推進し、効果的に実行することは私には難しい。」
— 趙紫陽
5月19日午前5時頃、趙紫陽は当時党中央弁公庁主任を務めていた温家宝を連れて、ハンガーストライキを続ける学生を見舞う中で涙を見せ、学生たちの愛国精神を褒め称え、「諸君はまだ若いのだから命を粗末にしてはいけない」と、迫りつつあった流血の惨事を避けるために、学生たちにハンストの中止を促しました。
この言葉は、学生たちに真意が十分に伝わらなかったのです。
しかし、趙紫陽の演説は学生たちに歓迎され、拍手は止みませんでした。
5月19日午後10時、党中央、国務院が中央と北京市党政軍幹部大会を開き、戒厳令布告の発表を行いました。
党中央、全人代、国務院、中央軍事委員会、中央顧問委員会、中央紀律検査委員会、全国政協と北京市の副部長級の幹部および、党中央弁公庁、国務院弁公庁の局長クラスが出席した。趙紫陽は「体調不良」により欠席することが大会を主催する喬石から伝えられ、趙紫陽に割り振られていた講話は楊尚昆国家主席が担当した。
5月20日、鄧小平は自宅で非公式会合を開き、趙紫陽の解任を事実上決定しました。その後、6月19日の政治局拡大会議で「動乱を支持し、党を分裂させた」として、趙紫陽は党内外の全役職を解任され自宅軟禁下に置かれ、これ以降政治の表舞台から姿を消しました。
5月23日には戒厳令布告に抗議するために北京市内で100万人規模のデモが行われました。
6月3日の夜中から6月4日未明にかけて、戒厳令実施の責任者である李鵬首相の指示によって、人民解放軍の装甲車を含む完全武装された部隊が、天安門広場を中心にした民主化要求をする大学生を中心とした民衆に対して投入されました。
このときの死者数について、中国当局は319人としています。
しかし、最も死者数を多く報道しているのは1989年6月5日に作成され、2017年12月23日に機密解除された英国政府の公文書では、「最低に見積もっても一般市民の死者は10000人以上が中国軍により殺害された。」と報告しています。
そのほか、ソ連の公文書に収められているソ連共産党政治局が受け取った情報報告では3000人の抗議者が殺されたと見積もられたりしていますが、1989年7月に作成され2011年6月に公開された米外交公電によれば、死者の数は1000人を遥かに下回るとされていたりして、真相はわかっていません。
3.六四天安門事件を弾圧した中国共産党が正しい
去年、こういう報道がありました。
香港のシンクタンク「香港民意研究所」は、1989年、北京で民主化を求める学生や市民を軍が武力で鎮圧した天安門事件について、30年前から毎年、香港の人たちを対象に世論調査を行ってきました。
この調査は事件の再評価や中国の人権状況などを尋ねていて「天安門事件について中国政府は正しいことをしたと思うか」という問いに対しては、「思わない」と答えた人が「思う」と答えた人を上回ってきました。
研究所はことしの調査結果を6日、インターネット上で発表する予定でしたが「リスクの検証を行った政府からの提言を受けた」として、発表を取りやめたことを明らかにしました。
六四天安門事件は、自由化を求めた学生が弾圧され、中国当局の発表を真実だとしても、少なくとも319人が殺害された事件です。
どうして、戦車を止めようとする学生ではなく、中国政府を正しいと思う人が上回るのでしょうか?
これは、事件の全容が報道されていないという問題が大きいと思われます。
しかし、事件を振り返り、今の世界を見たとき、本当にそう思う人たちがいることも事実です。
民主化のデモの指導者だった王丹(ワン・タン)のように天安門事件後、アメリカに亡命し、今も台湾で中国の民主化運動を続ける人もいます。
しかし、参加者のなかには、今の中国を支持する人もいます。
今でも天安門事件を主導した王丹などは、共産党支配に変わる何か未来の設計図があるわけでもなく、また民主化のための統一した団体を組織しているわけでもありません。
六四天安門事件の関係者に取材した安田峰俊氏によると、「考え方が多様すぎて、まとまらない」というのがこの問題に関わった人々の実情のようです。
東ドイツが崩壊し、ドイツが統一されました。
しかし、社会主義国で貧しかった東ドイツは、その非効率な社会システムもドイツ全体の重荷になり、バカにされているように見える中国の人たちもいます。
そういう状況の中で中国の国民は天安門事件を共産党が抑えなかったら、中国の国家はロシアのようにバラバラになっていたかもしれないと不安に思っているひとも少なくありません。
香港でも民主化をめぐって、2020年にデモの盛り上がりがあり、中国政府が弾圧しました。
プロレタリア独裁国家のなかに巨大な市場を抱え込む。
そのなかでは「搾取の自由」が許される。その経済的自由は精神的自由を育む。
共産党国家は「自由化」に染まる分子を雑草抜きのように排除する。
それは最近、日本共産党が行ったいくつかの除名処分とも似ています。
除名処分という雑草抜き作業です。
2022年にPHPの「Web Voice」にウーアル・カイシへのインタビュー記事が載りました。
中国も民主主義か?ということについてこう言っていました。
――共産党の一党独裁体制である中国と自由民主主義諸国では、価値観から政策決定に至るまで相容れないでしょう。
【ウーアルカイシ】第二次世界大戦以降に米国を筆頭とする戦勝国が構築したいまの国際秩序では当然、武力による国境の侵害を認めていません。ところが中国は、独自に国境を引いて新疆とチベットを併合しました。またウクライナを併合しようとするロシアのような独裁国家の横暴を国際社会が防げなかったように、第二次大戦後の国際秩序の不完全さが露呈しています。
さらに21世紀においては、インターネットや国際貿易システムが国境を曖昧にしている。中国は民主主義諸国の弱点を利用し、国際秩序の操作を試みているのが現状です。現に、中国がウイグルに行なっている人権侵害について国際社会から非難されようとも、少なくないイスラム国家が中国を支持しました。
もし中国が民主的ではないと国際社会が責めたとしても、彼らは「我々だって民主主義だ。投票があるのだから」と言い返すでしょう。たしかに中国の人民代表大会は投票で選出され、憲法には「民主」という文言が明記されています。
中国共産党は民主に無知ではなく、それを操ることに長けている。世界の民主的なゲームの規則は勝手に変更され、完全な失敗を迎えています。こうした状況を変えなければ、民主を操る中国のようなプレイヤーが第二次大戦後の国際秩序を利用して我々を支配しかねません。
レーニンは議会制民主主義をブルジョア民主主義だと一蹴し、共産党の民主集中制を推進しました。
日本でもそのシステムを採用しています。
それが行き着くのは、松竹伸幸氏の除名処分でしょう。
藤田健という機関紙の編集局次長が書いた文章を常任幹部会が正しいとしたら、府委員会・地区委員会でもその方向にそった形だけの調査がなされ、処分が下されます。
いつでも正しいのは、「常幹」=「常任幹部会」の見解であるということを末端まで1ミリも疑わないことだということに気付かないのです。
しかし、共産党では、その思考が組織を維持しているのも事実なのでしょう。