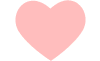以前、私が事務局を担当していた
大阪大学臨床栄養研究会からのお知らせです。
これは、阪大の臨床系の医局が持ち回りで
毎月違うテーマで講演を行い、
医療関係社や一般の人たちに知識を深めていただこうというものです。
もう、30年は続いているでしょうか?
ぜひ、興味のある方はご参加くださいね。
なお、毎月のお知らせをメールにてご希望の方は、
私までご連絡いただければ、登録させていただきます。
お名前、所属先などを書いて、下記アドレスに
 くださいね。
くださいね。 paris*paristyle.net (*を@に変えてね!)
paris*paristyle.net (*を@に変えてね!) 日 時: 平成22年4月13日(月) 18:30~
日 時: 平成22年4月13日(月) 18:30~ 場 所: 大阪大学医学部 講義棟2階 B講堂 (吹田市山田丘2-2)
場 所: 大阪大学医学部 講義棟2階 B講堂 (吹田市山田丘2-2) テーマ: 「医師と栄養士が組んで行う栄養療法―低身長児の栄養管理―」
テーマ: 「医師と栄養士が組んで行う栄養療法―低身長児の栄養管理―」今回は大阪府立母子保健総合医療センター消化器・内分泌科部長 位田忍先生と
同管理栄養士 西本裕紀子先生にご講演をお願い致しました。
多くの方々のご参加をお待ちしております。
小児の発育にとって「栄養」は不可欠な要素である。
疾患を持った子どもたちにとってもそれは例外ではなく、さらに栄養療法が治療の
根本をなす疾患もある。栄養治療の担い手である医師と栄養士が手を組み、
それぞれの知識と技能を分かち合うことで、より効果的な栄養治療を
子どもたちに提供することができる。
大阪府立母子保健総合医療センターにおける栄養療法の実践を低身長児に対する
我々の試みを通じて報告する。
身長発育は栄養、成長ホルモン(GH)、性ホルモンが作用する3相の重なりで構成される。
一方で身長発育は従来から慢性栄養障害の指標とされている。
Waterlow(1972)が栄養障害をstunting(慢性栄養障害) と
wasting(急性栄養障害)とに分類し、height for ageが 95%<が正常、
95-90% (-2SD以下)がGrade1、 90-85%がGrade2 、
85%がGrede3 の慢性栄養障害とし、weight for heightが 90%を正常、90-80% をgrade1、
80-70%をgrade2 、70%をgrade3の急性栄養障害とした。
我々は基礎疾患のない低身長児(低身長児)を栄養障害ととらえ、医師が内分泌的評価・
血液検査や診察所見から栄養評価を行った上で栄養士が介入し、前の栄養状態,
基礎代謝量、摂取量,食生活を評価し栄養指導実施(介入)後,
食生活チェック表に毎日の食生活を記録してもらい,半年後に再評価を行った。
低身長児は低栄養の傾向があり,食事の特徴として炭水化物特に米の摂取が少ないこと,
就寝時間が遅いなど生活リズムを含めた食生活にも問題があること、
三大栄養素(PFC)バランスが悪い食事をしていることなどが判明し、
その食生活改善に着目した栄養介入を行った。
半年後に栄養状態の改善とともに身長の伸びも認められ、
生活リズムを整え規則正しく食べることが小児の成長に重要な要素となることが確認できた。
また,PFCバランスが栄養改善のキーポイントであることが推察された。
低身長児には栄養療法が有効である場合があり,低身長児を栄養障害と捉えて
栄養管理を行うことの重要性が示唆された。
今回の検討から、低身長にも栄養の観点からアプローチが重要であることが明らかとなった。
子どもの成長を線で捕え、その軌道が外れないように見守り、
軌道が外れていれば適切にその原因を評価し早期に軌道修正をすることが
健全な成育に重要であり"栄養"はその中心的な役割を担っている。
栄養管理の担い手である医師と栄養士が手を組んで
専門性をいかすことが効果的な実践につながると思われる。
次回、第307回CNCは、
老年・腎臓内科学 藤澤智巳助教のお世話で平成22年5月10日(月)に開催予定です。
 こちらにもステキな情報がいっぱい!
こちらにもステキな情報がいっぱい! こちらにもステキな情報がいっぱい!
こちらにもステキな情報がいっぱい!