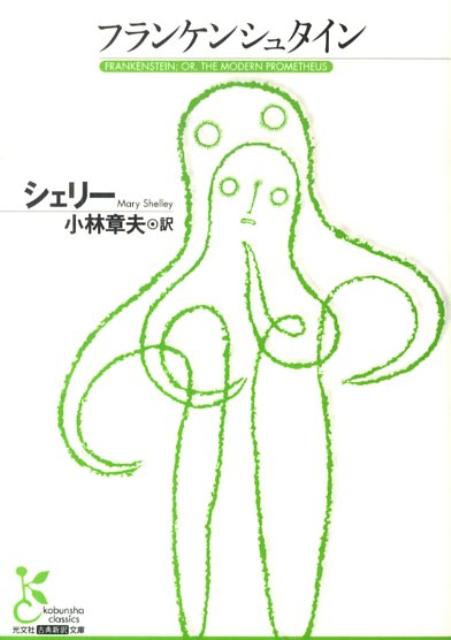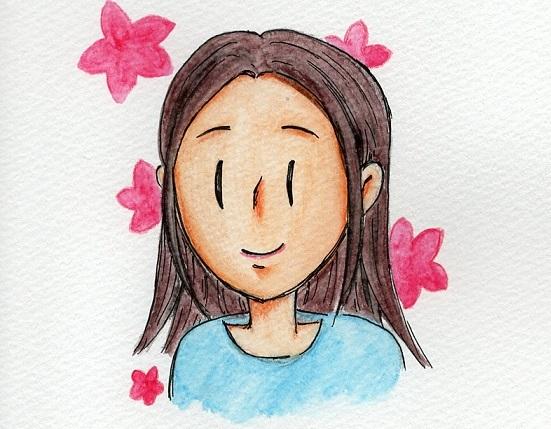2024年10月のテーマ
「目線で印象が変わる本」
第一回は、
「フランケンシュタイン」
シェリー 作、小林章夫 訳、
光文社古典新訳文庫、2010年発行
です。
以前に、「黒博物館 三日月よ、怪物と踊れ」という漫画をおすすめした際に、この漫画のモチーフとなり、主人公の一人である歴史上実在の人物、メアリー・シェリーが書いた小説「フランケンシュタイン」を一度ちゃんと読んでみたいと書いたのですが、その後ご縁があり読んでみたら、これが、もう…。
というわけで、あらすじです。
イギリス人で北極探検隊隊長・ウォルトンは北極圏に向かう途中、遭難者と思われる男性を救助。その男性はフランケンシュタインという名で、死を前にして彼に懺悔とも忠告ともつかぬ自身の体験を語るのでした。
優秀な青年だったフランケンシュタインは科学者を志して名門大学で学んでいました。やがて生命の謎を解き明かしたいという野望に取りつかれ、自らの手で生命を生み出すことになります。
しかしながら、誕生した新たな生き物は人と呼ぶにはあまりにも恐ろしく醜悪な外見をしていたため、フランケンシュタインは恐れおののき逃げ出してしまいます。今さらながらに己の行為が神に背くものだったと気づいたものの、自分が生み出した怪物を再び目にする勇気もなく、彼はすべてを忘れてしまいたいと願いながら故郷へ戻ります。
一方、誕生した怪物は研究室を出て外の世界を知り、人間の生活や文字、心、愛までも学んでいきます。
やがてフランケンシュタインは怪物と再び巡り合い、誕生してから後、怪物が体験してきたことや彼に心が芽生えていることを知ります。
フランケンシュタイン博士の苦悩と怪物の苦悩、相容れない二人の恐ろしくも悲しい物語です。
この物語は、ウォルトンという第三者がフランケンシュタイン博士の物語を書き留め、姉への手紙の中に書き綴っていくという形式をとっています。
そのうえ、怪物がフランケンシュタイン博士に語った物語は博士が書き留めていて、
ウォルトン ← フランケンシュタイン ← 怪物
という三重構造になっています。
つまり、読者はまずウォルトンの第三者としての目線で物語を読み、その次にはフランケンシュタインの心情を理解し、怪物の気持ちは彼が博士に語った言葉で知ることができるのです。
これだと、まずは第三者目線でフランケンシュタインと怪物の愛憎劇を読み始めることになります。
ところが、フランケンシュタイン博士の語りの部分(物語の大半にあたります)がすごく丁寧に描いてあって、彼の幼少期の思い出、家族や友人との関係、幼少期に熱中した本の影響から生命の謎にとりつかれていくに至った過程…そして怪物を生み出した後の苦悩や恐怖などを読んでいると彼の心情がよくわかるようになってくるのです。(ま、語り手ですからね。)
この物語の悲劇を生み出したのは彼自身であり、彼が怪物を作らなければこんなことにはならなかったわけで、苦悩する姿を冷ややかな目で見てしまう気持ちも私にはあったのですが、罪の代償としてとても重い罰を受けるので、同情を禁じえませんし、何より、事実上の主人公はフランケンシュタイン博士なので、知らず知らずのうちに彼目線で読んでしまっていました。
一方、怪物が自分の体験や気持ちを語り手として吐露する場面も物語中盤でがっつりあって、その部分は怪物目線で読んでいくことになります。醜悪な見た目のせいで人から疎外されて暴力を振るわれる。自分の存在について考える。愛を欲して得られない哀しさ…。ここだけ怪物目線で読めば、なんてかわいそうなんだろうと感じる方がほとんどでしょう。
しかしながら、最終的に第三者目線に戻っていくと、どちらがより悪いとか、あの時こうしていたらよかったのにとか、私にはよりよい解決方法を見つけることができませんでした。
博士が怪物を作ったのは重大な罪である一方、怪物が巻き起こした事件の数々はあまりにもひどく、どちらの側に立つことも私には難しかったのです。
ここまで、私が読んだときの目線を追って書いてきましたが、この作品は、人によって最終的に立つ目線が違うと思います。
どちらが正しいという話ではなくて、解決のできない問題で対立する立場があった場合に、どちらにより共感するかだとか、考え方が近いかとか、応援したくなるかとか、そういう心情的な理由で目線が変わってくると思うからです。
私が第三者目線に落ち着いてしまったのは、最終的にはどちらの応援もしたくなかったからです。
どちらの気持ちもつらく切なく、恐ろしく…。考えさせられることは山ほどありましたが、自分はこんな風な気持ちになりたくないと思ってしまったのです。
この「フランケンシュタイン」という作品は、文学的にも、書かれた時代の歴史的背景にも、作者のメアリー・シェリーに対しても、様々な角度から研究がされているようで、名作古典文学として語りたいことも多々ありますが、今回は"誰目線で読むか"に焦点を当てております。
この作品を読んだなら、読了後にぜひ自分は誰目線強めだったか考えてみてほしいです。おすすめいたします。(*^▽^*)