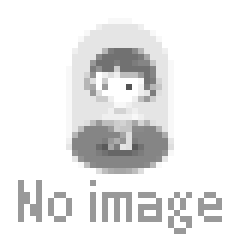こんにちは。
中学部理系担当の佐々木です。
先週はこの時期としては気温が高く、真夏日![]() を記録したところもあったようです。
を記録したところもあったようです。
このように急に気温が上がると気をつけなければならないのが熱中症です。
この時期はまだ気温が低く、身体が汗![]() をかくことにまだ慣れていません。
をかくことにまだ慣れていません。
ところが急に気温が上がると、汗をあまりかかず熱を発散できないので、
熱中症になりやすいと言われています。
この時期は遠足やスポーツテストなど野外で行う活動も多いので、
熱中症には気をつけて、こまめに水分を摂るようにしてください。
暑さに体を慣らすためには、風呂![]() に長めに入って汗をかくようにしたり、
に長めに入って汗をかくようにしたり、
ウォーキング![]() などの軽い運動で発汗をうながすとよいそうです。
などの軽い運動で発汗をうながすとよいそうです。
ところで、高校入試はまだまだ先ですが、
驚くようなニュースが飛び込んできた のでみなさんにお知らせします。
のでみなさんにお知らせします。
公立高校入試「デジタル併願制」導入を検討
現在の公立高校の入試は一人1校しか受験できない「単願制」となっていますが、
これを複数の高校を同時に志願できる「併願制」に変更するというものです。
これを検討することを、石破首相が文部科学省に指示したというニュースです。
この「デジタル併願制」とはどういうものなのでしょうか![]()
出願をする時に、生徒が複数の高校の志望順位をあらかじめ決めて志願し、
入試の点数や内申点、面接、部活動の成果などを基に、
デジタル技術を活用したアルゴリズム(計算手法)で生徒を順位付け、
合格基準を超えた高校を合格先として自動的に割り振る仕組みです。
これによってどんなメリットがあるのかというと・・・
合格ラインにギリギリの生徒が不合格になることを考慮して、
志望校のランクを落として願書を提出する、ということがありましたが、
「第一志望校がダメでも第二志望校なら大丈夫 」という安心感から、
」という安心感から、
本当に行きたい高校へ願書を提出することが可能になります。
つまり、「ギリギリだからあきらめる![]() 」ということがなくなるのです!
」ということがなくなるのです!
しかし当然デメリットもあり、その一つが、
「それぞれの高校のボーダーラインが上がる 」ということです。
」ということです。
点数のよかった生徒から自動的に振り分けるので、
単願制の時なら合格していた点数でも不合格になる可能性もあります。
・・・このようなことを話していますが、
まだ「デジタル併願制」を検討することを首相が指示しただけなので、
導入されるとしても数年先のことになりそうです。
他にも高校入試に関することでお伝えしたいことはあるので、
それはまたの機会にお話しします。
みなさんも高校入試に関するニュースには気をつけて見て下さいね。