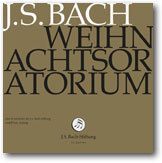本の山が崩れたことで
『文藝別冊 バッハ』が出てきて
そこで推薦盤にあがっていた
《クリスマス・オラトリオ》の
ガーディナー盤を聴き直したことは
前回書いた通りです。
それ以来
中古店に行くたびに
『文藝別冊 バッハ』での
《クリスマス・オラトリオ》推奨盤を
探すようになったんですけど
なかなか見つからず
その代わりに、今週の月曜日
冬季講習の帰りに見つけたのが
こちらの盤です。
(ワーナーミュージック・ジャパン
WPCS-16236/7、2015.11.18)
〈オリジナーレ〉という
古楽の旧盤を復刻するシリーズの1枚。
フリップ・ヘレヴェッヘ指揮
コレギウム・ヴォカーレ・ヘントの
合唱団と管弦楽団による演奏で
録音は1989年1月です。
ソリストは
バーバラ・シュリック(S)
マイケル・チャンス(C-T)
ハワード・クルック(T)
ペーター・コーイ(B)
という面々。
『文藝別冊 バッハ』には
あがってませんでしたが
ヘレヴェッヘならということで
あがなったんですけど
とりあえず第1部を聴いて
びっくりさせられました。
ソプラノが歌うコラールの章句を
バスがレチタティーヴォで説明する
という構成の第7曲目で
ソプラノ・パートが
合唱グループからの選抜による斉唱ではなく
ソリストが歌っているのでした。
(自分の耳にはそう聴こえます)
あわてて
手持ちの他の2枚や
オランダ・バッハ協会と
スイス・バッハ財団の動画を
確認してしまいましたが
自分の聴き間違いでなければ
ヘレヴェッヘ盤のみの
特徴のようです。
あとで述べる通り
第2部で羊飼いたちに
イエスの誕生を告げる
み使いの天使のレチタティーヴォも
これはソプラノのソロですけど
合唱団からの選抜ではなく
ゲストのソリストが
歌っているものと思われます。
これまた
他の演奏では
合唱団から選抜されて
歌っているのですね。
アルト・パートを
カウンターテナーが歌うというのも
数少ない手元の盤の中では
本盤のみの特徴ですが
これは他の古楽団体でも
やっていそうです。
それを知るには
まあ、見つけて買うしかなく
そうしてまた
懐が痛むという(苦笑)
その他に
自分的に特記されるのは
伴奏および通奏低音のオルガンが
ピエール・アンタイが弾いている
ということだったりします。
第1ヴァイオリンに寺神戸亮
オーボエに北里孝浩が
参加しているのも
注目すべきことでしょうか。
以下、記事タイトルの内容に入ります。
前回の記事でも書いた通り
バッハの四大宗教曲のひとつ
《クリスマス・オラトリオ》は
1曲が20〜30分くらいの
6つのカンタータを組み合わせた
いわゆる連作長編のようなものです。
第2部〈このあたりに羊飼いおりて〉は
1734年12月26日初演で
イエスが生まれた頃
羊の群れの番をしていた
羊飼いたちのもとに天使が訪れて
イエスの誕生を告げ
救世主のもとに急げと言う
羊飼いたちがふと気づけば
空には天使たちが満ちている
という状況を歌ったものです。
第2部冒頭は
器楽合奏によるシンフォニアで
パストラーレと呼ばれる
田園的な曲想が演奏されますけど
何で演奏しているのか
ハーディー・ガーディー風の
(ということはヴァイオリンかしら)
低音部のドローン旋律が
印象的な曲です。
こちらのドローン旋律は
最終曲(第14曲目)の
コラール合唱でも流れてきて
最初と最後に出てくることで
第2部に統一感を与えている
といったところでしょうか。
第6曲目のテノールのアリアは
《鳴れ、太鼓よ! 響け、トランペットよ!》
BWV214 のアリアからの転用で
第10曲目のアルトのアリアが
《ヘラクレス・カンタータ》BWV213 の
アリアからの転用。
《ヘラクレス・カンタータ》では
〈快楽〉の精がヘラクレスを誘惑する
という趣旨のアリアでしたが
《クリスマス・オラトリオ》になると
飼葉桶のイエスに向けた子守唄に変わる
という内容の落差の激しさで
有名なアリアです。
天使(バスのレチタティーヴォ)が
羊飼いたちに
救世主のもとに急いで
子守唄を歌えと言い終えると
空に天使たち(天の軍勢)が満ちる
という場面を加藤拓未は
「ふと気づくと、空は天使たちで
いっぱいに埋めつくされていた」
と書いてますけど
気づくとそんな状況だなんて
ちょっとホラーかも
なんて思ったり。(^▽^;)
そう思ったりするのは
自分が無宗教者だからでしょうけど。
皆川達夫が
「音楽とクリスマス」(1990)
というエッセイで
ルカ福音書の該当箇所を引いて
救い主キリスト誕生の喜ばしいしらせが最初にもたらされたのは、当時いちばん卑しめられていた羊飼いたちだったのです。そうしてまた、神をほめたたえ人々に平和を願う天使の歌声を聞いたのも、王侯貴族や金持ちたちではなく、彼ら羊飼いたちだったのでした。たいへんに暗示的、かつ象徴的なことのように思われます。(『音楽も人を救うことができる』p.43)
と書いているのを
思い出しもするんですけどね。
というわけで
ここで例によって
佐藤俊介の弾き振りによる
オランダ・バッハ協会の
第2部の演奏動画を
貼っておきます。
例によってアドレスも貼っておきます。
こちらの映像を観ると
ドローン旋律は管楽器
(オーボエ・ダ・カッチャ?)が
出している感じですね。
通奏低音に
かなり大ぶりな
アーチリュートが加わっていて
目を引きます。
今回観てて気づきましたが
オランダ・バッハ協会のソリストは
合唱団とは別ではなく
合唱団のメンバーでもある
いわゆるコンチェルティスト
というやつですね。
スイス・バッハ財団の方も
今回は貼り付けておくことにします。
念のためアドレスも。
バッハ財団の方だと
第2部は28分10秒あたりから
始まりますが
例によってなぜか
素朴さが漂っています。
アルトのアリア(子守唄)は
こちらの方が声質的に好みです。
(歌うはマーゴット・オイツィンガー)
バッハ財団は
合唱とソリストを分けており
羊飼いのところに来る
先ぶれの天使を歌う
ソプラノのレチタティーヴォは
ソロ扱いでした。
ガードナー盤では
ライナーにソリストとして
名前があがってますが
モンテヴェルディ合唱団の
ソプラノ・パートに名前が見られますから
ゲスト・ソリストではありません。
(ヘレヴェッヘ盤については
先に書いた通りです)
バッハ財団版では
少し高いところから歌うのが
いかにも天使らしい演出です。
それに
リア・アンドレスのソプラノは
今回に限ってもかもしれませんが
ボーイ・ソプラノに近い
という印象を受けます。
フラウト・トラヴェルソの
2人の女性奏者は
こちらのブログによれば
鶴田陽子と向山朝子で
テノールのソロの伴奏は鶴田陽子
と書いてありますけど
鶴田洋子の間違いではないかしら。
バッハ・コレギウム・ジャパンの
フルーティストとして活躍し
鈴木優人夫人となった方ではないか
と思うからです。
以前、観たことがある
出演した際の印象と
なんとなくかぶったもので。
と思って検索してみたら
こちらのプロフィール紹介に
「スイス・バッハ財団のレコーディング、
コンサートに定期的に出演」
とありますから
間違いないですね。
で、このプロフィール紹介に
「スイス・バッハ財団」とありますので
当ブログでも今後は
「スイス」とつけることにします。
もう一人のフルート奏者
向山朝子[むこうやま ともこ]は
バッハのカンタータ集で演奏を担当していた
バーゼル・カプリコルヌス・コンソートの
メンバーです。
こうやって
以前、知り得たことと
つながっていくのは
嬉しいものですね。