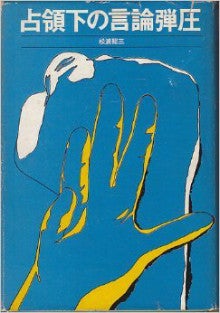読んだ本
増補決定版 占領下の言論弾圧
松浦総三
原題ジャーナリズム出版会
1974年1月
初版:1969年4月
松浦総三(MATSUURA SOUZOU, 1914-2011)は、ジャーナリスト。改造社に勤務後、フリーとなる。「東京空襲を記録する会」を主宰。
ひとこと感想
当時の時代の空気が非常に生々しく伝わってくる一方で、「言論」がいかに弾圧されたのか、その実際の「証言」としては、史料的確証性のもちにくい内容だった。プランゲ文庫にも足繁く通い検閲の痕跡を追いかけているのに、その良さが十分には伝わってこなかった。
***
これまで、原爆投下に対するGHQ検閲に関する研究をいくつか読んできた。
封印されたヒロシマ・ナガサキ(高橋博子)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11578469307.html
禁じられた原爆体験(掘場清子)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11964877796.html
原爆 表現と検閲(堀場清子)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11209824550.html
「天皇と接吻」第4章「原爆についての表現」(平野共余子)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11614953433.html
また、原爆投下直後の報道については、以下の二人をとりあげた。
The Atomic Plague, Wilfred Burchett, London Daily Express, 1945.09.05
http://nukes.hatenablog.jp/entry/2013/04/20/121541
ナガサキ昭和20年夏(ジョージ・ウェラー)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11715922026.html
***
1965年頃と1946年頃との「精神的気流」の違いを松浦は次のように説明している。
「昭和40年代の今日、自民党の代議士が"憲法9条を守れ"と叫んだら、世間はかれを狂人とよぶだろう。反対に、革新系文化人がアメリカの原爆投下を肯定したならば、たちまちにしてかれは"アメリカ帝国主義の手先"というレッテルをはりつけられるだろう。・・・ところが24年まえの現実は、保守党はぜんぶ"狂人"であり、革新系文化人はすべて"アメリカ帝国主義の手先き"であった。」(34ページ)
国会答弁。日本共産党の野坂銀が「防衛戦争は認めよ」と質問する。
それに対して吉田茂首相は次のように答えている。
「国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、私はかくの如きことを認むることが、有害であると思うのであります。」(34ページ)
一方で、武谷三男の発言にもふれている(「革命期における思惟の基準」)。
「武谷のいわんとするところは、ヒロシマ・長崎への米国の原爆使用を非難するまえに、日本人は中国などを侵略した残酷な行為を事故批判しなくてはならない、原爆はこういう日本の非人道的な政治機構をうちこわしてくれた、というものであった。」(36ページ)
***
本書では、第三章「原爆、空襲報道への統制」において、原爆投下と検閲の問題を扱っている。
「日本で、原爆報道についてさいしょに報道統制を行ったのは、おかしなことに被害者である日本政府だった。」(167ページ)
松浦はこう書いているが、これは不正確であろう。
「被害者」は「日本政府」ではなく、「日本国民」ならびに当時広島、長崎にいた人たち、である。
「日本政府」は、ポツダム宣言を無視した時点で、言ってみれば「加害者」である。
***
本書では、まず、当時の新聞報道についてふれ、続いて、バーチェットとウェラーによるルポをとりあげ、その後、いくつかの文学作品をとりあげる。
さんげ 正田勝枝
夏の花 原民喜
屍の町 大田洋子
原爆三題
サムライの末裔 芹沢治良
長崎の鐘 永井隆
「サムライの末裔」については、知らなかった。
「原爆を受けた女性が白人の占領軍の兵隊に強姦されて情婦になり、そのご再び黒人兵に犯されて黒い赤ん坊を生むという話であった。この小説は占領下の日本では発行できなかったが、フランスで出版されてベスト・セラーになったという。」(189ページ)
松浦は、長崎の鐘、屍の町、ヒロシマが出版され、ソ連が原爆を所有していることが明らかになった「1949年」を大きな旋回点としている。
「占領軍にとっては、もはや原爆を秘密にすることの意味もなくなった年であった。だから、占領軍としては、一方では原爆のおそろしさを日本人に知らせて威嚇しながら、一方ではアメリカは平和のために原爆を投下したということを宣伝しつつ、原爆にかんする出版を部分的に許可したのであろう。」(190ページ)
だが、それ以上にもっと大きな意味をもっている。
「日本が完全にアメリカの傘のしたに入ることが決定した年」(190ページ)である。
***
少し飛んで、次に、1952年に話題が移る。松浦もスタッフとしてかかわった「原爆特集・この原爆禍 改造 1952.11増刊」のほか、以下のものが挙げられている。
原爆の子、原爆の子にこたえて 長田新
原子雲の下より 峠三吉編
原爆に生きて 山代巴編
広島 アサヒグラフ、岩波写真文庫
広島原爆第一号 海野編
長崎の原爆 北島宗人編
ほか、映画として「原爆の子」「ひろしま」「長崎の鐘」「原子爆弾の効果」が上映された。
***
ほか、松浦は、1945年3月10日の東京大空襲をはじめとする本土空襲について、報道を規制したと指摘している。
残念ながらブログではそこまで守備範囲を伸ばす余裕はないが、少なくとも、原爆と倫理の問題を考える際には、空爆の是非も大いに問われているため、ヒロシマ、ナガサキ、に至るまでに繰り広げられた空爆についても、必ずふれなくてはならない。
***
目次
27年目の証言――決定版への"まえがき"にかえて
序章 敗戦から民主化時代へ
1 占領下言論の検閲と弾圧
2 マッカーサー司令部と外人記者の対立
3 原爆、空襲報道への統制
4 民主的映画人と放送人への弾圧
5 総合雑誌にたいする弾圧と抵抗
6 レッド・パージの演出者と犠牲者
7 朝鮮戦争下のジャーナリズム
8 民主的言論から中間文化時代へ
9 『改造』の崩壊と20年代の終焉
増補決定版 占領下の言論弾圧
松浦総三
原題ジャーナリズム出版会
1974年1月
初版:1969年4月
松浦総三(MATSUURA SOUZOU, 1914-2011)は、ジャーナリスト。改造社に勤務後、フリーとなる。「東京空襲を記録する会」を主宰。
ひとこと感想
当時の時代の空気が非常に生々しく伝わってくる一方で、「言論」がいかに弾圧されたのか、その実際の「証言」としては、史料的確証性のもちにくい内容だった。プランゲ文庫にも足繁く通い検閲の痕跡を追いかけているのに、その良さが十分には伝わってこなかった。
***
これまで、原爆投下に対するGHQ検閲に関する研究をいくつか読んできた。
封印されたヒロシマ・ナガサキ(高橋博子)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11578469307.html
禁じられた原爆体験(掘場清子)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11964877796.html
原爆 表現と検閲(堀場清子)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11209824550.html
「天皇と接吻」第4章「原爆についての表現」(平野共余子)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11614953433.html
また、原爆投下直後の報道については、以下の二人をとりあげた。
The Atomic Plague, Wilfred Burchett, London Daily Express, 1945.09.05
http://nukes.hatenablog.jp/entry/2013/04/20/121541
ナガサキ昭和20年夏(ジョージ・ウェラー)
http://ameblo.jp/ohjing/entry-11715922026.html
***
1965年頃と1946年頃との「精神的気流」の違いを松浦は次のように説明している。
「昭和40年代の今日、自民党の代議士が"憲法9条を守れ"と叫んだら、世間はかれを狂人とよぶだろう。反対に、革新系文化人がアメリカの原爆投下を肯定したならば、たちまちにしてかれは"アメリカ帝国主義の手先"というレッテルをはりつけられるだろう。・・・ところが24年まえの現実は、保守党はぜんぶ"狂人"であり、革新系文化人はすべて"アメリカ帝国主義の手先き"であった。」(34ページ)
国会答弁。日本共産党の野坂銀が「防衛戦争は認めよ」と質問する。
それに対して吉田茂首相は次のように答えている。
「国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、私はかくの如きことを認むることが、有害であると思うのであります。」(34ページ)
一方で、武谷三男の発言にもふれている(「革命期における思惟の基準」)。
「武谷のいわんとするところは、ヒロシマ・長崎への米国の原爆使用を非難するまえに、日本人は中国などを侵略した残酷な行為を事故批判しなくてはならない、原爆はこういう日本の非人道的な政治機構をうちこわしてくれた、というものであった。」(36ページ)
***
本書では、第三章「原爆、空襲報道への統制」において、原爆投下と検閲の問題を扱っている。
「日本で、原爆報道についてさいしょに報道統制を行ったのは、おかしなことに被害者である日本政府だった。」(167ページ)
松浦はこう書いているが、これは不正確であろう。
「被害者」は「日本政府」ではなく、「日本国民」ならびに当時広島、長崎にいた人たち、である。
「日本政府」は、ポツダム宣言を無視した時点で、言ってみれば「加害者」である。
***
本書では、まず、当時の新聞報道についてふれ、続いて、バーチェットとウェラーによるルポをとりあげ、その後、いくつかの文学作品をとりあげる。
さんげ 正田勝枝
夏の花 原民喜
屍の町 大田洋子
原爆三題
サムライの末裔 芹沢治良
長崎の鐘 永井隆
「サムライの末裔」については、知らなかった。
「原爆を受けた女性が白人の占領軍の兵隊に強姦されて情婦になり、そのご再び黒人兵に犯されて黒い赤ん坊を生むという話であった。この小説は占領下の日本では発行できなかったが、フランスで出版されてベスト・セラーになったという。」(189ページ)
松浦は、長崎の鐘、屍の町、ヒロシマが出版され、ソ連が原爆を所有していることが明らかになった「1949年」を大きな旋回点としている。
「占領軍にとっては、もはや原爆を秘密にすることの意味もなくなった年であった。だから、占領軍としては、一方では原爆のおそろしさを日本人に知らせて威嚇しながら、一方ではアメリカは平和のために原爆を投下したということを宣伝しつつ、原爆にかんする出版を部分的に許可したのであろう。」(190ページ)
だが、それ以上にもっと大きな意味をもっている。
「日本が完全にアメリカの傘のしたに入ることが決定した年」(190ページ)である。
***
少し飛んで、次に、1952年に話題が移る。松浦もスタッフとしてかかわった「原爆特集・この原爆禍 改造 1952.11増刊」のほか、以下のものが挙げられている。
原爆の子、原爆の子にこたえて 長田新
原子雲の下より 峠三吉編
原爆に生きて 山代巴編
広島 アサヒグラフ、岩波写真文庫
広島原爆第一号 海野編
長崎の原爆 北島宗人編
ほか、映画として「原爆の子」「ひろしま」「長崎の鐘」「原子爆弾の効果」が上映された。
***
ほか、松浦は、1945年3月10日の東京大空襲をはじめとする本土空襲について、報道を規制したと指摘している。
残念ながらブログではそこまで守備範囲を伸ばす余裕はないが、少なくとも、原爆と倫理の問題を考える際には、空爆の是非も大いに問われているため、ヒロシマ、ナガサキ、に至るまでに繰り広げられた空爆についても、必ずふれなくてはならない。
***
目次
27年目の証言――決定版への"まえがき"にかえて
序章 敗戦から民主化時代へ
1 占領下言論の検閲と弾圧
2 マッカーサー司令部と外人記者の対立
3 原爆、空襲報道への統制
4 民主的映画人と放送人への弾圧
5 総合雑誌にたいする弾圧と抵抗
6 レッド・パージの演出者と犠牲者
7 朝鮮戦争下のジャーナリズム
8 民主的言論から中間文化時代へ
9 『改造』の崩壊と20年代の終焉
- 占領下の言論弾圧 (1974年)/現代ジャーナリズム出版会

- ¥2,052
- Amazon.co.jp